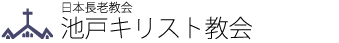2024/4/14ヨハネの福音書15節26〜16章4節「つまずくことのないためです」
イエス・キリストが十字架に死ぬ前夜、弟子たちと過ごした最後の晩餐の席での「告別説教」を続けて聞いています。その説教の中心は
「わたしがあなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい」
です。その戒めの中で、イエスは弟子たちへの憎しみの逆風を予告しました。今日の15章26、27節
「わたしが父のもとから遣わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来るとき、その方がわたしについて証ししてくださいます。27あなたがたも証しします。初めからわたしと一緒にいたからです。」
も、迫害を踏まえての言葉です。
「証し」はヨハネが繰り返す言葉ですが[i]、これが語源になって殉教、殉教者という英語が生まれました[ii]。ある真実のため、命をかけて証しを貫く。それが殉教という言葉なのです。でも誤解したくないのは、ここで、私たちが殉教してでも自分の信仰を捨てるな、証しせよ、と言われているのではない。イエスが言うのは助け主、真理なる聖霊の神を遣わして、
「わたしについて」
つまりイエスについての証しをしてくださる、という事です。日本語の殉教といえば、キリスト教信仰や自分の宗教のために死ぬこと、命を奪われても信仰を捨てないこと、という意味です。しかし、私たちはキリスト教という宗教を信じるキリスト教徒、というよりも、イエス・キリストという私たちに証しされた方を信じるキリスト者です。イエスは私たちにいのちを下さいました。それは、私たちが頑張って信心し、犠牲や殉教も厭わずに信仰心を守れば、死後の天国を下さる、という意味での来世の命ではなく、今既に、生かされているいのちです。喜びと平和、赦しと希望を戴いて、生き生きと生かしてくださるのです。裁かずに救う方、切り捨てず見捨てない方、私たちの羊飼いであり、どんな傷や過去をも癒して、何度でも立ち上がらせたもうイエスです。このイエスを、聖霊は証ししてくださり、私たちにも証しさせてくださるのです。
十六1わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがつまずくことのないためです。2人々はあなたがたを会堂から追放するでしょう。実際、あなたがたを殺す者がみな、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。
この予告は、能天気な信仰で苦難などないと高を括り、いざという時に「聞いていないよ~」とならないため、という事もあるでしょう。しかしここで言われるのは「追放され…殺される」時であって、信仰を棄てるよう迫られる時ではないし、イエスも「どんなに脅されても信仰を貫いて殉教せよ」と命じるのではありません。そういう殉教なら弟子たちが憧れた英雄の死でした。13章37節でペテロは
「あなたのためなら、いのちも捨てます。」
と胸を張りました。イエスはそんな弟子たちに「頑張る信心」から、「イエス」を信頼し、イエスの証しに留まる関係を語って来たのです。それはここでも同じです。
イエスがこれらのことを話したのは、会堂からの追放とか、処刑されるとしても、動揺せず怖気ないため、以上に、その時も自分たちが必死に信仰にしがみつかなければと自分たちの信仰心ばかりを考えて、イエスを忘れてしまわないためです。キリスト者を殺すことが神に奉仕することだ、というのが
3彼らがそういうことを行うのは、父もわたしも知らないからです
の宗教心であるように、私たちが頑張って信仰告白を貫かなければ天国に行けない、という発想も、
父もわたしも知らないから
の宗教的な思い込みです。イエスを聖霊が証ししてくださらなければ、私たちは、人間に殺されるのも嫌だけど、神様を怒らせて天国に行けないのも怖い、どちらでも死にたくない、生き延びたい、板挟みで苦しい選択をするだけになるでしょう。だから聖霊がイエスについて証ししてくれることが必要なのです。
4これらのことをあなたがたに話したのは、その時が来たとき、わたしがそれについて話したことを、あなたがたが思い出すためです。
イエスは十字架の苦しみを我慢したのではなく、神を冒涜する失敗者だという汚名を着せられても、そう嘲る人々を心から愛し、その救いのために命を捧げました。イエスから私たちが戴くのは、死にたくない、という恐れへの解決より、私たちのためにイエスが命を捨て、死や恐れ、罪や嘲り、憎しみから救われた、いのちです。それが私たちも互いに支え合い、いのちを贈り合う新しい生き方にまで身を結ぶのです。初代教会の多くのキリスト者が、徐々に迫害が強まる中でも、ますます主への信仰に留まりました。いただいた喜びのゆえに、死をも厭わなかった、生き生きとした姿こそが、それを見ていた人々の心に衝撃を与えて、自分もああなりたい、とイエスへの信仰を持たせることになったのです。
勿論そうは願っても、厳しく狡(ずる)い迫害のため、信仰を棄てた人々もいたのが事実です。牧師さえ信仰を否んだ人が少なくありません。その後、迫害が鎮まり棄教した人々が帰って来た時、厳格な人々は激しく反対しました[iii]。どんなに迫害が厳しかろうと、それで主を棄てた人は受け入れられない、そんな人の洗礼は無効だ。そんな牧師の授けた洗礼も無効だ、と主張した。「ドナチスト派論争」です[iv]。これに対して教会は話し合いを重ね、厳しい迫害で信仰を翻したからと、その人の救いが否定されるのではない、としました。大事な信仰を強いてでも棄てさせることは、そうさせる側が悪いのであり、本人にとって苦渋の決断なのを、一概に責めることは本末転倒です。それでは安易な棄教を促す、との反対もありましたが、それでも、赦しと恵みのイエスにこそ私たちの救いはある、という信仰の土台に立つこととしたのです。その後も教会は厳しい迫害を経験しますが、先の決断は安易な妥協や棄教には繋がらず、そんな主だからこそ、滅びや罰を恐れてではなく、主への愛から多くの人が主を証ししたのです。
その末に日本にキリスト教が伝えられました。切支丹への禁令が出され、厳しい迫害で転んだ人も、信仰を棄てずに殉教した日本人も多くいた、激しい尊い証しです[v]。
その切支丹の歴史をある小学生が知りました。それを自分の原体験として書き始める本が昨年出版されました。『性暴力を受けたわたしは、今日もその後を生きています』。池田鮎美さんが自分の壮絶な体験と戦いを綴る本です[vi]。著者は、圧倒的に不利な力関係の中で大切なものを奪われます。なのにその暴力が責められるより、被害者側が責められ、黙らされる社会が立ちはだかります。自分の体や大切な信仰を踏み躙られてもいい人などいないのに、本人に落ち度があるかのように扱われ、声が聴かれないという暴力に直面します。被害の声をあげさせない社会が、結局暴力を許容していることに気づき、それを仲間と共に声に綴り、ここ数年の法改正や意識の変化に繋がったのです。その切欠(きっかけ)に、キリスト者の迫害と抵抗の証しがあったし、その本を通して私たちはヨハネがいう「証し」が何であったかを教えられるのです。[vii]
イエスは、踏み躙られていた人の友となりました。生まれつきの病人、女性たち、売春婦や売国奴、犯罪者、罪や過去の重荷を追いきれずに潰れそうな人の友となりました。罪の赦しを与え、立ち上がらせ、黙らされていた声を言葉にさせた方でした。過去からの赦しも、自分の憎しみからの赦しも下さって、殉教の時にも「この罪を彼らに負わせないでください」と祈らせるイエスです[viii]。私たちに証しされているイエスはそういう方です。圧倒される状況で孤独で卑怯な脅しで信仰を棄てるよう強いられる時、その時も、どうすれば自分を守れるかばかり考えて、身を強張らせてしまいやすい。だからこそ、聖霊が、この恵み深く、共に苦しみ、どう言われようと私たちの友となったイエスについて証ししてくださいます。私たちもそのイエスを証しすることを求めたい。それは、迫害の時だけの事ではなく、普段から――一見、平和そうで、実は強い人と弱い人がいて、黙らされている人がいるような中から、私たちが聞かなければならない聖霊の証しであり、私たちに託されている証しです[ix]。一人でではなく、共に証ししていくのは、このイエス…私たちに声を与え、弱い者を躓きから守り、虐げられていた者を立ち上がらせ、自分を恥じることなく光の中を歩み、踊らせ、歌わせてくださるお方です。
「主よ、逆境を迎えても、あなたを見上げさせてください。嬉しいことでありませんが、その時が来たら、あなたのいのちの証しとされたいのです。自分が信仰を守る以上に、あなたがこの世界を癒してくださることを、切に待ち望みます。今ここで、私たちを恵みによって強めて、命への暴力や一切の狡(ずる)い言葉から解き放ってください。一人ではなく、聖霊が証しし、私たちがともに証しをする時、主の恵みが驚くほど豊かな証しの力となることを見させてください[x]」
[i] https://blog.goo.ne.jp/kaz_kgw/e/38164463a3611a7f26e38b27da03f8dd
[ii] martyr(殉教者), martyrdom(殉教).
[iii] 「教会は全く不意打ちをされたのでした。其の直前の五十年間は平穏無事で、厳しい取締は絞められていたのです。キリスト教徒は異教徒によく親しむようになって、時には異教徒と結婚した者さえありました。試煉に対する緊張した心構えがありませんでした。それで迫害が起るや、多くの者がくづおれました。或る者達は競って犠牲をささげました。司教でさえも自分の教会員を率いて、異教の祭壇に拜跪した者がありました。或るキリスト教信徒は屈服を肯じなかったので、牢獄に投ぜられました。或る者は暫らく拷問を耐え忍びました。また他の者は非常に面倒なことをしました。彼らは犠牲をささげませんでしたが、ささげたという証明書を手に入れました。役人達はしばしば融通をきかせて、キリスト教徒を殺そうとしませんでした。彼らはキリスト教徒に向かってこんな事を云ったのであります。「お前がキリスト教徒であることは、よく解っている。犠牲を捧げる必要はない。いくらか金を出しなさい。そうしたら犠牲を捧げないでも証明書を与えよう」
そこでキリスト教徒はこう考えました。「司教は犠牲を捧ぐべきでないと云った。自分も捧げようとは思はないが、司教は証明書を手に入れてはいけないとは云わなかった。証明書を入手することが、キリストを否むことにはなるまい。役人は自分がキリスト教徒であることを知っている。彼は自分が斬首されないでキリスト教徒として立ってゆくために、料金を拂わせようとしているのだ。キリストを否まない限り、そうしてもいいだろう」ところで問題は其の証明書に、其の人物が犠牲を奉献したと、まことしやかに記されてあることなのです。
迫害は長く続きませんでした。それで全くおさまつた時には、一旦信仰を棄てた人々が教会に復帰することを望みました。彼らは其の心の中に主を愛していて、教会は外部の者がみんな滅びてしまったノアの箱舟のようなものと信じていました。この人々は箱舟に帰りたいと思い、此の箱のように司教に懇願しました。
教会はどうすべきだったでしょうか? 此のような背教者が赦さるべきものでしょうか? もちろん神は赦し給うことが出来ますが、教会はどうでしょうか? 第三世紀の司教達によって与えられた答は、キリストがペテロとその後継者、特にロオマの司教に天国の鍵を与えたのであって、彼らが地上に於て赦すところのことは天においても赦されるというのでした。そこで司敎達は、此の人々が喪服を纏い頭に灰を被って、会衆の前に改俊の情を示すならば、背教者を敵そうということになりました。これが懺悔及び教刑と呼ばれたものであります。最初、懺悔は会衆の前に公然と行われたものですが、後には牧師即ち祭司の前で個人的に行われるようになりました。
或るキリスト教徒達は此のような放蕩息子どもが赦されたことを、大変に怒ったのでした。そのような手緩いことでは、次に迫害が起った場合に背教を奨励するようになり、教会は虚弱な者の寄り集まりとなってしまうだろうというのです。強硬派は脱退して自分の教会を創設し、その分立教会は其の後も長く続いて存在しました。七十五年後にコンスタンティヌス帝はキリスト教徒になっていて、此のグループをカトリック教会に合同させようとしました。まず何処に支障があるかを尋ねてみました。信仰上に何か相違点があつたのでしょうか? 何もありませんでした。それでは問題は何であつたのでしょうか? それはただ、迫害に際して信仰に誠実であつた人々の孫達が、背教した人々の孫達と折り合わないということだけでした。皇帝は立腹して強硬派の司教に向い、しからば其の方たちだけ梯子を設けて天国に昇って行ったらよかろうと云いました。
この時の迫害に続いて、また中世紀の平穏な時がありましたが、ディオクレティアヌス帝が迫害を始めたので、またしても悲惨な物語が繰り返されることになったのであります。此の皇帝は教会堂と聖書を一冊も残さず潰滅させようとしたのでした。教職の間の或る者さえも、聖書を棄ててしまいましたが、迫害が終ると教会への復帰を切望しました。信徒即ち一般のキリスト教徒は、教会に復帰させてもよいということが、すでに決定していたのですが、教職の方はどうであつたでしょうか? 結局、教職もまた赦されることになりました。然るに、今度は北アフリカにドナトゥス派と呼ばれる反対派の新教派があらわれました。アフリカの貧民や不平分子が盡く此の一派に群れ集い、その或る者ははなはだ我がままな無法者であって、他の教派の司教達の眼に梁木を投げ込もとする徒輩でありました。全ロオマ帝国がキリスト教化された後にさえも、ドナトゥス派は非常に厄介な存在であつて、死刑を以て取締るほどでありました。 ※ ドナトゥス派は第四世紀の初期にカルタゴの司教であったドナトゥスの起こした分派であって、教会の規律を厳にして偏狭に陥りました。背教者の洗礼を無効として譲りませんでした。其の発展は著しく、三三〇年の大会議にはこの派に属する司教の参集する者二百七十人の多きに上りました。
多くの者が背致しましたが、決して全部が背教したのではありません。或る者は信仰を告白するであろうと期待されていながら、それを否んだとしても、他の者は信仰を否むと思われていながら、立派に告白したのです。」 R・H・ベイントン『世界キリスト教史物語』(気賀重躬訳、教文館、昭和二七年)、32〜36ページ。
[iv] 指導者の司教ドナトゥスの名から。
[v] 「鎌倉在住の作家であった大仏次郎さんが『天皇の世紀』という長い歴史的記録を書き続けられました。今も読まれているかどうか知りません。感銘深い日本の歴史の記録であると思います。その第九巻に「旅」と題する章があります。この旅という意味は、ひとつは作家自身が旅をしているという意味もあります。しかし、それだけではありません。一八六九年頃、もう明治維新が起こっておりました。新政府が生まれていた。しかし、新しくキリシタン弾圧が始まった。長崎の浦上に隠れキリシタン、三世紀に近く信仰を貫いた人びとが姿を現した時、忽ち彼らが信仰の自由を謳歌し得たのではない。記録によって違うようでありますが、ほぼ四千人の浦上村の人びとが根こそぎ捕らえられて各地に送られた。金沢にまいりましてもそのキリシタンの人びとが入れられた牢の跡が残っております。
長崎空港の近くにも小さな丘がありまして、ここにキリシタンが囚われていたという遺跡があります。東京にも送られた人びとがおります。こうした強いられた旅をした人びとの記録でもあります。是非お読みいただきたいと思います。
この旅の記録にこんなのがあります。津和野に囚われていた人びとがある。若い人が多かったらしい。キリストに対する信仰を捨てることを求めて激しい弾圧をする。拷問が続く。三尺牢と言われる高さ三尺の牢に大人を閉じ込めて、二〇日も放り出しておく。そして信仰を捨てることを求める。大仏さんの記録を見ると、この時この人二一歳、この時この人二三歳、などと書かれています。これらの若者が信仰の節操を捨てず死んでいくのです。この仲間の数人が牢を脱出することに成功いたします。それは同じ仲間が各地に送られているが、その人たちの消息を知り、慰めてあげたいと思ったからだそうです。それからもうひとつ、神戸にフランス人の神父が教会堂を建てることを許されて、フランス寺という教会堂を建てていた。そこで既にミサをあげていると聞いて、どうしてもそれを訪ねたかった。このフランス寺におりましたヴィリヨンという神父がこの人たちの訪問を受けた記録を残しております。ミサをあげ終わった夕刻、薄暗がりの中にこの人たちが突然姿を現したので驚いた。そしてこの人びとが自分に訴える言葉に、自分たちの苦しみについて訴える言葉は何ひとつなかった。ただ飢えと苦しみのゆえにとうとう信仰を捨てると言わざるを得なかった人びとのために祈ってほしいとひたすら願った。自分たちは信仰の節操を曲げていない、彼らは捨てた、と言って誇りに満ちた殉教者気取りになっているのではなくて、彼らが飢えと苦しみに耐えられず、主イエスを否認したということをよく理解してあげてほしい。彼らの名に代わって彼らの名をもってそのことを訴え続けた、とこの神父は書いています。そしてもし彼らがやがて信仰に帰ることができるならば、そのために自分たちがその償いのわざでもなし得るならばそれを教えてほしい、と言うのです。こうしてこの人たちは訪問を重ねて、驚いたことに再び牢屋に戻ったと書いてある。大仏さんは、役人もびっくりしたに違いないと記しておられます。
これらの記録について事細かに紹介するいとまはありませんが、この部分の最後に大仏さんが書いた言葉はたいへん印象に残ります。なぜこの事件にこんなにも長くこだわって書いたのか。進歩的な維新史の研究者もまたこれを取り上げてはいないからだと言われます。私はプロテスタントの歴史家もこのことについて十分な配慮をしてこなかったと思っています。実に三世紀に及ぶ武家支配のもとで、日本人が一般に歪められて卑屈な性格になっていたときにあって、浦上の農民がひとり人間の権威を自覚し、迫害に対しても決して妥協も譲歩も示さなかった。日本人としてはまったく珍しく抵抗を貫いた。当時、武士にも町人にも、これまで強く自己を守って生き抜いた人間を発見するのは困難である。大仏さんは、そう絶賛しておられます。実際に大仏さんが描いているキリシタンたちは卑屈な弱い信仰者ではありません。若い農民の身でありながら、自分と向かい合っている年配の武士と堂々と信仰の論争をやります。むしろ武士たちの方が恐れを抱いている光景が描かれております。人間の権利を知っていた。それは今日私どもの世界に横行するあっちで何の権利、こっちで何の権利を主張するのとはどうも様子が違う。主イエス・キリストを知っている。主イエス・キリストの十字架を知っている。目に見えないが〈確かないのちの世界〉を知っている。そこに生まれる人間の自覚であります。これは天皇といえども脅かすことはできない。これが、明治維新より遥か以前にカトリック宣教師たちが蒔いていた種が三世紀の歴史を貫いてなお生んでいた実りであります。ここにも証人の姿があります。これらの人びとの名は殉教者の名として記録されているものではありません。しかしこの見事な証人の歩みは、私どもにも与えられていると信じてよいのではないだろうかと深く思っております。
この証人たちはひとりでは立っていません。あるいは自分たちだけで同志の決意固く一致団結しているというのでもない。繰り返して申します。フランス人の神父を深く驚かせたのは、その同志の一致から落ちこぼれた人びとのためにまず祈ってほしいと司祭に頼んでいる姿です。人が罪を犯すということについての深い痛みと同情があります。しかもそのような人びとすら、主イエスの恵みから落ちているはずはなかろうと、教会の司祭に訴えるのであります。あなたもその人たちのために祈ることができる方でしょうが、と信じて訴えているのであります。それが教会の姿です。今私どもは新しい若い伝道者を迎えてこの教会の新しい望みの歴史が開かれることに心躍る思いがいたします。しかしそこで、真実に謙遜に聞くべきものを聞き、立つべきところに立ちたいと思う。あなたがたは皆わたしの証人。父なる神・主イエス・キリストがそうおっしゃってくださる言葉を、今日立てられる若い伝道者と共にしっかり心に刻みたいと思います。」加藤常昭『ヨハネによる福音書4』(教文館、2005年)、160〜163ページ
[vi] 「性暴力を受けたわたしは、今日もその後を生きています」
「ある日の昼休み、校長先生が図書室にやってきた。
「お勧めの本はどれですか?」
わたしはドキドキしながら東の端にある棚のところへ歩いていき、自分にとって特別な一冊を取り出した。それは、隠れキリシタンについて書かれた歴史小説だった。江戸時代の終わり、禁じられたキリスト教を信仰していた長崎の離島の人びとは、上手に信仰を隠しながら、自分の心の平穏のために大切に信仰を守って暮らしていた。しかし物語が進むと、領主の命によってたくさんのキリシタンたちが殺されてしまう。
わたしはその本を、すでに何度も繰り返し読んでいた。どうしてこんなことが許されてしまったのかと驚いたからだ。次に、自分の心の真実を禁じられながら生きた人たちについて考えた。江戸時代の終わりに彼らの生きざまを目撃した人たちがいて、書き遺し、語り継ぎ、それが後世において、こうしてひとりの小学生に届けられた。超えるんだ。歴史を動かすんだ。
それは奇跡に思えた。言葉ってすごい。時間も空間もただ、感動しながらも、その爆発的な気持ちをどう扱っていいかわからず困っていた。当時のわたしには、伝わるかどうかということは、とても重要な問題だった。ある「言葉にできない気持ち」が芽生えはじめていたからだ。それをどう伝えるべきかと悩み、言葉を探しながら、図書室の本を手当たり次第に読み漁っていた。
ドキドキしながら本を手渡すと、校長先生は、
「じゃあぜひ読んでみます」
と言ってそれを受け取った。
この時わたしは、将来は本を書く人になりたいと初めて思った。」池田鮎美『性暴力を受けたわたしは、今日もその後を生きています』(梨の木社、2023年)、10~11ページ
「これまで自分は、当事者の言葉をそのまま、手を加えずに伝えることに気をつけてきた。原体験は小学生の頃、隠れキリシタンの言葉を読んだことだったと思う。あの時わたしは、それを言葉のリレーととらえて感動した。二○○年近くの時を経て言葉が伝えられた、その事実に感動したのだ。だから、大学生の時、社会的弱者の言葉はマジョリティに届かないというスピヴァクの訴えを読んだ時にも、あくまで弱者の言葉をそのまま逐語的に伝えることが大事だと考えた。言いよどみや支離滅裂に思える言葉遣いにも、当事者なりの意味が宿っている。当事者にとっては、言葉は手段ではなく、目的だからだ。そうした当事者の言葉に手を加えることはリスペクトのない行為だと考えた。なぜ言いよどんだのか、なぜ普通とは違う言葉遣いをしたのかを理解しようとする態度が大事だと感じたし、それ以前に、当事者の言葉を伝えること自体が社会において阻止されているのであれば、ジャーナリストとして風穴を開けたいと考えていた。だから福島の人たちを取材する時にも、常にボイスレコーダーを回し続けた。裁判ではボイスレコーダーを回せないので、泣きながらメモを取り続けた。それもこれも、当事者の言葉をリスペクトしていたからだ。」同、131ページ
https://www.youtube.com/watch?v=-EfOls-gw8k&t=4s
[vii] 圧倒的な力関係で、肉体的な暴力、精神的な脅迫、罪悪感を逆撫でするズルい言葉によって、なす術もない中、主を裏切り、真実に背くような言動を取ってしまう時、それを本人の弱さ、背信だとするのは、全くの間違いです。私はどんな拷問によっても、主を否定したくない、妻を裏切ったり、子どもに恥ずかしい行動を取ったりはしたくない。でも、そこにさえ付け込んで、私たちを操作し、その結果の後ろめたさで、また縛ろうとする悪はあるのですし、それに太刀打ちできないこともあるのかもしれないのです。「お前がもっと抵抗すればよかったのだ。おまえの責任だ」と。しかし、それは主の声ではなく、悪の声です。言葉を奪われるような状況から立ち戻ったら、また口を開きたい。あの言葉を撤回します、私の本当に言いたいのは、主こそこの私たちのただ中に、どん底に来てくださり、私たちのため、いのちを捧げてくださった、ということです。主は、私たちにいのちを下さいます。憎しみや断罪、後悔や絶望ではなく、平安を、赦しを、感謝を、笑いを、希望を、涙も訴えも、叫ばせてくださる。そういう恵みがあります。
[viii] 使徒の働き7章59~60節:こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで言った。「主イエスよ、私の霊をお受けください。」60そして、ひざまずいて大声で叫んだ。「主よ、この罪を彼らに負わせないでください。」こう言って、彼は眠りについた。
ルカ23章34節でイエスが「父よ、彼らをお赦しください」と祈った祈りは、新改訳2017欄外注にある通り、写本的には弱いのです。しかし、使徒の働きでステファノが祈ったことは本文に確かにあります。逆ではありません。そして、ステファノにそう祈らせたのは、イエスの祈りであり、それを届けた聖霊の証しに他ならない。
[ix] 今でさえ疑いや余所見(よそみ)をしてしまい、そういう自分に自己嫌悪し、後ろめたく自責してしまっているのではないでしょうか。
[x] だからイエスは「あなたがたも証しします。」と複数形で言われています。