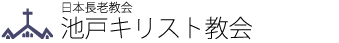2025/8/3 イザヤ書15章「主の心は叫ぶ」
イザヤは紀元前8世紀のイスラエルの人です。しかし、この15章を含む13章から25章まで続くのは、イスラエルでなく別の国々についての言葉です。今日の15章は「モアブについての宣告」と始まりますし、前の13章14章は「バビロンについての宣告」でした。筆頭のバビロンは具体的なバビロニア帝国よりも漠然と、大きな「バベル的な勢力」を指すのに対して、このモアブはイスラエルの東隣の国でした[i]。イスラエルを念頭に置きながら、周辺の国々への言葉が語られる。お隣であれば、諍いもあり交流もあり、同盟を組んだこともあれば戦ったこともある間柄です[ii]。現在の日本にいても、やはりお隣の韓国や台湾、北朝鮮や中国、ロシアの関係は、私たちに関わっています。行ったこともこれから行くこともないとしても、深い繋がりがあります。モアブのことを2頁程に亘って語る――これがイザヤ書15、16章。いや、イザヤを通して語らせる、聖書においてご自分を啓示される神、天地万物の造り主であり、唯一の生ける真の神、主という方です。神である主は、イスラエルの隣にも、私たちの周辺にも、教会の周囲にも、目を留め、心を注ぎ、そこに関わり、御自身が神であることを現されます。
モアブへの言葉は、他の国々へと同様、厳しい言葉です[iii]。
1…「ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せる。ああ、一夜のうちにキルは荒らされ、モアブは滅び失せる。」
ここにアルとかキル、ディボンなど見慣れない地名がたくさん出て来ますが、いくつかの地名は聖書の後ろの地図に載っています。より詳しい地図も調べるとありますので教会HPの説教原稿からご覧になってください[iv]。でもどこか分からない地名もあります。けれど、有名なキル、首都のキル・モアブは断崖絶壁の上に建てられた砦だとは知られているそうです。難攻不落の都だと誇っていた。しかし、そこにアッシリアは攻めてきました。その砦を攻め落とし、モアブを打ちのめしてしまいました。そして、残された人々は「高き所」(神殿)に「泣くために上る」と2節にあります。「頭をみな剃り落とし、ひげもみな切り落として。」とは激しい嘆きの表現です。「腰に粗布をまとい」も同じです。髪も髭も剃り、粗布をまといながら、「涙を流して泣き叫ぶ。」のです。大声で、遠くまで聞こえるほどの叫びとわめき、わななく様子が、この後も想像してみよと言わんばかりに描かれます。[v]
その真ん中に、5節にこうあります。
わたしの心はモアブのために叫ぶ。
新改訳聖書は、神やイエスが「わたし」と言われる時は平仮名、人間が「私」という時は漢字、と使い分けていますから、ここでもこの「わたしの心はモアブのために叫ぶ」と言われているのは、神である主ご自身だと訳しているわけです。確かにここでの流れはいきなりイザヤが登場するよりも、語り続けているのは主なる神だ、と取る方が自然です。そして主なる神が「わたしの心はモアブのために叫ぶ」と言われます。モアブの人々が叫び、泣き叫び、泣きながら逃げていく人々とともに、主は「わたしの心はモアブのために叫ぶ」と吐露されるのです[vi]。
「でもこの禍をもたらしたのは神様御自身でしょう。アッシリアがモアブを襲うようにさせたのは主でしょう」と言う声もあるかもしれません。確かに一面はそうです。そしてそれは、モアブもイスラエルも周辺諸国も、それに相応しい罪に陥り、酷い国になっていたからです。神の裁きは公正であって過剰な厳しさではありません。人間の傲慢、国家規模での間違いは、国民や在留者や周辺諸国まで巻き込む、酷い禍を招きます。それを主は、「自業自得だ。身から出た錆だ」とは言わないのです。冷酷な裁判官、機械的に罰ばちを与え、苦しみで報いを与える――閻魔大王ならそうかもしれませんが、まことの神、主は違うのです。「わたしの心はモアブのために叫ぶ」。そして、そんな心を――人間からすれば矛盾した葛藤だと非難されかねない思い、いわば、神の弱さ、感情をあらわにすることも厭わない方なのです。その後も、
5逃げ延びる者たちはツォアルまで、エグラテ・シェリシヤまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムへの道で破滅の叫びをあげる。6ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果てて、緑もなくなる。7それゆえ彼らは、残していた物や蓄えていた物を、アラビム川を越えて運んで行く。8ああ、叫び声がモアブの領土に響き渡り、その鳴き声がエグライムまで、その泣き声がベエル・エリムまで届く。9ああ、ディモンの水は血で満ちる。…[vii]」
ここに「ああ…ああ…ああ…ああ」と四回も重ねて、悲嘆が繰り返されます[viii]。こんなに繰り返し重ねて、主はモアブの難民たちの行進を見て、心を痛めて止まないのです。決して主はモアブを怒り、神に逆らう者たちに怒りを爆発させる暴君ではない。人の罪を見逃すことなく裁きつつ、なお心を痛め、いや、「わたしの心は叫ぶ」と仰るのです[ix]。
モアブといえば、聖書を読んで行けば、いくつかの出来事があります。そもそものモアブ人の始まりは、創世記18章にあるように娘が父を酔わせて寝ている間に同衾して宿したという、姦淫によるものでした。その不道徳や偶像崇拝に触れぬよう、イスラエル人はモアブ人と一線を画すよう命じられていました。しかし主はそんなモアブ人など汚らわしいとは思わず、彼らのために叫ぶ心のお方です。またモアブ人とイスラエル人の交流の中で生まれたのが「ルツ記」です。モアブ人ルツが姑に仕える美しい姿が語られ、ルツはイスラエル人ボアズと結婚し、その三代目がダビデ王です。ダビデ王の末裔がイエスですから、新約聖書の一頁目の系図には、モアブ人ルツの名前もしっかりと刻まれています。そのルツの家族、またルツとは別れてモアブに残った兄嫁オルパの子孫が、この時のモアブにはいたのでしょう。ルツとは違う道を選び、モアブで神に背いた歩みをしてきた人々のためにも、主の心は叫ぶのです。
モアブへの裁きは、こことよく似たエレミヤ書48章に告げられます[x]。預言書を最後に、モアブは新約聖書には出て来ません[xi]。現在もモアブの地は荒れ地です[xii]。しかしそうした結果を見る時にこそ、忘れてはならないのは、この「わたしの心はモアブのために叫ぶ」と仰った主の言葉でしょう。主がこんな風に仰る言葉は、イザヤ書だけでなく、旧約聖書全体でもここ以外にありません。しかし、モアブ以外のためには叫ばれない、ということではないでしょう。この後続くダマスコやエジプトについても、叫ばれる主が見えます。預言書は、主の叫びそのものです。勧善懲悪を超えて、熱い憐みの神である主の心が叫んでいるのが、預言書です。それは、モアブの神ケモシュや周辺のどの民族の神、また日本や世界の宗教とも違う、人間の考え付かない、人知を大きくはみ出して私たちに迫って来る、真の神を証ししています。
神は罪人が滅びるのを望まない。これは、旧約でもエゼキエル書18章23節などに明言される信仰ですが[xiii]、イエスにおいて教会は「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます」と確信して言えるようになりました[xiv]。そしてその目をもって、主は今も私たちを見ています。イスラエルもイランも、パレスチナも、日本も、世界のすべての国々も、その一人一人を深く叫ぶような心でご覧です。そしてその神を現してくださったのが、神のひとり子イエス・キリストでした。イエスはそのご生涯で何度も叫んでいます。十字架の上で、人のための苦しみを担いつつ叫びました。また亡くなった少女や友人の墓の前でも叫んで生き返らせます[xv]。神の子の力ならどんな奇蹟や死者の復活だって出来るだろう、ということではなく、人間の死、神から離れた状態の悲惨、苦しさのため、御自身の心から嘆き、叫ぶ神のあわれみがありました。自業自得とは決して言わない、思いもしない神がイエスにおいて私たちに出会ってくださいました。そして、私たちにも叫ぶ心と、その叫びがやがて終わって、歌う心に変えられる希望とを与えてくださっています。
「救い主イエス・キリストの父なる神。争いや涙のある世界をも見捨てず、何とかして立ち返らせようとなさるあなたの御心に触れました。主の衣に触れた人が癒されたように、み言葉に触れる私たちを癒し、あなたの恵みを心とさせてください。また私たちの心の叫びをも、あなたに似たもの、平和といのちを求めるものへときよめてください。世界のために祈り、身近な所ではどう語り、どう生きるべきかを教え、私たちの献げる小さな業を、祝福してください」
[i] 「モアブ人はアブラハムの甥のロトとロトの上の娘との間に生まれた、モアブを先祖に持つことが創世記一九章三一節から三七節に記されています。モアブ王国は紀元前一三〇〇年に生れました。イスラエル民族との関わりは古いのです。出エジプトをしたイスラエルが約束の地、カナンに行く途中、モアブの王バラクはイスラエルを妨げ、イスラエルを呪うために、メソポタミアからバラムを雇って呪わせようとしましたが、主はバラムがイスラエルを祝福するように導きました(民数記二二章から二四章)。 このため、モアブ人は主の集会に加わることを禁じられました(申命記二三・三―四)。士師時代に、モアブの王エグロンはエリコを取り、イスラエルを一八年間服従させましたが、士師イェフダが打ち破りました(士師記三)。しかし、イスラエルとは良い関係の時代もあり、飢饉を逃れたユダのエリメレク・ナオミと二人の息子はモアブに逃れ、二人の息子の一人はルッと結婚しますが、夫が死にます。モアブ人ルツはエリメレクの妻ナオミについてユダに行き、親戚のボアズと結婚し、その子孫にダビデが生まれました。 ダビデ王の時、モアブは占領され住民は貢を納めました(Ⅱサムエル八・一三)。イスラエルの王国時代には再び対立関係が激しくなっていました(Ⅱ列王三)。イスラエルと、特にダビデとの深い関わりがあるにもかかわらず、イスラエルの信仰と共通のものは何もなく、悪影響(民数二五)と敵対関係(Ⅱ列王三)のみでした。」油井、130頁
[ii] 詩篇にはモアブの事が何度か言及されます:詩篇60・8(モアブはわたしの足を洗うたらい。 エドムの上に わたしの履き物を投げつけよう。 ペリシテよ わたしのゆえに大声で叫べ。」、ほぼ同じものが、108・9)、83・6(エドムの天幕の民とイシュマエル人 モアブとハガル人)
[iii] 「イザヤの目的は、ある状況を日付や名前をもって描き出すことにあるのではなく、歴史を用いて真理を描き出すことにある。貧しい者は身を低くして神の民とひとつになり、約束の包含性のもとに来ることによって救いを見いだすことになる。しかし、プライドは致命的である」モティア、164頁
[iv] 地図2099.)Isaiah15»Isa15mapMoabDWELLINGintheWordachapteradaytoshapeourlivesforGod
[v] 「一五章と一六章の宣告は、紀元前七一五年から七一一年までの頃に、ユダのヒゼキャ王の時代になされました。預言は、アッシリヤのアッシュルバニパルによって紀元前六三九年と六三七年の間に東ヨルダンのアンモン(アモン)、モアブ、エドムを攻撃した時に成就しました。モアブは死海の東にあった小国です。」油井、129頁
[vi] 5〜9節は、主が苦悶しておられることの長い目録のようになっている。モティア、165頁
[vii] 以下、「わたしはさらに、ディモンにわざわいをもたらす。モアブの逃れた者、その土地に残った者に、一頭の獅子を。」
[viii] 原語は、なぜならを原意とするכִּיキー。7節の「なぜなら」はכֵּןケーン。
[ix] 叫ぶזָעַק、叫び声קוֹל(4)が、主の心が叫ぶ(5)に。
14:31 門よ、泣き叫べ。町よ、叫べ。ペリシテの全土は震えおののけ。北から煙が上がり、その編隊から落伍する者がいないからだ。
15:4 ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声がヤハツまで聞こえる。それゆえ、モアブの武装した者たちはわめく。そのたましいはわななく。
15:5 わたしの心はモアブのために叫ぶ。逃げ延びる者たちはツォアルまで、エグラテ・シェリシヤまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムへの道で破滅の叫びをあげる。
26:17 子を産む時が近づいた妊婦が産みの苦しみで、もだえ叫ぶように、主よ、私たちは御前でそのようでした。
57:13 あなたが叫ぶとき、あなたが集めたものどもに、あなたを救わせよ。風が、それらをみな運び去り、もやがそれらを連れ去ってしまう。しかし、わたしに身を寄せる者は、地を受け継ぎ、わたしの聖なる山を所有することができる。
[x] しかし、だからこそ、イザヤ書のこの預言が、いつを指しているのか、またいつ書かれたのか、が問題となってきました。「この困難さに加え、エレミヤ書48章には特定の部分が重複しているものの、順序と構成が異なるという事実から、多くの学者がこれらの章について非常に複雑な文学史を想定するに至っている。13しかし、カイザーが示したように、学者間での見解の一致は事実上存在しない。例えば、ヒッツィヒは最初の構想と形式をヨナに帰したのに対し、ドゥームはそれらを紀元前2世紀の編集者に帰した。少なくとも、エレミヤ書とイザヤ書の記述の類似性、そしてそれらがイザヤ書で確かに再利用されているという事実は、モアブを詩的に扱う標準的な手法が「共通の領域」に入り、両預言者によって利用された可能性を示唆している。」 オズワルト
[xii] 「「わたしの心はモアブのために叫ぶ」(五)。 預言者イザヤがモアブの滅亡について預言したころ、モアブは人口も多く肥沃な地でした。滅びうせてしまうことなどあろうか、と思われていました。 しかし、モアブは今日なお荒れ塚と化し、その廃墟には岩を深く切り裂いた井戸が口を開け、崩れた円柱がむなしく立つばかりです。かつてモアブ人が一つの文明をもって笑いさんざめいていた形跡は、ただそれらのものによってしか知られないのです。このモアブに対する預言は、他の預言と同じく完全に成就したのでした。 しかし、いたずらに預言の成就をたしかめるだけではなりません。預言者は、ただいいたずらに滅亡の力を示そうとして、かく叫んだのではありません。不敬虔な者たちが、真の神に立ち返るように、神はいまし、神は事実さばきたもうことを銘記せしめるためだったのです。神なんぞいるものか、神は地上のことに干渉されようか、とうそぶく心は、このような事実によって恐れおののき、あらためて十字架にすがるのです。」、小畑進、『きょうの力』、456頁。
[xiii] エゼキエル書18・23(わたしは悪しき者の死を喜ぶだろうか──神である主のことば──。彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。)、33・11(彼らにこう言え。『わたしは生きている──神である主のことば──。わたしは決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。立ち返れ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ、なぜ、あなたがたは死のうとするのか。』)
[xiv] Ⅰテモテ2・4。また、ペテロの手紙第二3・9(主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなたがたに対して忍耐しておられるのです。だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。)
[xv] マタイの福音書27・46(三時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」これは、「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味である。)、27・50(しかし、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。)、マルコの福音書15・34(そして三時に、イエスは大声で叫ばれた。「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。」訳すと「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味である。)、ルカの福音書8・54(しかし、イエスは少女の手を取って叫ばれた。「子よ、起きなさい。」)、23・46(イエスは大声で叫ばれた。「父よ、わたしの霊をあなたの御手にゆだねます。」こう言って、息を引き取られた。)、ヨハネの福音書11・43(そう言ってから、イエスは大声で叫ばれた。「ラザロよ、出て来なさい。」)、ガラテヤ人への手紙4・6(そして、あなたがたが子であるので、神は「アバ、父よ」と叫ぶ御子の御霊を、私たちの心に遣わされました。)、ヘブル人への手紙5・7(キリストは、肉体をもって生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙をもって祈りと願いをささげ、その敬虔のゆえに聞き入れられました。)