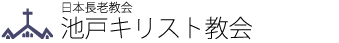2025/9/21 イザヤ書21章6~12節「朝は来る、また夜も来る」
イザヤ書の21章は「海の荒野についての宣告」と始まります。この「~についての宣告」という書き出しは、13章から繰り返されてきました。今日の9節の後半にも
倒れた。バビロンは倒れた。その国の神々の、すべての刻んだ像も地に打ち砕かれた」と。
とありますが、バビロンと称される、神に逆らう力、神を恐れず、自分たちの塔を高く築こうとする権力が倒されることが13章から語られてきました。今はそんな話は信じられない、大帝国、軍事大国も、やがては滅びる、悪を裁かれることが力強く予告されてきました。その合間にも、神である主の憐み深さ、裁きの先の回復・再出発が語られてはいました。ですが大枠は厳しいさばきでした。それがこの21章からは趣が変わります。もっと複雑で、人の心に焦点が当てられます。意味が分かりにくい短い幻が続きます。専門家たちも意見が分かれ、ひとつの解釈に断定できないと言う言葉が続くのです[i]。でもだからこそ、そこに見えるのは、預言者や当時の人々、そして読者である私たちの心の動きも、そこに映し出されて、浮き彫りにされます。
最初、1節にある「海の荒野」。これ自体、不思議な言葉です[ii]。海の、荒野。何でしょう? これは9節で、バビロンの終わりが宣言されるのに続いていく、主の裁きを受けた町が、廃墟になっているのを指しているのでしょう[iii]。2節でイザヤは
「厳しい幻が私に示された。」
と言います。イザヤは自分に示された、厳しい幻、高ぶった国を襲う最後を語っています。2節最後に
「すべての嘆きを私は終わらせる。」
と言うのは、バビロンの悪が様々な嘆きを引き起こしてきたからです。しかし同時に
3それゆえ、戦慄が私の腰に満ち、子を産む時のような苦しみが私をとらえる。私は心乱れて、聞くことができない。恐ろしさのあまり、見ることができない。
とも続けるのです。イザヤは決して、バビロンへの裁きを平然と受け止めてはいません。勝ち誇るような言葉もなく、むしろ
4私の心は迷い、戦慄が私を襲った。私が恋い慕ったたそがれも、私をおびえさせるものとなった。
とショックを隠さないのです。
神に逆らい、人に嘆きを強いる悪が裁かれる時にも、イザヤは万々歳とは言えない、むしろ、その裁きにも伴って起きる出来事に、深く心が揺さぶられると言う。現代の映画や政治でも、問題を解決するには、簡単だ――悪の親分をやっつけたらいい、ミサイルを撃ち込めばいい、なんて暴論がまことしやかに描かれます。実際は、そんな簡単なわけではないのに…。イザヤはその合間に立って、裁きが引き起こす苦しみに、動揺を隠しません。当の当事者は、
5彼らは食卓を整え、座席を並べて、食べたり飲んだりしている。
と、気楽なのですが。
戦闘の準備も本気なのかどうか、という彼らの無頓着さに対して、主は命じます。
6主は私にこう言われた。「さあ、見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。7戦車や二列に並んだ騎兵、ろばに乗る者やらくだに乗る者を見たなら、よく注意を払わせよ。」
するとすぐに見張りの
「その人は、獅子のように叫んだ」
と続くのが、
戦車や兵士、二列に並んだ騎兵が…互いに言っています。「倒れた、バビロンは倒れた。…」
という知らせ、となるのです。
そんな終わりが近づくとは夢にも思わずに食べたり飲んだりしていたわけですが、この「見張り」のモチーフが11節にも続くのです。
11ドマについての宣告。セイルから私に叫ぶ者がある。「夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りよ、今は夜の何時か。」
この「セイル」はイスラエルの南東のエドムの地名ですが、「ドマ」がどこの事なのか、アラビアの地名か、エドムのことか、諸説あるのです。いずれにせよ「夜」とは禍や混沌を指していて、「今は夜の何時か」とは「後どれ位で今の闇の時代は終わるのか」という質問なのでしょう。でも夜回りはそれにすげなく応えます。
12夜回りは言った。「朝は来る。また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ。もう一度、来るがよい。」
見張りは朝まで何時間あるか、には答えないのです。朝は来る、そしてまた夜も来る。ひと時、大変な時期が過ぎても、また夜の闇がやって来る。しかし、セイルからの叫びは、夜回りや見張りに、残り時間を聞くだけで、主に立ち返るようにとの言葉や、神の裁きの現実から目を背けての質問です。こんな質問には、夜回りは答えるより、諭す言葉を返すだけです。
尋ねたければ尋ねよ
と突き放し、
もう一度、来るがよい
と言われて、また来たとしても、同じやり取りを繰り返すだけでしょう。
神である主は、この世界を裁いて、バビロンを倒す、とここまで繰り返してきました。その言葉にようやく耳を傾けるようになったとしても、なお「それはいつまでなのか。どうしたら自分だけでもその禍をやり過ごせるだろうか」、そんな自分本位の発想しか思いつかない…。このセイルへの夜回りの言葉はとても謎めいていますが、その意味を探る私たちの関心自体が、どうでしょう。自分の罪を、どこか他人事のように、まだ何とかごまかし通せるかのように思いながらの、的外れな質問ではないか、と省みたいのです。もう一つ13節からは「アラビアについての宣告」です。デダンもテマも、イスラエルの北東に広く広がるアラビアの地名です。バビロンが倒されたなら、アラビアに逃げて来る人々も多いでしょう。その人々について
14…渇いている者を迎えて水をやれ。逃れて来た者にパンを与えよ。15彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから逃れて来たのだから。
ここにも、逃れて来た者が悪を報いられたのだから、邪険に扱われていいとは言われません。激しい戦火を逃れて来たのだから、水をやれ、パンを与えよ――これが主の言葉です。
最後16~17節に「ケダル」が出て来ます。アラビアの砂漠の一体に住む人々で、アラビアの他の住民にとってもケダル人は野蛮で脅威だったのでしょうか。そのケダル人の栄光は、間もなく解雇されて終わりを迎え、勇士たちも激減します。最後に
「まことに、イスラエルの神、主が告げられる。」
と力強く結ばれるように、バビロンだけでなく、アラビアの蛮族ケダル人も脅威でなくなることは、周辺の国々にとって、深い慰め、安心をもたらしたのでしょう。
しかし、主の言葉は、単純な勧善懲悪の正義ではありません。逃れて来た者に水やパンを与えて、迎えることを勧めます。もし、彼らが、逃れて来た人に対して冷酷であったなら、彼らもまたケダル人やバビロンと同じになったでしょう。勿論、裁かれないために親切にしておく、というのとも違いますが、主が世界を裁いてバビロンもケダル人の支配も終わらせた後に始めようとしているのは、渇いている者を迎え、逃げて来た者に飲み食いさせるような、そういう神の国です[iv]。厳しい幻がイザヤ書には続きます。しかしそうしたものを読んだら読んだで、その裁きを逃れられることだけを「救い」と考えるのが人間です。自分たちさえ禍を逃れられたらいい。何とかして苦難を早くやり過ごせたらいい――そういう卑しい身勝手さ、自己中心さそのものを変えてくださるのが、神である主です。イザヤ書でも不可解な部分の多いこの21章に、厳しい幻に苦しむイザヤと、「今は夜の何時か」と問われても答えない夜回り、そして、逃げて来た者を迎えよ、という宣告――どれも意外な三つの言葉が心に刻まれるのです。
この後歌う讃美歌218番は、今日の11、12節のやり取りをモデルに「夜を守る友よ」と尋ね、夜回りが答えていく、という掛け合いの歌詞です[v]。この讃美歌では「伝道」の項目に入れられていますが、元々は待降節アドベントのキャロルです[vi]。そこではハッキリと、自分たちが道に悩み、消えない望みをかけるお方を待ちわびていることが、3節までかけて丁寧に歌われています。漫然と「早く朝が来ないかな」と問うて、出直すよう言われるのとは違います。私たちは主イエスを待ち望んでいるのです。私たちを嘆きと滅びから救うために、人となって来られ、十字架にかかり、復活された主がもう一度来られるのを待ち望んでいるのです。そして、主の来られるのを迎えるに相応しいのは、いつ主が来られるかを知ることではありません。主は、いつ主が来られるとしても、主のしもべとして生きることを与えてくださったのです。
「聖なる主よ。あなたのパンと水で養ってください。世界を裁き新しくする主の壮大な幻を語りつつ、私の心のふとした思いや小さな奉仕を浮かび上がらせる御言葉に驚きます。向けるべき所に目を向けてさせるご配慮に感謝します。いつまで…どうして…そんな思いが来ては去り、去っては来る、しかし確実に永遠の朝に近づいていく地上の旅を恵みによって支えてください」
[i] 「13-22章の「序論」、本書一四四―一四六頁を見よ。最初の宣告のシリーズ(13-20章)は、軽率な楽天主義が特徴であった。この世の超大国も、主のみことばに従い、主のみことばは栄光ある約束に満ちていた。この第二のシリーズは、全く違っている。それぞれの宣告が主題を平明にしているにもかかわらず、宣告は謎に満ちた表題を持ち、神秘的な様相を呈し、全体としては前兆にさえなっている。事実、その当時は不吉な運命と暗闇が広がっていた。」モティア、190ページ
[ii] 「「海の荒野」は栄華を窮めたバビロンが滅亡する結果の状態を示す言葉です。第二次世界大戦後の東京は「焼け野原」「焼け跡」となったというのと同じです。イザヤ書一四章二三節で、バビロンが「針ねずみの領地、水のある沢」と言われています。バビロンは地形的に大きな川に浸された広い平野と言えます。そこに激しい嵐が吹き荒れて来るとイザヤは言います。「ネゲブに吹きまくるつむじ風のように。」ネゲブは、パレスチナの南、あるいは南東の地域です。この地域の嵐は激しいです。つむじ風が吹き荒れた後には廃墟が残されます。そのような嵐が押し寄せて来ると言うのです。/これは単なる比喩ではありません。恐ろしい軍隊がネゲブの野から来るように荒野から来ます。メディヤとペルシャの軍勢です。それは二節のエラムとメディヤと言っても良いです。その軍勢がバビロンを攻撃するために来るという予告預言です。これは紀元前五三九年のペルシャ王クロスによるバビロン陥落の予告預言です。前五三九年の夏、ペルシャ軍はバビロン攻撃の準備を完了し、決定的な戦いがチグリス川のオピスで行われてバビロン軍は敗退し、バビロンは陥落しました。」油井、163〜164ページ
[iii] 聖書の中では、海とは、のどかや「母なる海」というイメージではなく、死のイメージです。
[iv] 主ご自身がそういうお方です。イザヤ書55章:ああ、渇いている者はみな、水を求めて出て来るがよい。金のない者も。さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで、穀物を買え。代価を払わないで、ぶどう酒と乳を。なぜ、あなたがたは、食糧にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。わたしによく聞き従い、良いものを食べよ。そうすれば、あなたがたは脂肪で元気づく。
[v] https://www.umcdiscipleship.org/resources/history-of-hymns-watchman-tell-us-of-the-night
「ボウリングの政治的手腕は一部の人々から尊敬されていたに違いありません。1860年に引退した後も、彼はイタリア駐在の委員をはじめ、ヨーロッパやハワイの外交官として公務を続けました。「アメイジング・グレイス」を作曲した、元奴隷商人から英国国教会の司祭に転身したジョン・ニュートンを除けば、彼ほど多彩で国際的な生活を送っていた賛美歌作者はほとんどいません。サー・ジョンは、多忙な政治・外交のキャリアを歩みながらも、詩の翻訳、創作詩の作曲、そして政治・宗教をテーマにしたエッセイの執筆など、活発な活動を続けていました。しかし、アルバート・ベイリーは、「現在まで残る賛美歌はすべて、彼が30歳前後の頃に書かれたもので、詩への関心が最も高まっていた時期であり、若さゆえの理想主義が彼を虐げられた人々や恵まれない人々の擁護者にしていた」と述べています。賛美歌の話に戻りますが、詩人はこの賛美歌が舞台となっている世界の地域を間違いなく意識していたでしょう。この詩は、ボーリングの『賛美歌』(1825年)に初版が出版されました。この詩の特徴は、完璧な対称性にあります。各節の最初の2行では、旅人が見張りに何を見たのか尋ねます。そして、最後の2行では見張りの返答が続きます。この詩はまた、賛美歌が徐々にクライマックスへと盛り上がっていく様子を示す優れた例でもあります。各節は、力強さと希望を増していきます。第3節では、
番人よ、夜について語れ。星はさらに高く昇る。
旅人よ、その道筋は祝福と光、平和と真実を予兆する。
しかし、第4節では、平和と真実の光が輝き、地球を覆います。平和の光です。
見張り人よ、その光線だけが、彼らを生んだ場所を金色に染めるだろうか?
旅人よ、時代はそれ自身のものだ。見よ、それは全地に輝き渡る。
第 6 節の最後の対話では、平和の君の到来という降臨のテーマが明らかにされています (イザヤ 9:6)。
見張り人よ、放浪をやめ、静かな家に帰れ!
旅人よ、見よ、平和の君、見よ、神の子が来た!
合同メソジスト教会賛美歌の編集者カールトン・R・ヤングは、この賛美歌がアメリカ合衆国で初めて歌われたのは1830年1月、ボストンのパーク・ストリート教会であったと記しています。ルーファス・アンダーソン牧師の説教が終わると、著名な作曲家、音楽教育者、教会音楽家、そして合唱指揮者でもあったローウェル・メイソン(1792-1872)が「作曲家による独唱、合唱、会衆、そして鍵盤楽器のための楽曲を合唱団に歌わせました。この賛美歌は『ウォッチマン! 夜を告げよ:宣教師の賛美歌かクリスマスの賛美歌か』という楽譜として出版され、ボストン・ヘンデル・ハイドン協会教会音楽集第9版(ボストン、1830年)に収録されました。」
ヤング博士は、この賛美歌は「神の王国は地上に確立できるという、ボーリングの揺るぎないユニテリアンのポストミレニアル主義的な楽観主義」を反映していると指摘しています。確かに、ボーリングの旅人としての幅広い経験と、多くの文化、言語、そして世界情勢への理解は、当時の人々には到底及ばない視点をもたらしました。実際、この賛美歌は部分的に自伝的な要素を帯びているのかもしれません。平和を求めて世界を旅し続けたボーリングの姿が描かれているのです。」 Google翻訳による
[vi] 讃美歌218番 Watchman, tell us of the night. John Bowring, 1825:
- 「夜を守もる友よ、闇夜を照らす道の光はまだ昇らずや」
「旅ゆく友よ、かの山の端はの栄え輝く星かげ見ずや」 - 「栄え輝くその星影に消えぬ望みは懸かりてありや」
「尽きぬ恵みも朽ちぬ真理まことも、いよよ分明さやかに燦きらめくを見よ」
- 「露つゆにしめりて夜を守る業の務めもはつる朝は近きか」
「道に悩みて旅ゆく友の待ちにし君も今し来ませり」