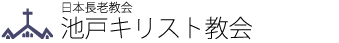2025/8/31 イザヤ書18章「刈り入れ時の暑さの中の雨雲のような神」
4主が私にこう言われたからだ。「わたしは静まり、わたしのところから眺める。照りつける日差しの暑さのように、刈り入れ時の暑さの中の雨雲のように。」
なんとも不思議な言葉です。神である主が言われるのです。静かに、じっと見ておられる。「眺める」というとただ腕組みをして他人事のように眺めている印象も受けるかもしれません。「照りつける日差しの暑さのように」というのも残暑厳しい中で、しんどいな~と思いたくなる言葉です。続いて「刈り入れ時の暑さの中の雨雲のように」とあると、暑さと暑さの中の雨雲とでは全然違うことのように思う。けれども確かに、暑さも雨雲も、照りつける日差しの中で働く者にとってはどうすることも出来ない空の上で、ゆっくりと動いていて、暑さは過ぎ去ったり、にわか雨をもたらしたりする。私たちは暑さも雨も操作できない小さなものです。そしてその中に生かされて、種をまき、作物を育て、収穫して、食べて生かされている私たちです。
前回の17章12~13節には「ざわめき…どよめき」が何度も繰り返されました。イザヤ書の時代、国々が騒めき、右往左往し慌あわただしくなっていた時代です。その世界の騒ざわめきと対照的に、主が「わたしは静まり…」と仰る。何か神に圧倒的な解決を期待する人々が大勢だったでしょう[i]。しかし神はむしろ、静まり、時を待ち、信頼することを語るのです。神は奇跡や力の中にではなく、細い声を通してご自身を現される、という聖書の神観がここにもあります。そして、この言葉こそ、全世界に伝えよと言われている言葉です。
3世界のすべての住民よ。地に住むすべての者よ。山々に旗が揚がるときは見よ。角笛が吹き鳴らされるときには聞け。
この18章の解釈には諸説あります。1節の「クシュ」は欄外に「すなわち「エチオピア」」とありますので、これをエチオピアへの言葉とも読めますが[ii]、むしろ
「クシュの幾多の川のかなたにあり」
とあります。クシュエチオピアはイスラエルから見て南の地の果てでした。ですからクシュの彼方にある「羽コオロギの国」とは、実在したどこかというよりも仮想上の国で、「羽コオロギ」というのも、船の帆を「羽」に見立てて、海路、船で使いを送る様子を描いているようです[iii]。同様に、2節の
背が高く肌の滑らかな国民…あちこちで恐れられている民…その国土を多くの川が分けている、力強い、踏みにじる国
も、どこか特定の国を指しているのではなく、仮想上の大国なのでしょう。南の果ての向こうにある国から、強い巨人たちが住む国に、海路、使者を遣わせという大きな絵を描きながら、実質は
3世界のすべての住民よ。地に住むすべての者よ。山々に旗が揚がるときは見よ。角笛が吹き鳴らされるときには聞け。
と全世界のすべての者が、聴くべき言葉として4節の主の言葉が肝心なのです。
4主が私にこう言われたからだ。「わたしは静まり、わたしのところから眺める。照りつける日差しの暑さのように、刈り入れ時の暑さの中の雨雲のように。」
そしてこの譬えは、5節6節に続きます。
5刈り入れの前、花が終わって、花房が熟したぶどうになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取って除き去るからだ。6それらはみなともに、山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられる。猛禽はその上で夏を過ごし、野獣はみな、そのうえで冬を過ごす。」
刈り入れで、余計な枝を切り、蔓を除いて投げ捨てるように、主は時が来れば裁きを果たす。人間のごちゃごちゃとした問題は整理されるのです[iv]。そればかりではありません。
7そのとき、背が高く肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、その国土を多くの川が分けている、力強い踏みにじる国民から、万軍の主の名のある場所、シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれて来る。
2節で「使者」が遣わされた民、巨人たちの恐ろしい国の国民から、エルサレムに贈り物が運ばれて来る、というのです。「あちこちで恐れられている民」が、万軍の主のためにと贈り物を携えて来る、この大逆転です。そんな国に、主の言葉を船で届けたとしても、聞いてもらえるだろうか、笑われるだけではないか、いや踏み躙られてしまいそうです。それが、その一つ一つの描写を繰り返した上で、「万軍の主のために贈り物が運ばれて来る。」という将来! 乱暴な巨人たちも、万軍の主への贈り物を携えてやって来るようになる。まして、世界のどの国々も、その時には、自分たちの造った偶像や神々を捨てて、主なる神こそがまことの神だと認めて、礼拝にやって来て捧げものをするようになる。そういう大団円です[v]。
イザヤ書最後の66章にも、こう言われます。
19わたしは彼らの中にしるしを置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に遣わす。(中略)わたしのうわさを聞いたことも、わたしの栄光を見たこともない遠い島々に。彼らはわたしの栄光を諸国の民に告げ知らせる。20彼らはすべての国々から、あなたがたの同胞をみな主への贈り物として、馬、車、輿こし、らば、らくだに乗せて、わたしの聖なる山エルサレムに連れて来る――主は言われる――。(略)
また、聖書の一番最後のヨハネの黙示録の最後でも同じです。最後には、悪やサタンが滅ぼされた後、「新しい天と新しい地」について、国々の王たちが礼拝に来るのです。
21・24諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えて来る。
同26こうして人々は、諸国の民の栄光と誉れを都に携えて来る。
主を知らない人々や王たちも、自分たちの栄光を贈り物として主の元に来て、礼拝を捧げる。そういう将来は聖書で繰り返されています。それは、主が神の全能の力によって世界をねじ伏せて成し遂げることではありません。権力争いの勝者になられるというよりも、権力争いそのものが終わり、引っ繰り返るのが7節で描かれる、巨人が贈り物を携えて来る光景です。
だからこそ主は「わたしは静まり、わたしのところから眺める。日差しの暑さのように、暑さの中の雨雲のように」と言われます。主は沈黙しています。主への礼拝もおざなりで、シオンの山など弱小でしかなく、イスラエルなんて南北に分裂した小国は、踏み潰されるだけだ、と思われていたのです[vi]。しかし、そのような笑い声が響くような中で主は「わたしは静まる」と仰います。主の静けさは、私たちにも立ち止まって静まり、信頼することを招く静けさです。
勿論、主はいつまでも黙ったままではいません。この言葉はイザヤ書で7回繰り返され[vii]。最後の62章1節では主が「わたしは沈黙しない」と立ち上がってくださいます。またこの時のイザヤに4節を言われたこと、この18章の預言があること、イザヤ書という長い預言書があることも、神が沈黙しているわけではない証拠です。神は無口でも、無関心でもない方です。この言葉は他では「落ち着く・信頼する」と結びつけられます。
30・15立ち返って落ち着いていれば、あなたがたは救われ、静かにして信頼すれば、あなたがたは力を得る。
ですから、主が静まるのは、何も言わないとか、言いたいことがいろいろあるけれど口を閉ざしている、といった表面的な「静か」というより、深い信頼、堂々とした落ち着きがある、という大いなる沈黙です。神は人の右往左往に対して厳しく語り、罪に対して断固たる回心を呼びかけます。神らしからぬ激しい感情を露わにさえします。しかし、その奥には深い信頼があります。確かな将来を握っておられます。そして人間にも、そのような静まりを――ただ黙るだけでなく深い信頼を――希望を抱くよう呼びかけます。勿論、その深い信頼の上で、現実的な対応をする(「正しく恐れる」)ことをするのです[viii]。
主イエスの御生涯にも、この静けさはあちこちに見られます。弟子や群衆の期待は度々肩透かしを食らいました。すぐに解決できる力がありながら、黙ってともに歩き、待たせたり、わざわざ手を触れたりした。そのイエスは、人間が思い描く英雄や神々とは大違いの救い主です。主は静まっている時、その沈黙の中で私たちに目を注ぎ、暑さや雨を与えてくださっています。巨人たちの国をひれ伏させることも出来る方、してくださる方が[ix]、それ以上の尊いことを私たちのうちに育ててくださっています。
「万軍の主よ[x]。あなたは大いなることをなさり、私たちに信頼と希望を与えてられます。あなたの沈黙は、私たちに辛く厳しいことも多いですから、どうぞ主よ、私たちを憐みお支えください。今週の歩みをも主の大いなるご計画の一部として導き、知恵と沈黙を与えてください」
[i] 「4 イザヤは今、自分に与えられた御言葉を分かち合います。旗が掲げられ、ラッパが鳴らされる時、神はどのような力強い御業を行われるのでしょうか。その答えは、神が途方もない圧倒的な御業をなさることを期待する人々にとっては、失望となるでしょう。エリヤの「静かな細い声」(列王記上19:12)のように、主は、御業は静かで控えめなものでありながら、それでもなお完全なものとなると断言されます。神は、自分のために神に命令することを期待する人々のために存在するのではありません。神は、ご自身の愛と、この世における救いの目的のために存在されます。神はこれらの人々のために、そしてご自身の方法で行動されます。しかし、神は必ず行動されます。
ある観点から見ると、4節は意外な一節です。機敏な使者が召集され、強大な民のもとに遣わされます。世界は備えをするよう求められます。緊張が高まります。どんな大災害が解き放たれるのでしょうか。真実は、主権者の静かなまなざしこそ、世界の最強の軍隊よりも重要なのです(詩篇 2:1-4、33:13-17、80:14、哀歌 5:1、イザヤ 63:15)。主にとって、何もせず(「静かに座して」)、ただ傍観していることは、世界のあらゆる官邸でのあらゆる審議よりも重要なのです。しかし、午後半ばには耐えられないほどに高まる静かな暑さや、海岸から谷間を漂う霧のカーテンのように、神はご自身の存在を知らしめ、感じさせてくださるのです。 16 ベツレヘムでの誕生のときと同様に、華やかさやファンファーレはありませんが、世界は永遠に変わります。」Oswalt、Google 翻訳による。
[ii] 19章は「エジプトについての宣告」とあり、ちょうどイザヤの時代に、エチオピアがエジプトを征服したということもあって、18章から20章まではエチオピアとエジプトについての宣告であるとする説もあり。モティアなど。
[iii] 「羽コオロギ」とはここにしか出て来ない名詞で、意味は不明です。エジプトに多かったツェツェバエとする説や、コオロギの黒さとエチオピア人の肌の色とを重ねている説など、諸説あり。
[iv] 「わたしは静まって、わたしの所からながめよう。」(四)。 台風の目アッシリヤは、クシュにも進攻を開始します――クシュ人は「背の高い、はだのなめらかな国民」といわれています。 アッシリヤ軍は敵なき野を行くがごとく侵入します。神がその進軍の速度をゆるめることも、止めることもなさらないのは、どうしたことでしょう。このままではアッシリヤ軍の思うままになってしまうではありませんか。神はこれを知っておられるのか、見ておられるのか。 もちろん、神は知っておられました。しかし、「わたしは静まって、わたしの所からながめよう」と語られるだけなのです。なぜ? なぜ? 一刻を争うというのに……。しかし、いよいよという時、「刈り入れ前に花が咲き、花が、熟したぶどうになるとき」、時満ちたとき、「人はその枝をかまで切り、そのつるを取り去り、切り除き」一挙に倒したもうのです! この呼吸を忘れないように。時として、神は沈黙しておられます。神の御手は片鱗だにあらわれません。しかし、沈黙は同委ではないのです。必ずや時いたれば一挙に裁断されるのです。」小畑進、『きょうの力』、458頁。
[v] それは決して、力づくで、独善的で、身勝手な終末理解とは違うものでなければなりません。この終末は、新約において主イエスが既に果たされて、すべての国々の人々が教会に加えられることによって始まっている、宣教的なものです。
[vi] イザヤ書36章、37章など参照。
[vii] שָׁקַט シャーカト イザヤ書に7回:7・4(彼に言え。「気を確かに持ち、落ち着いていなさい。)、14・7(全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げる。)、18・4(本節)、30・15(イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。「立ち返って落ち着いていれば、あなたがたは救われ、静かにして信頼すれば、あなたがたは力を得る。」しかし、あなたがたはこれを望まなかった。)、32・17(義が平和をつくり出し、義がとこしえの平穏と安心をもたらすとき、)、57・20(しかし、悪しき者は荒れ狂う海のようだ。まことに、それは鎮まることができず、その水は海藻と泥を吐き出す。)、62・1(シオンのために、わたしは黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その義が明るく光を放ち、その救いが、たいまつのように燃えるまでは。)
[viii] 私たちが落ち着いて静まるとは、決して何もしなくて待つとか、逃げなくても大丈夫とかではありません。必要以上に慌てふためくのも、必要なのに避難しないのも、どちらの極端も要注意です。預言者たちも、主を忘れた画策に走ることと、神殿や聖書を過信した楽観的態度、両方を咎めました。私たちの生涯は通常、そのどちらかではない、グレーゾーンです。イザヤの時代、激動期でさえ、まず落ち着いて信頼することが大事だったのです。
[ix] 「主はすぐに行動されずに静まって、刈入れまでぶどうが熟すのを待つ方である。アッシリヤの侵略活動が阻止されないで進展しているのも、さばきの時期が熟するまで主が「静まって……ながめ」ているからである。いつの時代でも、世界の諸国家のあらゆる動きを、主は静まって御自分のところから注目しておられ、刈入れの時期の完熟を見守っておられるという主のおことばは、多くの困難や疑問の中で信仰者を平安にすると共に、静まって見守っておられる主に全く信頼することの重要さをも教える。主の民を苦しめる活動が絶頂に達する前に、主は必ず行動を起されるが、それを待つ忍耐と信仰が我々にもっと必要に思われる。」 鈴木昌、134ページ
[x] 「ここでの主の名は重要な神学的概念である。その名は人格や評判と同義である。なぜ地上の諸国民がエルサレムに集まるのだろうか。それは、その神の人格による。すなわち、義なる者でありながら愛に満ち、全能であるにもかかわらず優しく、裁き主でありながら解放者でもある、などである。私たちは皆、まことに神のような者はいないので、神の場所に惹かれるのである」 Oswaltと7節の解説。Google 翻訳による。また「「万軍」が複数であるのは、ご自身において主がすべての可能性と力を持っていることを指し示している。結果として主は、ご自身のご性質に従って、どのような方法であっても主権的に行動される。その同じ主が(2節)さばくのみならず、また抑制的保持において行動される(9節)。主の愛のゆえに、私たちに終わりが告げられることはない。主のあわれみは尽きないからである(哀歌3・22)。そのようにイザヤはこの部分を締めくくっている。」(モティア、52〜53ページ)