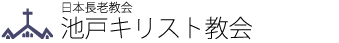2025/8/24 イザヤ書17章「あなたの造り主に目を留めよ」
今もイスラエルの北東に広がるシリアの首都はダマスカスです。この町は「世界一古くから人が住み続けている町」と言われるそうで[i]、当時はアラムの首都、交通の要衝として栄えていた大きな都でした[ii]。そのダマスコが今日のイザヤ書17章で名指されます。13章から23章まで、周辺諸国への言葉が続きますが、現在もニュースで耳にする町、「世界一古くから人が住み続けている町」にも、神はその運命を決する言葉を語られる事実にハッと息を吞むのです。
1…見よ。ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。2アロエルの町々は捨てられて 家畜のものとなり、群れはそこに伏して、それを脅かす者はいなくなる。」
復習になりますが、イザヤの時代、イスラエルは南北に分裂して、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分かれていました。その北にあったのがシリア王国で、更にその北のアッシリア帝国が急激に勢力をつけて南下してくる脅威となっています。そのため、北イスラエル王国とシリアとが、反アッシリア同盟を組んで、南のユダにも参加を求めた。しかしユダは、アッシリアとの同盟を謀り、新アッシリア政策を選んだので、シリアとイスラエル連合は、まずユダ王国を攻撃しようとした、という背景がありました。それは7章に詳しく書かれています。ともあれそういうわけで、ダマスコはイザヤやユダ、エルサレムの住民にとっては今にも攻め入ろうとしてきた、憎らしい敵、しかし恐ろしい大国です。そのアラムに対して、神は「都でなくなり、瓦礫の山になる…捨てられて家畜の群れのものと…」と宣告をなさるのです。
3エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。…
エフライムとは北イスラエルのことです。彼らにとってダマスコは要塞のような頼みの綱でしたが、それは失われるし、ダマスコは王国そのものを失うのです。南ユダの人々にとっては、憎らしい敵国に対する神の宣言に、万歳を叫びたいような吉報だったでしょう。ダマスコという名前が出て来るのはこの最初だけですが、この17章は、要塞のようなダマスコも、いつまでも安泰ではない事実を思い起こさせます[iii]。
3…アラムの残った者はイスラエルの子らの栄光のようになる。――万軍の主のことば。
どういうことでしょうか。それを4節では「ヤコブの栄光」と言い換えて
4その日、ヤコブの栄光は衰え、その肥えた肉は痩せ細る。5刈り入れ人が立ち穂を集めて、その腕に穂を刈り入れるときのようになる。レファイムの谷で落穂を拾う時のように。6オリーブを打ち落とすときのように、取り残しの身が中に残される。こずえには二つ三つの熟れた実が、実りの多い枝には四つ五つが残される
と幾つもの寂しい限りの光景を描きます。アラムもですがイスラエルも主の前には道を踏み外していました。神を忘れて思い上がっていました。その栄光は、すっかり痩せ衰えるのです。「レファイムの谷」とはエルサレム南西の谷で、あのダビデとゴリアテが戦った谷です。その谷で取り残しの落穂を拾うような、侘しい限りになる。ヤコブの栄光、イスラエルの輝きや誇りが見る影もなくなる。そのようにアラムもなる、というのです。しかし、厳しい言葉の合間に、7節で思いもかけない恵みの言葉が埋め込まれます。
7その日、人は自分を造った方に目を留め、その目はイスラエルの聖なる方を見る。8自分の手で造った祭壇に目を留めず、自分の指で造った物、アシェラ像や香の台は見ない。
その日、人は自分を造った方に目を留める。自分の造り主に目を留める。「イスラエルの聖なる方」とはイザヤ書で何度も出て来る特徴的な神の呼び名です。聖なる神、罪を容認せず、人をきよく生まれ変わらせてくださる神を見る。今までは、自分の手で祭壇や偶像や、何かしら神々のように頼るものを造って来た人々が、その自分の造ったものでなく、自分を造った方に向きを変える、大きな変化が「その日」には起きるのです。
それは罪の結果の荒廃を留めるわけではありません。9節以下
その日、その堅固な町々は、森の中の見捨てられた場所、かつてイスラエル人によって見捨てられた山の頂のようになって、荒れ果てる。10あなたが救いの神を忘れ、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。…
と語り、再び農業の譬えで、不毛になる最後が語られます。こうした荒廃が避けられるわけではありません。しかし、そうした最後によって、神ならぬものを神とする、あるいは、自分の手で神々や確かな未来を作り出せるかのように思ってきた計画が全く消え失せた後に、人が自分を造った方に目を留めるという日が来る。そういうのです。
うがった見方をする学者は、この7~8節はこの箇所にあまりに馴染まないから、元々ここにはなかったに違いない、というようです[iv]。しかしそれならなぜ後からここにこの言葉を入れようなどとしたのか、その方が不自然で説得力がありません。ただそれ程にこの7~8節がここにあることは驚くべきこと、人間の常識では考えだせないこと、「イスラエルの聖なる方」だからこそ言い得る言葉に違いないのです。それは、ここだけではありません。これは13章から25章という大枠そのものです。また、その前にあった11章12章の喜ばしい歌で、すべての国々が新しい関係、和解に入れられると歌われました。ここ17章でもそうなのです。
最後12~14節は「ああ、多くの国々の民のざわめき」と始まって、諸国の人々がざわめき、どよめく大きな危機について語ります。恐らく、ダマスコも南北イスラエルも脅威に思っていたアッシリア帝国軍の南下です。しかし
13…しかしそれは、しかりつけると遠くへ逃げる
云々と、呆気なくその危機は去る。最後14節は
…これこそ、私たちから奪い取る者たちの取り分、私たちをかすめ奪う者たちが受ける割り当て。
と結びます。これは「私たち」が正しいから、善い所があるから、では100%ありません。ひとえに私たちを造った方、主が私たちの神でいてくださるからです。ひたすら、この神が聖なるあわれみの方だからです。
この神に私たちが立ち帰り、造り主であり聖なる神を仰ぎ見る――これが神に造られた人間の原点です。3節の「イスラエルの子らの栄光のようになる」は4~6節の荒廃だけでなく、7~8節も含めて読むことが提唱されています[v]。イスラエルの思い上がった意味での「栄光」は衰え、消え失せます。しかしそのことを経て、自分が造った神々や計画が水の泡だったと気づいて自分の造り主に目を留め、聖なる方に向くようになるなら、それこそ本当の栄えある生き方の始まりです。ルカ15章の「放蕩息子」が財産を使い果たして惨めなどん底生活になった時、「我に返って」父の元に帰ったのと重なります。イスラエルの栄光は、砕かれた後、本当に栄光ある神に目を留めることになる。そのように、というならダマスコ、アラムも惨めな最後を迎えて終わり、ではなく、その後に造り主に目を留める、聖なる方を見ることも含まれるでしょう。7節の「その日、人は」――イスラエル人だけでなく、アラム人も諸国の人々も私たちも――人種、民族、国籍に関係なく、あらゆる「人」は虚栄を失った後、主を仰ぐのです。
ダマスコの都はこの後、この言葉通りにアッシリアに攻め落とされますが、ずっとそのままではなく、やがて人が戻ります。聖書を読んでいて最も有名なのは、使徒の働き9章のサウル(後の使徒パウロ)の回心、「ダマスコ途上」の出来事でしょう。教会の迫害者であり熱心な宗教者であったサウロに、主イエス・キリストが出会ってくださいました。それはサウルの握り締めていた誇り、生まれや経歴、熱心さや正しさを「損」「ちりあくた」と言わせるほどの大転換でした[vi]。それはサウロにとって、神理解の大転換でした。神が神としての栄光の御座に高く留まる神ではなく、人間のため、御自身を与えて謙ってくださった。人となり、十字架にまで卑しめられることを厭わなかった。その惜しみない恵みこそ、主イエスを通して現された神の栄光です。そしてその栄光が、迫害者サウロも、砕かれた使徒パウロに変えました。ダマスコの名を、主の恵みを思わせる名に変えました。私たちもその栄光に与るのです[vii]。
「聖なる主よ。造り主なるあなたはすべてのものに勝り、一切を導かれる神です。国々も、迫害者もそして私たちも、あなたの前にひれ伏し、あなたに栄光を捧げます。私たちの自慢や頼みとするものが朽ちる時、どうぞ私たちの心を支え、善い知恵を与え、朽ちることのないあなたの栄光に、あなたの深い御心に信頼させてください。人の虚栄が廃れて、あなたを仰ぎ見て新しくされる、その恵みを、私たち一人一人にも、この世界の為政者たちにもお与えください」
[ii] 「ダマスカスは古代世界で最も戦略的な都市のひとつであった。なぜなら、メソポタミアとエジプトを結ぶ唯一の便利な陸路が通る天然の漏斗の入り口に位置していたからである。市の北にはヘルモン山がそびえ立ち、南には玄武岩の台地が連なっている。これらはともに隊商の移動の障害となった。その結果、ダマスカスは同規模の他の都市をはるかに凌駕する影響力を及ぼした。しかし、イザヤはダマスカスが都市から廃墟に変わると述べている。ペリシテとモアブに対する預言のころには、この預言は既に大部分実現していた。732年の壊滅的な包囲戦の末、シャルマネセルがダマスカスを征服したからである。どんな有力な勢力にも、それを荒廃させるさらに大きな勢力が常に存在する。唯一の希望は、すべての力の中で最も強大な力にある。」オズワルト
[iii] ダマスコ(シリア)への預言は、アモス1・3~5、エレミヤ49・23~27、ゼカリヤ9・1以下などにも。
[iv] 「事実上すべての現代注釈者は、7-8節は不適切であると主張している。それは、6節から9節への思考の流れを中断しているように見えるからだけでなく、この神学が捕囚後の種類のものであり、偶像崇拝に対する嫌悪が大きな勢いを増しているからでもある。(グレイはまた、「造り主」はホセア書では51:13と54:5にしか出てこないことから後世の概念であると主張している。しかし、この同じ議論は、これらの言及をこの言及に依存させることで逆転する可能性がある。特に造り主はホセア書8:14に登場しており、これは捕囚後の日付とは到底言えないからである。)4-6節について上で述べたように、思考の連鎖には、一見したところほど大きな断絶はないのかもしれない。神と和解するという概念は、来たるべき審判の幻に対する最も自然な反応なのかもしれない。」Oswalt
[vi] ピリピ人への手紙3・4~9参照。
[vii] 箴言14:31 弱い者を虐げる者は自分の造り主をそしり、貧しい者をあわれむ者は造り主を敬う。
17:5 貧しい者を嘲る者は自分の造り主をそしる。人の災難を喜ぶ者は罰を免れない。
22:2 富む者と貧しい者が出会う。どちらもみな、造られたのは主である。