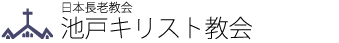2025/8/10 イザヤ書16章「その自慢話は正しくない」
キリスト教会が、イエスの教えの特徴の一つとして伝えているもの、そしてある程度定着しただろう言葉の一つに、「隣人愛」があるでしょう。隣人(聖書ではわざわざ「となりびと」と読ませています)を大切にする。ルカの福音書10章では「私の隣人とは誰ですか」と尋ねた人に対して、イエスが話した「良きサマリア人の譬え」も知られているでしょう。強盗に襲われて道端に倒れていた人を助けたのは、祭司や神殿の奉仕者ではなく、隣国でありながら敵対関係にあったサマリア人でした。イエスは、隣人とは誰か、ではなくて、対立をも乗り越えて近づく隣人愛へと、人間を招き寄せたのです。
今日のイザヤ書16章には、モアブの民への言葉が、15章から続いて語られています。モアブはイスラエルの隣国の筆頭に挙げられています。イザヤの時代は「サマリア人」という存在はまだなく、イエスの時代にはモアブの存在がなくなっていましたが、どちらも当時の人々にとっては、身近な隣国であり、身近だからこそ、確執があり、煩わしい存在でした。そのモアブに対して、神である主は、イスラエルに助けを求めよと言い、協力していくよう命じます。
1「おまえたちは、子羊をこの国の支配者に送れ。セラから荒野を経て、娘シオンの山に。…
セラはモアブの南の町ですから、北から攻めて来たアッシリア軍を逃れて、このセラに避難していたのでしょうか。そこから荒野を経て、シオンの山、つまりエルサレムのイスラエルに援助を求めて、子羊の贈り物を持っていけ、というのです。3~4節は誰に言われているのか、「あなた」とは誰のことなのか、不確かです[i]。いずれにせよ、「昼のさなかにも、あなたの影を夜のようにせよ。散らされた者をかくまい、逃れて来るものを渡すな。」とは、暑さの中を逃れて来る難民のために、十分な日陰を作ってあげて、保護をせよ、ということです。
4あなたの中にモアブの散らされた者を宿らせ、荒らす者から逃れる者の隠れ家となれ。
とモアブの民を安心して住まわせることを命じます。或いは欄外にあるように、モアブがイスラエルの民の隠れ家となることを命じている、という読みもあり、いずれにせよモアブとイスラエルが対立するのでなく、助けを求め合い、逃れ場を提供し合う関係が語られています。その根底にあるのは、主ご自身が、イスラエルだけでなく、隣国のモアブをも愛しむ事実です。
…虐げる者が死んで破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、5一つの王座が恵みによって堅く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、さばきをし、公正を求め、速やかに義を行う者。
主なる神は、虐げや破壊が消え失せて、恵みによって王を即位させる。武力や戦いによってではなく、嘘や策略によってでもなく、勿論コネや賄賂によってでもなく、人間が努力したことへの報いとか犠牲に対する褒美とかでさえありません。ただ、恵みによって――神ご自身からの一方的な好意・無償の贈り物として、です[ii]。そして、その王が正しく民を治め、イスラエルもモアブも治めてくださる。虐待や不正や暴力に怯えて泣いて逃げることも終わり、自分たちの中の差別や圧迫、いじめや不平等もない、この王による新しい時代が来るのです。
これは嬉しいことでしょうか。本来は嬉しいはずです。しかし、私たちは自分の内側に、正しからぬ考え、身勝手な差別、二重基準ダブルスタンダードがあります。だから、この王の統治には自分の心を探られて、頑固に「自分が王でいたい、間違いを認めたくない」自分を手放す痛みも覚悟して、謙ってこの王の恵みに自分を明け渡すことです。回心とは、聖なる降伏宣言の物語なのです。
ですから、ここでモアブの深刻な問題が言及されます。
6われわれはモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりと不遜さ、その自慢話は正しくない。
モアブの自惚れの体質が四つの言葉で言い換えて強調されます。具体的にどう高慢で、どんな自慢話をしていたのかは分かりません。国や権力者とか民族といったものが、愛国心とか自国第一主義に走ると、色々な自慢話をしだすものです。世界で第一位になるとか、金メダルを何個取ったとかが自分たちの優れた証拠のように思いたがる。日本にわざわざ来てくれた旅行客が「日本は素晴らしい」と褒めてくれたら、心から感謝しつつ自分たちも他の国に出かけて行って、相手をリスペクトする、そういう応答を忘れて、鼻の下を伸ばしているなら、恥ずかしいことです。
ここで挙げられるのは、7節最後の「干しぶどうの菓子」です。英語ではレーズンケーキを訳されて美味しそうです[iii]。8節から10節に「葡萄」が何度も出て来ますから、モアブの国は葡萄栽培に適して、豊かな葡萄畑が広がっていたのでしょう。その葡萄を干して作ったお菓子は、自慢の一品だったのでしょう。特産品、銘品だったのでしょうか。いや、実はその自慢も正しくない、独り善がりな宣伝だったかもしれませんし、その菓子を自慢して、国の守りとか内政に関してはレーズンケーキ並みにボロボロの隙だらけ、だったこともあり得るでしょう。
その遠くまで広がっていた葡萄畑も、侵略によって枯らされてしまう日が近づいていました。
8ヘシュボンの畑もシブマのぶどうの木も枯れた。国々の主たちがその房を打ったのだ。…
隙だらけのモアブが絶やされる日が描かれます。ここで繰り返されるのは主ご自身の悲しみです。
9それゆえ、わたしはヤゼルのために、シブマのぶどうの木のために泣く。ヘシュボンとエルアレよ。わたしはわたしの涙でおまえをぬらす。…
それは、10節最後にあるように「わたしが喜びの声を絶えさせたのだ。」という面もあります。しかしそれに続くのは
11それゆえ、わたしのはらわたはモアブのために、わたしの内臓はキル・ヘレスのために、竪琴のようにわななく。
という主の嘆きの絶叫です。腸、内臓がモアブのために震え、かき乱される。勿論、神には人間のように腸や体があるわけではありません。しかし、その大いなる神が私たち人間が辛い時、愛する人が苦しんだり正しくない道に直走ひたはしっているのを見て、胃が痛くなったりする、そんな姿を思い描くような卑近な表現を憚らず、人への思いを表すのです[iv]。前回15章5節で「わたしの心はモアブのために叫ぶ。」と聖書にもここにしかない言い方があると紹介しましたが、ここでは更に譬えを変えて、主はモアブのためにわななくのです。
イスラエル人にとっては隣の国、拮抗してきた民族、偶像崇拝をして、真の神を知らない人々です。そのモアブ人のために、主はこんなに心を痛めている。助けを求めよ、そして逃れ場を作ってもらえ、と言い、やがて恵みによって堅く立てられる王座がある、と告げました。この主の言葉を、体現したのは主イエス・キリストです。イエスが人々を見て「深くあわれんだ」という言葉は「はらわたが動かされる」という言葉です[v]。
またイエスは「良きサマリア人の譬え」を語りました。当時はモアブ人は消えて、サマリア人というリアルな隣人を持ち出しました。それは、憎しみや争いを捨てて、仲良くしなさい、という道徳を教えるためだったのでしょうか。いいえ、イエスご自身が、人間のため、腸がわななくと言われるほどの深い深い思いのお方だからです。主なる神に無関心で高慢ちきなモアブ人のためにも、深く慟哭される神だから、やがて主なる御子キリストは、人間のため、この世界に来られ、人としての生涯を歩みました。
恵みによって堅く立てられた王座とはイエスのことで、イエスはモアブ人のためにもユダヤ人のためにも、私たちのためにも、ご自分のいのちを献げてくださいました[vi]。主イエスが、私たちを恵みによって治めてくださるので、私たちは高慢から救われます。正しくない自慢話などしなくなるのは、自分の力ではなく、主イエスが私たちを治めてくださるからです。そして高慢を砕かれるだけでなく、隣人や隣国との関係も変えてくださいます。それはまず主イエスが、私の事もどの人の事も、こんなに深く大切に思っているかを知るからです。神が私たちの高慢を砕き、隣人や周りの国々との新しい関係へと私たちを導いてくださるよう、この8月に強く願います。それは人間の道徳ではなく、恵みの主の支配を待ち望むからです。
「平和の主、イエス・キリストの父なる神。人の高ぶりと疑いが、今なお戦争や暴力を産んでいます。あなたの善き支配により、私たちは傲慢と争いから救い出され、互いに日陰を差し出し逃れ場となる関係さえ、今、思い始めています。主よ、御心のままに私たちを新しくしてください。十字架に現された主の深い憐みにより、世界を新しく、あわれみで満たしてください」
[i] モアブの民がイスラエル人に言っているのか、主がイスラエル人に言っているのか、主がモアブの民に言っているのか。
[ii] 恵みhesedは神の民に対する変わりのない約束に基づいた不変性。時代が変わり、体験が変わり、信仰を揺るがすようなことがあっても変わることはない(モティア『イザヤ書』、168頁)
[iii] レーズンケーキは、レーズンを圧縮した小さな塊と思われるが、珍味とされ、様々な祝宴で用いられた(サムエル記下6:19、雅歌2:5、ホセア3:1)。
[iv] これに似た表現は、イザヤ書15~16章と並行して取り上げられるエレミヤ書48章にも出て来ます。「それゆえ、わたしの心は、モアブのために笛のように鳴る。わたしの心は、キル・ヘレスの人々のために笛のようになる。彼らの得た富も消え失せたからだ。(36節)」
[v] マタイの福音書9・36、ルカの福音書10・33、15・20など。
[vi] もしそのような神でないなら、「お前は高慢で、他の神を礼拝しているから、お前が滅びてもわたしは痛くも痒くもない。思い知るがいい」と言われるかもしれませんでした。そして誰一人、希望は持てません。