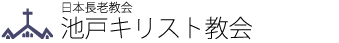2025/7/6 イザヤ書12章1〜6節「主は私の力、私の賛美」交読文8 詩27篇
イザヤ書12章は、短いですが、イザヤ書の最初の大きな区切りとなる大事な章です。前回11章では、切り倒された森の中から、切り株に生え出る若枝のように現れる方が、弱い者、貧しい者のための支配者となって、戦いを終わらせ、囚われていた人々を帰らせる将来が描かれました。すべての敵意や妬みが去る将来が語られました。その日に歌われるのが12章です。
1その日、あなたは言う。「主よ、感謝します。あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。」2見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れない。ヤハ、主は私の力、私のほめ歌。私のために救いとなられた。
将来、その日、本当に一人ひとりがこう言う。この言葉を心から、深く言う。11章で語られたのは、大きな状況が平和になり、良い支配になる、という図でした。続くこの12章はそれが「あなたは言う…私に…私を…私の…私は…私のために…」と、実存的に、というか、私に落とし込まれた一人ひとりの言葉となるのです。それも、心からの感謝と、主の怒りと慰めとを受け止める言葉になるのです。これは、口先の告白、言うように言われたから言う台詞ではありません。この前5章から10章までには、主は人に怒っていました。それは彼らが上部だけ、形式的なだけの礼拝をして、実際の生活では主を信頼せず、不正や残酷な権力との結託をしていたからです。主の声に心から聴こうとしない罪に、神の怒りが告げられました。しかもイザヤがどんなにそれを語っても、人々は頑固というか鈍感というか、のらりくらりと逃げ回る有様でした[i]。しかし、やがてその日には
「主よ、感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださった」
というのです。主の怒りに相応しい、自分たちの罪を認める姿と、その怒りは去り、慰めてくださった――そんなことをいう、大変化です。どうでしょう、あなたもこう心から言う日が来るとは[ii]? ゆっくりと
「見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れない。ヤハ、主は私の力、私のほめ歌。私のために救いとなられた。」
と。
この「あなた」には、主に聞こうとしなかった人々も含まれるでしょう。またそうした権力者に虐げられてきた、社会的弱者、貧困、囚われた人、人間らしい扱いを受けてこなかった人々も含まれます。そうした長く深い抑圧を受けた人々には、こんな言葉は「余りにも明るく、綺麗すぎて、信じられない。無神経で腹立たしい」と思われるでしょうか。あるいは、現実逃避して、あの世や未来に夢を抱かせようとするインチキ宗教に聞こえるでしょうか。
ですから、この12章や11章からの明るい言葉だけを取り出すのでなく、この前にはキッチリとシッカリと、現実の世界の不正や暴力、格差の構造などの問題を、イザヤは厳しく非難していることを、忘れずに思い出しておきましょう。そして、人の心の深い傷は、いきなり薔薇色のユートピアに行ったからって癒されるものではなく、ましてそんな話を聞かされて希望を持てるものではないでしょう。戦争や飢餓、犯罪や虐待、また家族や身近な関係で虐げられてきた経験は、神が怒られる通り、複雑で、神を信じることさえ難しくします。けれども、だからこそ、そういう子どもや大人たちこそ、「模範的な賛美」とか「綺麗な信仰の台詞」などではなく、心から、本当に心から、力強く、感謝と神への賛美を言えるようにさせるのが、主イエスのみわざでなければなりません。神の愛への想いに影を刺すような体験、人の言葉、体に染みついた過去を、本人が拭えず、それが洗い流された自分など想像できないとしても(できないからこそ!)、主がイザヤに託したこの12章が「その日、あなたは言う」と言ってくれている力強さをここに聞き取りたいのです。この言葉を信じられる人は、信じられない人にこれを信じるよう強いるのではなく、信じられない人に代わって信じるのです。そして「その日」にこの言葉を言う時と比べたら、今の私たちの精一杯の感謝や賛美は曇った鏡に写しているような混ざり物で、視野の狭い、そして自己本位を免れないものです。そうした私たちに、主が「その日」を備えてくださって、こういうと約束していてくださることが驚きなのです。
「救い」という言葉はイザヤ書で初登場です[iii]。ただし、イザヤという名前そのものが「主は救い」を意味しますので、1章1節の「イザヤの幻」という書き出しに「救い」が最初から語られていたとも言えます。イザヤ主は救い――なんとも大胆な名前ですが、イザヤだけでなく私たちがみな「ヤハ、主は私の救い」と歌うようになるのです[iv]。そして「救い」が3回目「3あなたがたは喜びながら、水を汲む。救いの泉から。」と水・泉のイメージと結び付けられて語られます。乾燥したイスラエルでは水は貴重でした。聖書には、水は人のいのち、神の恵みのモチーフとして何度も出てきます。主イエスもヨハネの福音書7章で言いました。
「だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書が言っているとおり、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。」[v]
それを言われたのはイスラエルの「仮庵の祭り」の時で、今も祝われる一年で最も喜ばしい祭り「仮庵の祭り」では、このイザヤ書12章3節から取られた歌「マイム、マイム」が歌われます[vi]。マイムとはヘブル語の水です。水、水と歌いながら、水を汲む儀式が行い、昔、先祖たちが仮庵に住んで荒野を旅したこと、途中で主が水を与えてくださったことを思い返してお祭りをする。そうして、今も主が必要な水を与えてくださることを喜びをもって思い起こす。その祭りで、イエスはご自分を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れる、と言いました。イザヤ書の今日の箇所を初め、聖書には水を救いのシンボルとして、私たちが潤され、喜び、生き生きと生かされることの約束が繰り返されます。その約束をイエスは思い出させて、ご自分があの約束を、喜んで水を汲み、歌い、踊る日を来させると言うのです[vii]。
4その日、あなたがたは言う。「主に感謝せよ。その御名を呼び求めよ。そのみわざを、もろもろの民の中に知らせよ。御名があがめられていることを語り告げよ[viii]。5主をほめ歌え。主はすばらしいことをされた。これを全地に知らせよ。…[ix]
この素晴らしい事とは、最後の6節に結びつきます[x]。
6シオンに住む者よ。大声をあげて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる大いなる方。[xi]
主を自分たちの中におられる大いなる方、イスラエルの聖なる方と知った。これが「すばらしいこと」です。そう知るように目を開いたのも、私たちとともにいます神「インマヌエル[xii]」の御業です[xiii]。何か華やかなこと、目覚ましい奇跡や神業をしたことを讃美するのでなく、主が私たちの中におられる聖なる方、あなたの中におられる大いなる方、そういう主として告げ知らせる。今まで形式的な礼拝儀式だけで考えていた神を、私の中におられる神、として感謝と賛美をささげ、告げ知らせる。貧しさや不正のため、神など遠くかけ離れて信じられないと思っていた人も、その日、こう言う。神を怒りっぽくて怖いだけの神と思っていた人も、その日、こう言う。神も人をも信じることが出来ないような何か重く暗く深いものを心に抱えている人も、その自分の中におられる主と出会う。魂の奥底がカラカラに乾いて、カサカサになっている人も、その日、深く深く潤されて、喜びながら水を汲みながら、主に感謝せよ、主はすばらしいことをされた、と喜び歌う。その賛美と感謝に水を刺すような、過去の経験やいろんな柵しがらみ、呪縛、恥も誇りも比較がその時にはいささかも影を落とすことはなくなって、大声をあげて喜び歌う。
こういう将来があるからこそ、また現在の問題、神も人も蔑ろにしてぞんざいに扱われるあり方を、私たちは強く非難するのです。罪を罪だと批判するだけでなく、ここにも聖なる主がおられることが見えるよう、わかるよう、少しでも改善しようとします。その私たちの毎日を励ますのは、主が無条件に約束している、この将来、私たちがこう言う、という幻です[xiv]。
「創造主、贖い主、完成者なる主イエス。あなたを賛美し告白するこの礼拝でも、私たちの内には様々な相容れない思いが澱んでいます。あなたを心から褒め称え、ともに歌う日、何の引き攣る思いもなくそう言える日は、主よ、人となり渇く生涯を送り[xv]、御怒りをすべて引き受け、私たちを喜んでくださるあなたからの恵みです。どうぞ、その日への旅路においても、私たちのうちにいて、素晴らしい御業を続けてください。私たちの心を高くあげさせてください」
[i] イザヤ書6・9~13、7・10~13、9・8~10、など。また前の7章では、アハズ王がこの言葉から逃げました。「気を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない」と言われるのにアハズ王は身をかわしました。イザヤ書7章、特に4節と11~13節を参照。
[ii] 私自身、自分の罪を出来るだけ認めまいという誘惑も常にありますし、同時に、その罪を主が全く怒らない日が来るとは、どこかで信じきれない思いを抱いていることもあるのです。
「ヤハ」は太字で「主」とある主の名(おそらくはヤハウェ)の短縮形です。
[v] ヨハネの福音書7章37~38節。また、同4章13節も参照。
[vi] ユダヤ教3大祭りのひとつ「仮庵の祭り」とは?(新生宣教団)、仮庵の祭り「スッコート」 聖書暦第7月 メシアニック運動 情報サイト
[vii] イエスこそは、私たちの救いとなり、私たちのほめ歌、救いの泉となってくださった神です。今なお、その告白は私たちにとって途上であるとしても、主イエスはこの言葉がご自身において私たちに与えられると約束してくださっています。
[viii] 4節の背景には以下の聖句が酷似したものとして想定できる:詩篇105・1(主に感謝し 御名を呼び求めよ。そのみわざを諸国の民の間に知らせよ。)、I歴代16・8(主に感謝し、御名を呼び求めよ。そのみわざを諸国の民の間に知らせよ。)。詩145・4〜6(代は代へと あなたのみわざをほめ歌い あなたの大能のわざを告げ知らせます。私は あなたの主権の栄光の輝き あなたの奇しいみわざを語り伝えます。人々はあなたの恐ろしいみわざの力を告げ 私はあなたの偉大さを語ります。)
[ix] 出15・1(そのとき、モーセとイスラエルの子らは、主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。「主に向かって私は歌おう。主はご威光を極みまで現され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。)、21(ミリアムは人々に応えて歌った。「主に向かって歌え。主はご威光を極みまで現され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。」)、詩68・32(地の王国よ 神に向かって歌え。主にほめ歌を歌え。セラ)、98・1(新しい歌を主に歌え。主は 奇しいみわざを行われた。主の右の御手 聖なる御腕が 主に勝利をもたらしたのだ。)
[x] 「神である主がすることなんだから素晴らしいのは当たり前で、素晴らしいって言わなきゃ冒瀆」という事ではありません。賛美をそのように捉えることが、家父長制の影響を受けた神観には拭えないのが現在ですが、そのような構造そのものが、終末論的には霧消するのです。
[xi] 6節の背景にある聖句は以下の通り:ゼパニヤ3・14(娘シオンよ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。娘エルサレムよ、心の底から喜び躍れ。)、イザヤ1・4(わざわいだ。罪深き国、咎重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。)、41・14(恐れるな。虫けらのヤコブ、イスラエルの人々。わたしがあなたを助ける。──主のことば──あなたを贖う者はイスラエルの聖なる者。)
[xii] イザヤ書7・14、8・8、10(欄外)参照。
[xiii] 「この書のこの部分の最後の節が「イスラエルの聖なる方」という表現で締めくくられているのは、決して偶然ではありません。12 なぜなら、ここで述べられているすべての根底にあるのはこの概念だからです。前述のように、聖性は神性の属性の総体です。根本的に、それは神を単なる人間性から区別するものを意味します。イザヤが経験的に発見したのは、イスラエルの信仰全体が何であるか、すなわち、宇宙で唯一の聖なる方がイスラエルの神であるということでした。しかし、それ以上に、神の性格、つまり神の聖性の中身が、神を際立たせています。その性格は偶像とは根本的に異なるからです。神は正しく、清く、純粋で、真実です。これらすべてを考慮すると、民が犯し得る最大の愚行は、この神を偶像のように扱うことであろう。偶像とは、崇拝者が儀式において操り、崇拝者の汚れた利己的な動機のみを表現する、日々の政治的現実とはほとんど関係のない非人格的な力である。そのような行いは、ただ破滅をもたらすだけである(6:3)。しかし、まさにこの神、唯一の神の聖なる性質ゆえに、希望がある(6:7, 13)。神の異質性は、人間性が移ろいやすく邪悪であるところにおいて、神は忠実で真実であることを意味する。このように、神の聖性ゆえに、預言者は、回復された民が彼らの唯一の財産である聖なる方を、陽気に祝う日が来ることを信じることができる。この信仰は、今度は神の自己啓示の意味を指し示しています。すなわち、聖なる神がその被造物の間に住むということです (出エジプト 40:34、35、イザヤ 57:15(いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方が、こう仰せられる。「わたしは、高く聖なる所に住み、砕かれた人、へりくだった人とともに住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。)、66:1、2(主はこう言われる。「天はわたしの王座、地はわたしの足台。あなたがたがわたしのために建てる家は、いったいどこにあるのか。わたしの安息の場は、いったいどこにあるのか。2これらすべては、わたしの手が造った。それで、これらすべては存在するのだ。――主のことば――わたしが目を留める者、それは、貧しい者、霊の砕かれた者、わたしのことばにおののく者だ。)、ヨハネ 1:14(ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。)、14:15、17(もしわたしを愛しているなら、あなたがたはわたしの戒めを守るはずです。…17この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなたがたは、この方を知っています。この方はあなたがたとともにおられ、また、あなたがたのうちにおられるようになるのです。))。」、Oswalt, 6節の注解。Google翻訳による。
[xv] ヨハネの福音書19・28。