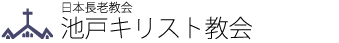2025/7/27 イザヤ書14章24〜27節(24〜32節)「喜ぶのは早い」エペソ2・19〜20 #191
イザヤ書14章は、13章から続いてきた「バビロンについての宣告」です。次の15章は「モアブについての宣告」に切替わります。ですが、今日の24節からには、25節で「アッシリア」29節には「ペリシテ」とあります。色々な外国の名前が出て来て混乱して、「私たちには関係がない話」という思いを強くしてしまいそうです。そこで、主の祈りを思い出してください。
主の祈りでは第二祈願で「御国が来ますように」と祈り、最後の第六祈願で「私たちを試みに会わせないで、悪からお救いください」と祈ります。この世界には確かに「悪」がある――「悪い者」や「悪魔」とも訳せる人格的な悪の働きから、私たちを守ってください。そうした悪が完全に終わる、永遠の「御国が来ますように」の第二祈願と切り離せない、大きな祈り、かつ私たちの具体的で身近な生活においても、禍や悪事や罪から守られることを祈るのです。
このイザヤ書13、14章の「バビロンについての宣告」もそうです。バビロンはバベルと同じ言葉で、創世記のバベルの塔から、黙示録の「大バビロン」まで続く、神に逆らい、自分の国を建てようという力の総称です。イザヤ書が書かれた時代にも「バビロン」という国はあり、100年後には新バビロニア帝国となってユダ王国を攻め落とすほどになりますが、その特定の国を指して将来のことをイザヤは預言したというよりも、この時点では、諸国についての宣告の真っ先にこのバビロンが挙げられるように、神を忘れて高慢になり、今でも天に届くような塔を建てようと虎視眈々と狙っている動きを語っています。そして、そうした人間の思い上がりは必ず崩れる。バビロンの企みは決して成功しない、と歌うのです。
24万軍の主は誓って言われた。「必ず、わたしの考えたとおりに事は成り、わたしの図ったとおりに成就する。
そしてそれは今イザヤの時代、目下リアルな脅威として、圧倒的な勢力を誇るアッシリアが、主によって打ち破られることで現実になるのです。「25わたしはアッシリアをわたしの地で打ち破り、わたしの山で踏みつける。アッシリアのくびきは彼らの上から除かれ、その重荷は彼らの肩から除かれる。」いわば、バビロン(バベル)と呼ばれる悪が絶ち滅ぼされるしるしとして、この先のアッシリアの敗北、惨敗がもたらされるのです。
26これが、全地に対して立てられた計画。これが、万国に対して伸ばされた御手。27万軍の主が計画されたことをだれがくつがえせるだろうか。御手が伸ばされている。だれがそれを押し戻せるだろうか。
主は悪を倒す。絶大な権力を掌握しているような国家でさえ、主は御手を伸ばして、その繁栄を終わらせる。高ぶって、人に軛や重荷を負わせて、自分の名を上げようとする企みを引っ繰り返されるのが主の計画であり、必ずそれを果たすのが主の御手なのです。
しかし、イザヤの時代にアッシリアが倒されたのは、主が悪を究極的に倒す――バビロンを滅ぼす、と約束されたことそのものではありませんでした。それはまだ先のことです。イザヤの時代から百年少し後に、バビロンの名前をそのまま冠した新バビロニア帝国が滅ぼされ、捕囚になっていた人々がエルサレムに帰ってきました。それは大きな喜びであり、それ自体、奇蹟とも神の御業という一面がありました。しかしそれは、主がバビロンを滅ぼす、悪の力を終わらせる、と約束した預言の成就そのものではありませんでした。それから更に後、紀元4世紀に、「大バビロン」と黙示録で仄めかされたローマ帝国が、キリスト教迫害からキリスト教の公認、国教化に転じた時も、教会は大いに喜び、主を讃美しました。それも、主がなしてくださった信じがたい御業でもありました[i]。しかしそれも、悪に対する最終的な勝利そのものではありませんでした。悪の帝国とか軍事大国が滅ぼされるのは確かに喜ばしい事、大いに喜ばしい事です。禍が終わり、大変な事態から救い出されるのは、本当に有難い恵み。けれども、それは主の御計画のほんの一部です。主の御手はそこでは終わりません。
「くびきは除かれ、重荷は肩から除かれる」に似た表現は、今までにも何度かありました[ii]。ここでもアッシリアを踏みつけるだけでなく、アッシリアが首に枷を着け重荷を背負わせた人々の重荷が除かれることこそ、主の計画だと言われています。戦争が終わる、敵が打ち負かされる――それだけでは、本当の平和は来ません。また、本当の悪はただ支配するだけでなく、自分が消された後にも深い痛みと傷、暗く荒んだ影響、絶望や憎しみや疑いの闇を残そうとするものです[iii]。戦争を終わらせるだけではない、戦争の残した傷がじっくりと十分にケアされることや、そもそも戦争を引き起こした不公正や抑圧の軛、憎しみや罪の重荷が押し付けられたままなら、平和とは言えません。平和「シャロームは、戦争がないだけではなく、不正義、貧困、構造的暴力がなくなること」も含みます[iv]。そして、主イエス・キリストはそのような
「平和の君」[v]
としておいでになりました。人々は、ヘロデやローマの圧政からの解放を期待しましたが、イエスは排除された人、見下された人、友なき者の友となりました。
「すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい」
と招いて[vi]、平和の道を示されたのです。私たちは「悪からお救いください」と祈る時、当座の悪や争いが終わりさえすれば平和が来るのではないことを、最終的な平和と取り違えないことを確認する必要があります。
28節以降はその具体例です。
アハズ王が死んだ年
とあり、32節に
異邦の使者たち
とある。ペリシテからアハズ王の訃報にお悔やみを述べるため使者たちが遣わされてきたのでしょうか。アハズの死に悔みを言いつつ、反アッシリアだったペリシテは、ユダにも自分たちの同盟に加わるよう誘った、という理解なら筋が通ります[vii]。その使者たちに
「喜ぶな」
と窘めるのが29節で、
30弱い者たちの調子は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし、わたしはおまえの根を飢えで死なせる。おまえの残りの者は殺される。
と、安易な希望的観測で喜ぶより、ペリシテもまもなく世界の流れに呑み込まれて、715年アッシリアに滅ぼされたのでした。そして、主を仰がせる言葉で結びます。
32異邦の使者たちにどう答えるべきか。『主がシオンの礎を据えられたのだ。主の民の苦しむ者たちは、ここに身を避ける[viii]。』
主の目は、ご自分の民の苦しむ者たちに向けられています。敵への憎しみや悪への怒りで一杯ではないのです。ご自分の民の、弱い者、貧しい者、苦しむ者にいつも目を注がれる。その人々の避け所、憩いの場所、安心してそこに来て、長年の軛や重荷ですっかり傷んだ体をも伸ばして、深く養われる――そういう避け所を備えられる主なのです[ix]。
「喜ぶな、ペリシテの全土よ」と言いますが、ペリシテ人だけのことではありません。主の民の中にも、キリスト者の中にも、目先の厄介な出来事が解決したからと言って喜ぶことがあります。一過性のことで喜んで窘められるペリシテ人は、誰にとっても鏡です。「バビロンへの宣告」の締め括りに当たるのは、バビロンが滅ぼされる、勧善懲悪でチャンチャン、が結びなら取り残されるような、苦しむ者、名もない弱い者、軛を負い疲れて、声も出ない貧しい人人のことです。その痛みが癒され、悪しき力の爪痕がすっかり治される――「主の民の苦しむ者たちは、ここに身を避ける」、ここにバビロンの悪は完全に無力で、敗北が宣言されます。
「そんな平和、信じられない」と思うがあるなら、それ自体、今バビロンの言葉が強く勝っている証拠なのかもしれません。同時に実際、今の世界で戦争や暴力の深い傷があまりに酷く、癒しも慰めもないと思ってしまうのも現実でもあります。そうです、御国が最終的に訪れて、悪を打ち負かす日まで、今はまだどんな勝利も不完全です。どんな喜びにも酔い痴れず、なお喜べない人、悲しむ人がいること、痛む人がいます。そこにこそ主イエスがおられて、最後の平和を始めたり、垣間見させてくださるよう「御国が来ますように」と祈る。そして、私たちもそこに目を向けて生きることで、悪バビロンの終わりを先取りして宣告する存在となりたいのです。
「平和の主、イエス様。重荷を負う人を招くため、いのちを惜しまなかった主よ。あなたの平和を褒めたたえます。戦争がまた起き、止まない中、改めて、平和と見えた世界にどれほどの問題や苦悩があったかを思い知らされます。主よ、戦いを終わらせてください。上からではなく、苦しむ人が身を避け、弱い者、貧しい者が心から喜ぶ、あなたの平和により、悪が終わる日を待ち焦がれさせてください。御国が来ますように。悪からお救いくださいますように」
[i] 「「新しい歌を主に歌え。主は、奇しいわざをなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に現された。」主の戦いでの勝利を祝う詩篇九八篇一、二節です。最初の教会史家エウセビオスが、コンスタンティヌス帝の台頭によってキリスト教の神がついに勝利を収めたとの感慨を込めて、著書『教会史』の最終巻の冒頭で引用した詩篇です。/勝利の賛美を歌う教会! これは、四世紀の公同教会の姿を見事に表現しています。ついに日の目を見た教会! それまで「人類の敵」「無神論者」と非難され、迫害に甘んじてきたものが公認を勝ち取った! そんな教会を創造してみてください。賛美と喜びの声はどのように響いたことでしょうか。」、丸山忠孝『キリスト教会二千年』、いのちのことば社、1985年、46ページ。
[ii] イザヤ書9章4節(あなたが、彼が負うくびきと肩の杖、彼を追い立てる者のむちを、ミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。)、10章27節(その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼のくびきはあなたの首から除かれる。くびきは脂肪のゆえに外される。)
[iii] この事例としては、映画「セブン」、マンガ「Monster」(浦沢直樹)などを推薦します。
[iv] 「(講師の左近豊氏は)冒頭では、戦争中のロシア、ウクライナ、イスラエル、ハマス、加えて西欧、米国がキリスト教、ユダヤ教、イスラム教を背景にしており、「時に聖書を盾にした、暴力、戦争がまん延してきた」と問題提起。4月に編著刊行した『聖書における和解の思想』の研究成果にも触れ、「シャロームは、戦争が無いだけではなく、不正義、貧困、構造的暴力がなくなることも言う。聖書の中で、構造的暴力を含めての戦争をどう考えたらいいのか」と述べた。/古代イスラエルは、南は大国エジプト、北からの古代メソポタミアの諸帝国に挟まれ、交易の要衝であり、緩衝地帯であり、覇権がせめぎ合う最前線であった。この地は、出エジプトからバビロン捕囚まで「戦闘と殺戮に脅かされ、晒され続けた期間でもあり、人間観も世界観も戦争のリアリティに彩られ、深く影響を受けたものとなっていたと言える」と説明。/中でも、紀元前8世紀以降に、古代イスラエルの人たちの価値観や観点に多様な影響を及ぼしたアッシリア文化とそのプロパガンダによる「アッシリア・イデオロギー」への抵抗について、旧約学者T・レーマーの『ヤバい神』(新教出版社)の見解を示しつつ、紹介した。「聖書の『戦争物語』には、アッシリアの『戦争物語』との対決がある」として、「この文脈と切り離して、聖書そのものの『戦争』観として誤解し誤用する」ことを戒めた。」、「旧約聖書における戦争 現代の暴力に帰結する解釈の危険性に警鐘 日本福音主義神学会東部部会春季公開研究会から」『クリスチャン新聞』2025年6月8/15日号、4頁。
[v] イザヤ書9章6節より。
[vi] マタイの福音書11章28節。
[vii] 「アッシリアの時代に、ペリシテは絶えずアッシリアに敵対した。前七三四年に、ガテはアッシリアにみつぎものを贈ることを拒んだので、侵略を受けた。前七二〇年には、ペリシテはエジプトと協力して反旗をひるがえしたので、サルゴンⅡ世はエジプト軍をガテで打ち破り、アシュケロンとガザを占領した。前七一一年にパレスチナ西部の同盟軍がアッシリアに反抗したが、アシュドデはその中心的役割を果たした。前七〇五年、アシュケロンは反旗をひるがえしたが、前七〇一年、セナケリブによって攻略された。前七一五年にアハズが死んだとき、多分ペリシテは反アッシリア同盟にヒゼキヤを誘ったに違いない。アハズ王の死に弔意を表すために来た使節がそのような行動をすることは、十分に考えられることである。そう考えることが、この箇所を理解するのに大変役に立つ。」 モティア、160〜161ページ
[viii] 「身を避ける」は、イザヤ書の中で発展する思想:4章6節(その仮庵は昼に暑さを避ける陰となり、嵐と雨から逃れる避け所、また隠れ家となる。)、25章4節(あなたは弱っている者の砦、貧しい者の、苦しみのときの砦、嵐のときの避け所、暑さを避ける陰となられました。横暴な者たちの息は、壁に吹きつける嵐のようです。)、32章2節(彼らはそれぞれ、風を避ける避け所、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある、大きな岩の陰のようになる。)、57章13節(あなたが叫ぶとき、あなたが集めたものどもに、あなたを救わせよ。風が、それらをみな運び去り、もやがそれらを連れ去ってしまう。しかし、わたしに身を寄せる者は、地を受け継ぎ、わたしの聖なる山を所有することができる。)
[ix] 「第一に、神ご自身の臨在である。直訳すれば、「主ご自身が……」。第二に、シオンの民がすでに得ている安全性である。彼らは選ばれた主の町に住み、約束のうちに安全である。(例 28・16)。第三に、人間の弱さは問題にならない。「悩む者」(すなわち、虐げられている)は、絶望的な状況にあるが、それでも「主の民」であり、主の選ばれたシオンに住んでいる(ヘブル12・22〜24)。第四に、彼らは身を「避ける」場所を持っている。シオンの都において主は、その民とともに住んでおられるからである。」 モティア、163ページ