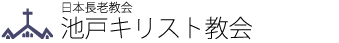2025/7/20 イザヤ書14章1〜8節(1〜23節)「力強い安らぎの歌」
イザヤ書は、イスラエルの歴史の中でも大変混迷を極めた時期、紀元前8世紀から7世紀にかけて書かれました。イスラエルの形式的な宗教を批判する厳しい言葉が続きますが、その節目々々や、区切りの最後には力強い回復の約束が宣言される、宣言され続ける書です。13章から35章のまとまりを先週から読んでいます。この14章は13章と合わせてバビロンへの宣告が告げられますが、ここでもそうです。今日の14章1節以下にはイスラエルの回復が、美しく、力強く歌われています。
まことに、主はヤコブをあわれみ、再びイスラエルを選んで、彼らを自分たちの土地に憩わせる。…
今は、イスラエルは南北に分裂し、神の怒りに値するような体たらくです。その罪を厳しく非難し、終わりは避けられないと予告されつつ、その先にはすべての国々も終わり、主のあわれみによって、憩う日が約束されるのです。
それはイスラエル民族だけの祝福ではありません。
…寄留者も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。2諸国の民は彼らを迎え、彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地で、その寄留者を男奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを捕らえた者を捕らわれ人にし、自分たちを追い立てた者を支配するようになる。
奴隷とか囚われ人、支配という言葉が出てきますが、決してイスラエル人が外国人(異邦人)をこき使って踏みつける、という意味ではありません。すべての支配、抑圧や虐待は終わって、諸外国がイスラエルを搾取・占領していた関係も解消する――でも代わって、イスラエルが仕返しをする、下剋上が始まるのでもなくて、捕らえたり追い立てたりする暴力は金輪際一切なくなり、迎え入れ、喜んで仕えるのです。
3主が、あなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを憩わせる日に、4あなたはバビロンの王について、このような嘲りの歌を歌って言う。…
と以下、その歌が続くのですが、ここまでの将来の回復を豊かに描いたエッセンスはイザヤ書後半40〜66章に展開していきます。逆に言えば、イザヤ書最後27章の希望をギュッとまとめたのが、この14章冒頭の数節とも言えます[i]。今は、こんな憩いや平和は到底信じられない、想像も出来ないけれど、主はこう約束されます。これが主の言葉です。聖書の描く将来の約束です。そして明るい言葉はここで終わって4節後半からはバビロンへの裁きの言葉だというのでなく、このバビロンへの裁きの言葉自体、将来の平和、回復がもたらす歌です。ぬくぬくとした平和、破られるかもしれない楽園、というのとは違い、すべての悪、暴力、人を虐げる力が終わることが、この4節から21節まで続く「嘲りの歌」で歌われます。これは「ヘブライ語詩の中でも最高傑作」とも言われ[ii]、ただ暗く重い裁きではないのです。
前回も申しましたように、この13章14章で名指しされる「バビロン」とは、バビロニア帝国というよりも、創世記の「バベルの塔」に始まり、黙示録の「大バビロン」まで続く、神に逆らう権力全体を示しているようです。
4…「虐げる者はどのようにして果てたのか。横暴はどのようにして終わったのか。5主が悪しき者の杖を、支配者の笏を折られたのだ。
と始まり
7全地は安らかに憩い、喜びの歌声をあげる。8もみの木もレバノンの杉も、おまえのことを喜ぶ。『おまえが倒れ伏したときから、もう私たちを切り倒す者は上って来ない。』
と世界の人々も木々や自然界も、この横暴な支配者の終わりを喜ぶ、というのです。
9節からは
よみは、下界でおまえが来るのを迎えようとざわめき、…
と滅ぼされた後、死後の陰府よみの国に落とされる様子が描かれます。そこはもう誰も選ぶることも、誰かが大きな顔をすることもない、死者の国です。人の世で、どんなに繁栄を極め、頂点に君臨し、成功に自惚れたとしても、それらは何の役にも立ちません。その虚しさが嘲って歌われるのです。
ところで、この12節
明けの明星、暁の子よ。どうしておまえは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしておまえは地に切り倒されたのか。
13おまえは心の中で言った。『私は天に上ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座に着こう。
14密雲の頂に上り、いと高き方のようになろう。』
15だが、おまえはよみに落とされ、穴の底に落とされる。
は、バビロンよりも奥にある存在、サタンのことだ、という解釈が2世紀後半から生まれました[iii]。かつて「明けの明星、暁の子」と称されるほど最高の地位にいた天使が、「私は天に上ろう、いと高き方のようになろう」と自惚れたため、サタンになったという、悪魔の起源がここにある、という読み方です。悪魔を「堕天使」と呼んだり、「明けの明星」のラテン語ルシファーがサタンの名前だとするようになったのもそこからで、そんな呼び方は今や世界に広まっています。聖書の理解としては、ここに悪魔の起源を読み取ろうとすることは「書かれていることを超え」ている[iv]、という理解が主流ですが、バビロンへの言葉の向こうにサタンのことも言われている、という解釈をする立場もなくなってはいません[v]。
しかし、そもそもサタンがどうして誕生したのか云々を知ることに興味を持つこと自体、サタンの思う壺でしょう[vi]。聖書がはっきりと語っているのは、最初に作られた世界のエデンの園で、サタンは蛇の形をとってエバとアダムを誘惑したという物語です。禁じられていた木の実を食べたら、目が開かれて、あなたがたは神のようになって善悪を知る者となる、という言葉で誘ったことです[vii]。そしてそれ以来、人間は神に近づこうとし、頂が天に届く塔を建てよう、神のようになろう、神のようになれる、と自惚れてきたことです。バベルの名はその想起です。そしてそのバビロンの言葉、天に上ろう、神のようになろう、という言葉や、そこに隠されている、神を小さくし、神を嘲り、神の誠実さ、聖もあわれみも疑う言葉は、主の言葉に勝って力あるかのように私たちの中に浸透しています。「神は、人が神のようになれる方法を隠しているのだ」という蛇の嘘が、私たちと神との関係、私たちの願い、生き方や将来を歪め、サタン誕生のファンタジーの根底にもあります。この解毒作業のほうが遥かに大事です。
前回13章で、バビロンへの宣告の真ん中12節に
わたしは人を純金よりも、人間をオフィルの金よりも尊くする。
という言葉がありました。14章でも20節に
おまえは墓の中で彼らとともになることはない。自分の地を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。
とあります。外国や他民族に対する罪も指摘されています。しかし、国民に対しては潔白、よい政治をしている、ということはない。人を純金よりも尊ぶどころか、労働力や戦力にし、道具にして、消費していく。結局、自分の国を荒廃させ、滅ぼしてしまう。そう責められるのです[viii]。
いや、この言葉は4節から21節まで続く、バビロンへの嘲りの歌の結びです。やがて主の民である「あなた」が歌う歌詞の台詞です。主なる神や預言者イザヤでなく「あなた」が、バビロンの暴力を正々堂々と言葉化するのです。そして頭にも染み付く、高ぶりの言葉、神を卑しく考え、上に立ちたい、そうして神のようになろう、という言葉も笑い飛ばさせてくださる。そして、聖書の最後、黙示録でも、18章19章と大バビロンの完全な終わりと、神が王となったと歌う賛美が声高らかに歌われるのです。私たちは今、混迷の只中で、この歌を聞くのです。
本当の神は、のし上がった先に近づくような神でも、そんな企みを許せず、秘密を隠すような卑怯な神ではありません。そんなものは人間が考えた宗教、空想ファンタジーです。神である主は憐れみの神、低く謙る神です。背いた人間を追いかける神です。滅ぼし合う人間のため、天から降りて、十字架の死に至るまで低く卑しくなる方です。「上がよくて下は恥ずかしい」という根深い嘘を自ら引っくり返し、私たちを取り繕うとか背伸びする生き方から救い出すため、私たちの心の奥深い闇に降りて来てくださった。そしてバビロンという言葉に託して外からの凡ゆる暴力からも、心の罪からも完全に解放される日に向けて、今を生かしてくださっています。
「『明けの明星』なる主よ[ix]。厳しい裁きの言葉の合間に、あなたの力強い希望の約束が光差しています。だからこそ、それとはかけ離れた痛み、苦しみ、重荷が今ある悲しみも胸を塞ぎます。夜明けを待ち侘びながら、今この時も、夜の終わりを先取りする歌を歌い、励まし合い、仕え合い、新しい言葉を紡がせてください。高ぶりや卑下の言葉の支配から心の考えも唇からの言葉も解放し、あなたの恵みと赦しの言葉で、日々少しずつでも新しくし続けてください」
[i] 「歴史の中心主の民 (14・1-2) ここには、新しい世界、すなわち協力が敵意にとって替わる世界の幻がある。それは主の新しい日であって、相互的な破壊へ至る狂暴な情熱は、一致によってとって替わられ(1節)、敵対心は助けの心によってとって替わられる(2節)。しかし、この新しい人間性の開示の背後に、神の主導権があり(あわれみ)、選びと定住があるのである(1節)。バビロンからの帰還(前五三九年)のときに実際起こったことは、うわべだけのことであった。クロスは、軍人から政治家に転身した多くの人々のように、自らの手で剣を口の舌に替えて(エズラ1・2―4)、見せかけのあわれみのもとに、優位な立場からできることをしたのである。そこには国際的な喝采も、援助の意志もなければ、支配者と捕囚にされた者の役割の逆転もなかった(2節)。ひとことで言えば、バビロンの崩壊が主の「日」の一つの側面の中間的な成就だったように、神の民の帰還はその別な側面のごく小さい成就だったのである。それぞれが前兆であり、脅威あるいは約束はまだ完全には成就しないのである。」、モティア、152〜153ページ
[ii] 「これはヘブライ語詩の中でも最高傑作の一つであることに、広く異論はありません。言葉のバランス、力強さ、そして比喩表現の力強さは、ヘブライ語詩の最高傑作の特徴です。」、オズワルト。
[iii] 「一二節から一五節は、高慢なバビロン王の滅亡を語った預言ですが、テルトリアヌスなどの教 会教父たちは、これが、又、天使長であったサタンの墜落を語った言葉として解釈しました。私はバビロンの王の墜落とサタンの墜落が二重に重ねられて預言されていると思います。暁の子、 明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。それは、心の中で高ぶり、私は天に上ろう。 私の位を神の星々の上にあげ、高い密雲によって至高者のようになろうと思ったからです。僭越 にも神の位に着こうとしたので、よみに落とされ、穴の底に入れられたのです。このように高慢のために天界を追放されたサタンは、エデンでエバを誘い、禁断の木の実を食 べれば、目が開けて神のようになると誘惑して来たのです。そしてエバも高慢のために罪に落ち たのです。戒めるべきは、高慢です。」、油井、122〜123ページ。「教父の中には、この箇所をルカによる福音書10章18節や黙示録12章8節と9節と結び付け、そこに記されているサタンの堕落を指していると解釈する者もいました。しかし、宗教改革の偉大な解説者たちは、この箇所の文脈はそのような解釈を支持していないと異口同音に主張しました。」、オズワルト。
[iv] 「書かれていることを超えない」
[v] 伊藤淑美「悪魔論」、『新キリスト教辞典』いのちのことば社、1991年。
[vi] C・S・ルイス『悪魔の手紙』序文より。
[vii] 創世記2・1〜13:
[viii] 読者は、王が抑圧した外国(七十人訳聖書では「わが国。わが民」)に対して行った行為について裁かれると予想するが、実際には、自らの国と自らの民を滅ぼし、そのことで裁かれるのである。よく考えてみると、この真実が明らかになる。あらゆる偉大な暴君の帝国主義的計画の原動力となってきた傲慢さは、他の場所と同様に自らの国と民に対しても破壊的であったからである。しかし、暴君が他民族に対して何を行なったにせよ、それは自らの民であり、その民を牧し、搾取したことは最も非難されるべきことである。この原則は暴君に限ったことではない。私たち一人ひとりが、自分の仲間以外の人々に何を行なったにせよ、まず第一に、私たちの傲慢さが自分に最も近い人々に何を行なったかに対して責任を負っているのである
[ix] ヨハネの黙示録22・16(わたしイエスは御使いを遣わし、諸教会について証しした。わたしはダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。)、また、同2・28(わたしも父から支配する権威を受けたが、それとおなじである。また、勝利を得る者には、わたしは明けの明星を与える。)参照。