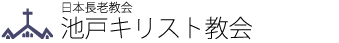2025/4/6 イザヤ書8章(6~18節)「御顔を隠しておられる方を待ち望む」
1節の「マヘル・シャラル・ハシュ・バズ」という舌を噛みそうな名前は、欄外に「分捕り物はすばやく、獲物はさっと(持ち去られる)の意」とあります。その名を大きな看板に大書させて印象付けます。「普通の文字…で書け」とは誰もが読めるようにということでしょう[i]。更に3節では「女預言者」つまりイザヤの妻が子を身ごもり、生まれた男の子に、主は「その名をマヘル・シャラル・ハシュ・バズと名付けよ。」と言われます。ここでその意味が明らかにされます。
4それは、この子が『お父さん。お母さん』と呼ぶことを知る前に、ダマスコの財宝とサマリアの分捕り物が、アッシリアの王の前に持ち去られて行くからである。
最初に看板を書かせ、それからイザヤの妻が身籠り出産まで十月十日、お父さんアブ、お母さんエムと呼ぶまで、二、三年でしょうか。それまでに、アラムの首都ダマスコも、北イスラエルの首都サマリアも、ともに更にアッシリア帝国に「すばやく…さっと」滅ぼされ強奪される予告でした。
前回7章ではアラムとイスラエルが連合してユダに攻めて来たけれど攻めきれなかったと前置きされました。実際、二つの国は引き上げたのです。ユダの民はそれをお気楽に喜びました。主への信頼は棚上げしたまま、アッシリアに援助を求めて良かったと浮かれました。6節の
この民は、ゆるやかに流れるシロアハの水[エルサレムの小川]を拒み、レツィンとレマルヤの子[の引き上げたこと]を喜んでいる。
とはその事です[ii]。しかし7節からはそのアッシリアが大河ユーフラテスの向こうから大洪水のように溢れて押し寄せ、アラムとサマリアを呑み込み、更にユダにまで勢いよく流れ込んで来ると言います。喜んではいられません。それでも「首にまで達する」とは首までで留まり守られる、ということでしょうか。
8…その広げた翼は、インマヌエルよ、あなたの地をおおい尽す。
インマヌエルも欄外に「神はわれらとともにおられる、の意」とあります。10節も
はかりごとをめぐらせ。しかしそれは破られる。事を謀れ。しかしそれはならない。神が私たちとともにおられるからだ。
も欄外に「インマヌエル」とあります。インマヌエル神が私たちとともにいます。これが繰り返され、枠組みになります。大国アッシリアがユダも略奪して世界を征服しようという謀はかりごとは成りません[iii]。当面の脅威が去っただけで安堵するな、帝国が版図を広げてここまで押し寄せる日は近い。人の営みや王座や国家も、明日にはもっと強い勢力が奪うようなもの。でもその強い国よりも遥かに強い神がおられて、人の謀を挫く。その神への信頼こそ、イザヤが告げる言葉でした。
しかしこの時、ユダのアハズ王も民も、目に見えない神、主を信頼するより、目に見える力、特にアッシリアを頼ることを国策としました。11~15節には、主が力強くイザヤを捕らえて、この民が謀反と呼ぶものを謀反と呼ぶな、この民が恐れるものを恐れるな、おびえるな、万軍の主、主を聖なる者とせよ、と言われます。裏を返せば、イザヤを「国策に水を差す謀反人」と呼んで叩く風潮があったのでしょう。16節に
この証しの書を束ねよ。このおしえをわたしの弟子たちのうちで封印せよ。
とあるのも、主の教えを守るために文字に書いて本(巻物)にして弟子たちの間で保管する、切迫した緊張が語られます。しかしそこでなお言い切ります。
17私は主を待ち望む。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みを置く。18見よ。私と、主が私に下さった子たちは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでのしるしとなり、また不思議となっている。
主は御顔を隠しておられる。けれども自分と子どもたち――7章のシュアル・ヤシュブちゃん、8章のマヘル・シャラル・ハシュ・バズちゃん、――まだ幼い。少なくとも弟のマヘル・シャラル・ハシュ・バズちゃんは母と一緒にいて、パパ、ママさえ言えない幼児です。シュアル・ヤシュブちゃんはもうちょっと大きくなったでしょうか。そんな小さな子どもでも、父親にとっては可愛い子らでしょう。その名前と存在が、またその子らがもたらした喜びや毎日が、見えない主のしるし、不思議な主の証しになったのでしょうか。神が私たちとともにおられる。それ以外の事は、壊れたり奪われたり移り変わるけれども、神はともにおられる――その主を待ち望む。そうイザヤは言い、自分と与えられた幼い子らのかけがえなさを言います。何か出来るわけでなく、神々しいわけでもないけれど、主を待ち望む自分と子どもたちを見えない主の証し、神秘というのです[iv]。
さて、8章は、7章と9章がクリスマス預言で知られる中、目立たない章のようですが、この17~18節がそのまま引用されているところがあります。ヘブル人への手紙2章13節です。
ヘブル2・13また、「わたしはこの方に信頼を置く」と言い、さらに、「見よ。わたしと、神がわたしに下さった子たち」と言われます。
ヘブル書ではイザヤの今日の言葉が主イエスの台詞せりふとされています[v]。イザヤが厳しい時代の只中ただなかで主を待ち望み、自分と主が自分に下さった子らを「見よ」と語った事そのものが主イエスを表していたと言うのです。ヘブル書も厳しい時代の最中で書かれました。主を信頼して激動の時代に生きること、安易な楽観もせず不安に動かされるでもなく、ただともにいます神を信頼することの疑問が見え隠れします。そういう葛藤の中で書かれたヘブル人への手紙です。
その2章にあるのはイエスが私たちを栄光に導くために、本当に私たちと同じ人間となってくださり、人間としての苦しみを十分に受けてくださった、という受肉の教理です[vi]。神の子イエスが人となり苦しみを味わったのは、私たちのためであって、私たちを
11…兄弟と呼ぶことを恥と
しないほどでした。その流れで、今日のイザヤ書が引用されるのです。イエスはご自身が神に「信頼を置く」と言うだけでなく、続けて「見よ。わたしと、神がわたしに下さった子たち」と言われるのだ、と。イザヤのあの言葉が、イエスご自身に帰せられます。主なる神キリスト・イエスご自身が、人として多くの苦しみを知り、理解されず、父なる神から見捨てられ、人々から神を冒涜する者と呼ばれながら、なお主なる神に信頼を置いたことの予告でした。そして、それは、私たち人間を救い、神との関係を回復するための受肉であり、苦しみであり、十字架でした。だから、イエスはご自身が主に信頼を置くだけでなく、「見よ。わたしと、神がわたしに下さった子たち」と私たちを呼ぶ事をも恥としません。
私たちは、イザヤの子らのように名前ばかりはあっても、まだ幼かったり、神を父と呼ぶことを習い始めたばかりかもしれません。
「万軍の主、主を聖なる者とせよ。主こそ、あなたがたの恐れ。主こそ、あなたがたのおののき」
ということ、
「神が私たちとともにおられる」
という信仰を習い始めている途上です。しかしそんな信仰を持ち始めた事自体、私たちから始まったことではなく、神ご自身が始めてくださった御業です。自分から始まった信仰心であれば、苦しみや疲れでいつかは挫けるでしょう。ヘブル書が語るのは、イエスが私たちのために、同じ人となり、苦しみを通して生涯を全うされたのだから、イエスは私たちを必ず助け、成長させ、救いに至らせてくださる。その証拠に、イエスご自身が私たちに「幼子のようになる」ことを語ります。また、私たちを指して
「見よ。わたしと、神がわたしに下さった子ら」
と言う事を厭わないのです[vii]。それは私たちの立派さ、信仰の強さを褒めての称賛ではありません。主ご自身が、私たちを愛して、神が私たちをご自身の子とすることを良しとした、一方的な恵みに基づく言葉です。その主が私たちを助け、いつもともにいてくださる恵みは、どんな巨大な人間の力も奪うことが出来ません。
キリスト者の信仰とは、痛みを逃れ、苦しみとはなるべく無縁で済むから大丈夫、という保証とは違います。むしろ、罪や病気から災害や戦争まで、様々な苦難に満ちたこの世界に、神のひとり子キリスト・イエスが来て、人となって、苦しみの生涯を歩み、私たちの罪をも背負って死に、よみがえったこと――このキリストが私の神となった、という福音です[viii]。
「私たちの神よ、今ここにあること、あなたを待ち望む者とされている事自体が、あなたからの一方的な恵みです。イザヤのわが子らへの思いで、あなたが私たちを包んでいてくださる不思議に恐れ戦おののきます。インマヌエル、私たちとともにいます神、この告白がますます私たちの中に深く根付き、生き生きとした力となりますように。あなたを聖なる方とし、何にも勝って恐れさせてください。あなたの御顔が隠れていても、み言葉によって教え導いてください」
[i] 「普通の文字」と訳されたのは意訳で、正確な意味は諸説あります。一番穏健な理解として、この訳と解釈が妥当とされています。
[ii] シロアハは、エルサレムの近くに流れた小川。後にここからシロアムの人工池が造られる。オズワルドの解説:「イザヤは美しい比喩で、神の助けを一見無力な小川に例え、世界の強大な国々の助けをユーフラテス川に例えています。私たちが気づいていないのは、この強大な川が私たちを飲み込み、自らの思惑で飲み込むことがあるということです。最も強いものが外見上は最も弱いように見えるというこの逆説は、聖書のいたるところに見られます。神を信頼する者は、外見よりも深く見なければなりません。」ここで言及されている小川は、キデロンの谷の西側にあるギホンの泉から来て、キデロンとテュロペオンの谷が出会う町の下端にある池まで導水路を通って回っていたようです。現在判明している限りでは、町の真下の水をシロアムの池まで運ぶ有名なシロアムのトンネルは、ヒゼキヤの治世中に掘られたもので、当時は存在していませんでした。」 Google翻訳による。
[iii] この事はイザヤ書で繰り返されて、特に36~37章で詳しく描かれる、イザヤ書において肝心な視点です。
[iv] イザヤの家族だけではありません。16節には「わたしの弟子たち」とあります。この「わたし」が、主なのか(つまり、主の弟子なのか)、イザヤなのか(つまり、エリヤの時代同様、預言者の学校のようなものがこの時もあったのか)は、解釈が分かれるところです。イザヤの言葉に耳を傾けて従う弟子たちがいたと想定できます。すると18節の「主が私に下さった子たち」も、二人の子どもに加えてイザヤに与えられた弟子たちも含んでいるとも考えられます。主が隠れているとしても、その中で主を待ち望む者は、自分だけ孤軍奮闘とは思わず、幼い家族も、わずかであっても主が与えてくださった仲間がいることをもって、不思議にも自分たちこそしるしだ、と深く嘆息するかのように言います。
[v] 安田吉三郎氏の解説を引用します:二番目の引用は、七十人訳によるイザ八17後半から取られたものである。〈わたしは彼に信頼する。〉この短い文章だけでは引用の意図はすぐにはわからない。これは、旧約引用の理解のためにはその文脈や広い背景をよく見なければならないことを示す典型的な例である。預言者イザヤは、彼のことばが王と民に無視されたのを見て、これを封印して弟子たちに保管を命じた。それは、預言が成就した時に、イザヤの語ったことが真の神のことばであったことがあかしされるためである。このようにして後、彼は、「私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に、望みをかける」(イザ八17)と述べる。神がヤコブの家、すなわち、神の民から御顔を隠されるとの預言者のことばは、詩二二篇の「神によって見捨てられた」嘆きと共通のものである。預言者によって体験されたことが、御子によっても同じように体験されるのである。預言者のことばがその民に聞かれないということにおいて、彼は神が御顔を隠されるという事実に直面した。しかしなお彼は主に〈信頼した〉のである。詩二二篇の義人は、「主に身を任せよ。彼が助け出したらよい」と、その苦難の中で人々にあざけられた。しかし彼は、信仰の先達にならって神に「信頼し」、「助け出され」ることを願う(二二8、4、5)。そして、救いを受けた時、「まことに、主は…御顔を隠されもしなかった。むしろ、彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった」(詩二二24)と告白するのである。預言者のことばが民に受け入れられず、信仰者がイスラエルの中であざけられるということによって、「イスラエルの残りの者」が指し示されるようになる。残りの者たちこそ、旧約のメシヤの教会であり、ヘブル人への手紙の著者は、その関係が、御子とその兄弟たちにそのまま当てはまると見ているのである。したがって第三の引用は、きわめて自然に、第一、第二[引用者注、ヘブル書2・12~13における、詩篇22・22とイザヤ書8・17bのこと]に結びつくのである。/ 第三の引用は、イザ八18前半である。旧約の本文では、第二と第三の引用の句は一続きであるのに、これをわざわざ分割し、〈またさらに〉と言って、新たに導入したのはなぜであろうか。ヘブル語本文では、八18は「見よ。私と、主が私に下さった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでのしるしとなり、不思議となっている」と一つの長い文章であるが、七十人訳は、「見よ。……子たちとは」で一つの文章になっている。ヘブル人への手紙の著者は、イザヤが望みをかけた残りの者が、一つは彼の弟子たちであり、もう一つのグループは彼の子どもたちであったと理解したのであろう。八18前半が独立の文章になっていることが、彼の意図を表すのに都合が良いと判断されたものと思われる。同時代の人々がどんなに不信仰であっても、エルサレムにおける預言者イザヤの存在と彼が語ることばは神のあかしである。それだけでなく、彼の二人の子ども、シェアル・ヤシュブ(残りの者は帰って来るの意)と、マヘル・シャラル・ハシュ・バズ(略奪はすみみゃかに起こるの意)は、その象徴的な名のゆえにイスラエルに対する使信となるのである。イザヤが子どもたちにこのような意味を持った名をつけたということは、彼がこれらのことを必ず実行してくださることを確信した証拠である。/ さて[ヘブル書の]著者は、預言者とその子たちの関係が、神の御子とその子たちの間に見出されると主張する。死の苦難の中でも神にのみ信頼したキリストは、神によってその右の座に挙げられた。この事がらは、まだキリストを信じる者の間でしか認められていない。しかし、キリストの家族である信者の生活とあかしは、全世界に対して、苦難を経て全うされた救い主の栄光を現すものである。天によるキリストと地上にあるキリストの子たちの親密な関係が、この引用によってよく表わされている。キリスト者が、キリストの子たちと言われる例は、新約聖書においてここ以外にはないが、最も近い例は、ヨハ一七章のキリストの大祭司としての祈りの中に見出される。そこで主は、キリスト者のことを、くり返し「あなたがわたしに下さった者たち」と呼んでいる。」※文中の聖書は、「新改訳聖書 初版」より。安田吉三郎「ヘブル人への手紙」『新聖書注解 新約3』(いのちのことば社、1972年)、226~227ページ。
[vi] ヘブル人への手紙2・10~18:多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全な者とされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神に、ふさわしいことであったのです。
聖とする方も、聖とされる者たちも、みな一人の方から出ています。それゆえ、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずに、こう言われます。
「わたしは、あなたの御名を兄弟たちに語り告げ、
会衆の中であなたを賛美しよう。」
また、
「わたしはこの方に信頼を置く」
と言い、さらに、
「見よ。わたしと、神がわたしに下さった子たち」
と言われます。
そういうわけで、子たちがみな血と肉を持っているので、イエスもまた同じように、それらのものをお持ちになりました。それは、死の力を持つ者、すなわち、悪魔をご自分の死によって滅ぼし、
死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。
当然ながら、イエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。
したがって、神に関わる事柄について、あわれみ深い、忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪の宥めがなされたのです。
イエスは、自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。
[vii] ブライアン・ペイト氏はこう論じます。「2. キリストの生涯のパターンとしてのイザヤの生涯。この時点で、イザヤとキリストの類似性に関するグローガンの洞察を繰り返すことは有益である。「当時の人々から拒絶されながら、自分の周りに弟子たちを集めたイザヤとキリストの間には、明確な類似点があったローガンは言いている39。私は、イザヤとイエスの間には、グローガンが言及したよりもはるかに多くの類似点があると信じている(下表参照)。以下では、より重要な類似点のいくつかを詳しく説明する。
| 表1.キリストの生涯の模範としてのイザヤの生涯 | |
| イザヤ | イエス |
| 名前の意味は”ヤハウェは救い” | 名前の意味は”ヤハウェは救い”(マタイ1:21) |
| 預言者 | より良い預言者 |
| イスラエル代表 | イスラエル代表 |
| 残党を集めるリーダー | 仲間を集めるリーダー |
| ぶどう園のたとえ (イザ5:1-7) | ぶどう園のたとえ(マタイ21:33-41) |
| 神によって遣わされた (イザ6:8) | 神によって遣わされた(ヨハネ2021、第1ヨハネ4:14) |
| 怒ったが、人々は理解しなかった(イザ 6:9-10) | 人々が理解できないように、たとえで語った(マタ イ13:14-15) |
| しるしに関する(イザ7:10-14) | しるしに関する議論 (マタイ12:38-39) |
| 神を信じた(イザ8:17) | 「神を信頼した(ヘブライ2:13) |
| 人々に拒絶された(イザ28:9-10:30:9-11) | 人々に拒絶された(ヨハネ1:11) |
| 偽善的な礼拝に立ち向かった(イザ29:13) | 偽善的な礼拝に立ち向かった(マタイ15:7-9) |
| 人を「恐れるな」 (イザ37:6-7) | 人かられることを恐れるな (マタイ10:28) |
| 特定の使命のために油注がれた(イザ61:1-2) | 同じ使命を持っていた(ルカ4:17-18、722) |
| 殺された(ヘブライ11:37) | 殺された(マタイ27章) |
イザヤもイエスも人々に悔い改めるように呼びかけ(イザ1:18、マルコ1:15)、赦しを受けることができるようにした(イザ40:1-2、マルコ2:5)。二人とも、ある人々が理解できないように隠語で語った(イザ6:9-10、マタイ13:14-15)。主ヤハウェの霊がわたしの上におられるのは、ヤハウェが貧しい者に良い知らせを伝えるためにわたしに油を注がれたからである。主は、心ある者を縛り上げ、捕らわれている者に解放を、縛られている者に牢を開くことを告げ知らせるために、わたしを遣わされた。イエスが箇所を意図的に見つけて読まれたのは、それから700年後の安息日だった。今日、この聖句はあなたがたの耳に成就した」(ルカ4:21)。ここでイエスは、イザヤの言葉を自分の言葉として採用したのである。
さらに深いレベルでは、イザヤもイエスも忠実な民を象徴している。神はイザヤに(しもべを予表するものとして)「あなたはわたしのしもべ、イスラエル、わたしが栄光を受ける者」(イザ49:3)と言われた。神の民の残党の指導者として、イザヤは真のイスラエルを代表する役割を果たした。イエスは真のイスラエルであり、イエスに結ばれるすべての人は「神のイスラエル」である(ガラ6:16)。トレンバー・ロングマンとレイモンド・ディラードは、イエスがイザヤの時代のレムナントをどのように代表し、成就させたかを見事に示している。「忠実なレムナントの体現者として、(イエスは)罪のために(十字架上で)神の裁きを受け、流浪墓の中で神に見捨てられた3日間)を耐え忍び、神の約束を新たに受け継ぐ新しいイスラエルの基礎として、生への回復(復活)を経験されるのです。
イザヤが語ったとき、イザヤはその子らと弟子たちとの間の信頼を表現したのである(イザ8:16-18)。これまで見てきたように、この箇所はヘブル人への手紙の著者によって明らかにイエスに適用され、キリストとその民との連帯を強調している。イエスは、真の信者を「一つの源」を共有する兄弟として語っている(ヘブライ2:11)。イエスはまた、彼らの人間的本性を共有し、「あらゆる点で兄弟たちに似た者とされた」(ヘブライ2:17)。このことが「多くの子らを栄光に導く」(2:10)資格となったのである。その連帯はイザヤは弟子たちとともに、イエスは兄弟姉妹とともに、とF・F・ブルースは説明する。
確かに、イザヤの預言的宣教においては、来るべき王とレムナント、ヘブル人の言葉を使えば、子とその兄弟たちとの間に密接な関係がある。さらに、イザヤ自身が、イザヤ8:16で彼が語っている弟子たちの輪の中で、また、彼自身の家族の中で、当時のレムナントの胎動に意識的な企業的存在を与えるための措置を講じたと信じるに足る理由がある。
弟子たちの代表的指導者であるイエスは、苦難の道を通して弟子たちを高揚へと導く。預言者(イザヤ)は人々から迫害され、拒絶されたが、信仰の結集点となった。イエスは今、苦難を通して栄光へと導かれる新しい人類の代表的な長である」。
イエス(ヨハネ1:11)のように、イザヤは民全体から拒絶された(イザ28:9-10;30:9-11)43.そしてイエス(マタイ27)のように、イザヤは迫害され、最終的には殉教した。ユダヤの伝統によれば、マナセ王から逃げていたイザヤは、古い幹の空洞に隠れた。やがて王の部下がイザヤを見つけ、イザヤを追い出すために木を切り倒した。ヘブル人への手紙の著者は、「真っ二つにされた」人々について言及するとき、イザヤの殉教を思い浮かべているようだ(ヘブライ11:37)。イザヤとイエスの間に顕著な類似点があることを考えれば、イザヤ読んだエチオピアの宦官が、”あなたがたに尋ねますが、預言者は誰についてこのように言っているのですか。(使徒8:34)。上記の証拠に基づけば、適切な答えは”両方”だと思われる。イザヤは、自分のしたこと、言ったことが、来るべきしもべ、すなわち、イスラエルが失敗したところを成功させ、身代わりのいけにえとして苦しみを受け、終わりの時代に真のイスラエルの残党を自分の周りに集める人のパターンであることを自覚していた。(以下略)」「ヘブル2:13におけるイザヤ8:17-18の用法」WHO IS SPEAKING? THE USE OF ISAIAH 8:17–18 IN HEBREWS 2:13 AS A CASE STUDY FOR APPLYING THE SPEECH OF KEY OT FIGURES TO CHRIST by BRIAN PATE DeepLによる翻訳。
[viii] 「神の子が苦しみの果てにあのような死を遂げられたのは人間が苦しまないためではなく、人間の苦しみもまた、彼のそれに似るためであった。」ジョージ・マクドナルド、C・S・ルイス『痛みの問題』、新教出版社、ページ。