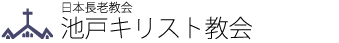2025/3/9 イザヤ書5章1~17節(1〜6)「農夫である神」
イザヤ書5章はこう始まります。
1さあ、わたしは歌おう。わが愛する者のために。そのぶどう畑についての、わが愛の歌を。…
愛の歌(ラブソング)です。聴く人々の心を捉える始まりです。そしてその「わが愛する者」が自分の葡萄畑を、掘り起こして、石を除き、良い葡萄を植えた。櫓を立てて盗人や獣が来ないよう番をして、踏み場を作って葡萄が出来たら実を絞って葡萄酒にする準備も万端。
ぶどうがなるのを心待ちにしていた。ところが、酸いぶどうができてしまった。
ガッカリな結果になった、という歌です。深い失望と徒労感を思い起こさせた上で、
3今、エルサレムの住民とユダの人よ、さあ、わたしとわがぶどう畑との間をさばけ。
と歌詞は一変します。誰か、のことではなく、「わたし(神)」と神の葡萄畑の話になります。葡萄畑を手塩にかけて育て、収穫を心待ちにしていたのに、出来たのは酸い葡萄だった、というのは、他でもない、主ご自身の思いでした。そして、4~6節で主は、そのぶどう畑を取り壊して、荒れるままにする[i]、と告げます[ii]。そして、7節でそのぶどう畑の正体が告げられるのです。
7万軍の主のぶどう畑はイスラエルの家。ユダの人は、主が喜んで植えたもの。主は公正を望まれた。しかし見よ、流血。正義を望まれた。しかし見よ、悲鳴。
その「葡萄畑」とはイスラエルの民のことでした。イザヤの時代、イスラエルの民は、主の目には「酸い葡萄」のようでした。主なる神が、子どものいないアブラハム夫妻から始めさせ、エジプトで奴隷にされていたその子孫を救い出して、カナンの地に住まわせたのは、ご自分の葡萄畑のように育てるつもりだったからでした。しかし、彼らは直ぐに主の恵みを忘れて、主以外のものに惹かれて、味気ない歩みに走ることを繰り返してきました。イザヤが語った紀元前8世紀もそんな時代で、民族は北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂して二百年が経ち、北のイスラエルは間もなく南からのアッシリア侵略で陥落します。しかし南のユダにも他人事ではありません。この五章では、イスラエルという言い方を繰り返して、北も南も含めた全体が等しく主の前に「酸い(苦い、不味い、出来の悪い)葡萄」となっている問題が語られています。
葡萄が好きな方もそうでない方もいるでしょう。どちらでも大して困らないぐらい、私たちの生活に身近ではありません。それでも新しい品種が出回って吃驚(びっくり)します。聖書の地域、また今から二千年以上前、今ほど大きく艶々(つやつや)した糖度の高い実ではないけれど、数少ない食糧の中で生活に欠かせない葡萄。高級フルーツというよりもっと実も素朴な、日常の必需品でした[iii]。この5章に「ぶどう」という言葉は12回出て来ますが、「良い葡萄」「ぶどう」「酸い葡萄」全部違う言葉で、ここだけでも6種類、全体だと12もの違う言葉が出て来ます[iv]。それだけ、イスラエルの生活に葡萄は大きな存在だったのです。そういう大事な物を引き合いに、主がその民をわたしの葡萄畑と呼ばれる。ここに出てくる厳しい言葉以上に、抑(そもそも)主がその民を葡萄畑だと言われる言葉が驚きです。そして、その実として「公正を望まれた…正義を望まれた」と言うのも、特別な正しい生き方、潔癖で高潔な生き方を期待されている、というよりも、極々日常的なこと、主からの恵みを頂いて養われながら生きること――シャインマスカットか巨峰のような実を実らせなくても、大きな花を咲かせなくても、主から受けた幸いにいつも立ち戻りつつ歩めばいい。その結果、実る生き方は、どんなに小さくても十分なはずです。
この主から受けた幸いがここで「公正…正義」です。正義とは神また人との関係が正しくあることです[v]。「公正」とはその具体的な適応のことです。正義を公に実行するのが公正です。16節の「さばき」と訳されているのも同じ言葉です[vi]。実際の出来事が正しくあるようにすること、これが公正です。しかしここで指摘されるのは、公正と正義を望んだのに、代わりに流血と悲鳴、と言われます[vii]。何があったのでしょうか。具体的には、8節以下、11、18、20、21、22節と6回「わざわいだ」と重ねて指摘されます。
8わざわいだ。家に家を連ね、畑に畑を隣り合わせる者たち。あなたがたは場所を残さず、自分たちだけこの地に住もうとしている。」
家の増築と畑の拡張、経済的な繁栄、暮らし向きの高級志向[viii]。家を二つ、三つと増やせる人は増やし、そんな余力のない人は住んでいる処からも追い出されるアンバランスです。
9私の耳に万軍の主は告げられた。「必ず、多くの家は荒れすたれ、大きな美しい家々も住む者がいなくなる。10十ツェメドのぶどう畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。
容赦なく手に入れた家は廃墟になり、住民は追い出され、増やしに増やした畑の収穫もなしのつぶてしか生まなくなる。家も畑も、暮らしも事業も、究極的な頼みとはならないし、それらを手に入れるために流血や悲鳴も厭わなかった報いが降りかかります。また、
11わざわいだ。朝早くから強い酒を追い求め、夜が更けるまで、ぶどう酒に身を委ねる者たち。12彼らの酒宴には竪琴と琴、タンバリンと笛とぶどう酒がある。…
朝から酒浸り、楽器で音楽を演奏させて、毎日どんちゃん騒ぎ。しかし何よりの問題は
…彼らは主のなさることに目を留めず、御手のわざを見もしない[ix]。
だから13節以下、その浮かれた生活が終わり、飢え渇く日が来ることが告げられます[x]。どちらも、自分たちの暮らしや事業、パーティ三昧な生活だけに浮かれて、貧困、低賃金の労働、福祉は疎かにしていた。その暮らしは、自分たちの目には、華やかで成功して、勝ち組と見えたつもりだったでしょう。しかし、主は良い葡萄のはずが酸い葡萄を実らせた、残念で、滅びに突進するような、無価値な生き方だと強く言うのです。一花咲かせたつもりでも、肝心な実が酸っぱいだけ、でした。
16しかし、万軍の主はさばきによって高くなり、聖なる神は正義によって、自ら聖なることを示される。
人間の舞い上がった贅沢暮らしのバブルは弾けますが、主は高くされます。それは、裁きと正義によってです。先にも言いましたように、この「さばき」は7節の「公正」と同じ語で、7節で
「公正…正義を望まれた」
と対応するようにここで万軍の主は「公正(さばき)と正義によって」高くされ、自ら聖なることを示す、と言われるのです。人が思い上がりや、他者を押しのけて自分を高くするのと違い、主は、人との関係を正しい関係になさいます。それが、
17子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食を取る。
という絵でしょう。小さな動物や、今まで瘦せ細っていた獣が、荒れ果てたあの葡萄畑の跡地で黙々と草を食べている、という光景が描かれます。これが、主のさばき(公正)、正義であり、主が聖なることの証しです。神を侮り、同じ人を踏みつける人間の傲慢が終わり、虐げられていた人、飢えた人が必要を与えられ、安心、慰め、癒しを与えられる、という公正です。
他ならぬイスラエル人こそ、その主の正義に与って、奴隷生活から救い出された人々です。その後の歩みでも、何度も何度も、この主の恵み深い御手のみわざを見て来ました。その恵みが良い土台、豊かな栄養となって、イスラエルの民のあり方、社会の骨組みとして実を結ぶと期待されたのです。やがて、主イエスが来られた時も、イザヤが繰り返すぶどうの譬えを使い、
ヨハネ15・5わたしはぶどうの木、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。…
と言った時もそうでした。
わたしに留まりなさい。わたしの愛に留まりなさい。
でした。私たちが弱い時、貧しい時、何も出来ない時、主は私たちを招き、わたしはぶどうの木、あなたがたは枝です、と言われる。決して、正義の実を結べ、美しい花を咲かせよ、ではない。枝になりなさい、でさえなく、あなたがたは枝です、と言われる。主の民は葡萄畑だと言われます。多くの豪邸も華やかな宴会も酸っぱくて苦く味気ないと思わせるほどの、主の恵みを頂いて、私が枝となって結ばれる、尊い実がある。それも一つならず豊かに、私を通してなされる主の実りがある。そんな信じがたい主の思いが、ここにあります。だから「愛の歌」なのです。
「造り主なる主よ。世界を造り、私たちを、葡萄を、命を作り、育まれる御名を讃美します。厳しい言葉の奥には、私たちを尊んでやまない、聖なる愛、正義と公正を下さる恵みがあることを聞きました。見えるもの、ひと時の楽しみよりも喜ばしい実を結ばせてください。まして、誰かを踏みつけることのないよう、声なき悲鳴を聞く耳を忘れることのありませんよう。」
[i] といっても、怒りに任せて滅茶滅茶にぶっ壊す、のではありません。周りを囲む垣を取り払い、放っておく。守りがなくなるので、人や動物が踏みつけるままになり、雑草や茨が生え放題になる。雨も降らせなくするだけで、雷や洪水で破壊するわけではないのです。人間である農夫は、雨を降らせたり降らせなかったりは出来ないので、その違いはありますが、農夫が畑の出来が悪いのを見て、そこを畑にするのを止めるのは、畑や木に八つ当たりをすることではなくて、手間をかけるのを止めるだけです。そうすれば当然、荒れ放題になるでしょう。そのように、主はご自分の畑から手を引く、と言うのです。
[ii] 4~6節:わがぶどう畑になすべきことで、何かわたしがしなかったことがあるか。なぜ、ぶどうがなるのを心待ちにしていたのに、酸いぶどうができたのか。5さあ、今度はわたしがあなたがたに知らせよう。わたしが、わがぶどう畑に対してすることを。わたしはその垣を取り払い、荒れすたれるに任せ、その石垣を崩して、踏みつけられるままにする。6わたしはこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨やおどろが生い茂る。わたしは雨雲に命じて、この上に雨を降らせないようにする。」
[iii] ブドウ園と農夫 Bridge for peace
[iv] イザヤ書における「ぶどう・ぶどう園 」כֶּרֶם 他
[vi] イザヤ書における「公正・さばき」מִשְׁפָּטミシュパート
[vii] 7節には語呂合わせの言葉遊びがあります。「公正ミシュパートを望まれた。しかし見よ、流血ミスパーハ。正義ツェダカーを望まれた。しかし見よ、悲鳴ツェアカー。」
[viii] 今とは違い、聖書の律法では貧富の格差を少なくするため、土地はその人の家のもの、金策に困って売ったとしても最長で五十年したら返さなければならない、と規定されていました。しかし、ここには土地の所有・私物化が進み、貧者や弱者に場所が残されていない現状があります。ミカ2・2(彼らは畑を欲しがって、これをかすめ、家々を取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。)、アモス2・6〜8(主はこう言われる。「イスラエルの三つの背き、四つの背きのゆえに、わたしは彼らを顧みない。彼らが金と引き換えに正しい者を売り、履き物一足のために貧しい者を売ったからだ。彼らは、弱い者の頭を地のちりに踏みつけ、貧しい者の道を曲げている。子とその父が同じ女のもとに通って、わたしの聖なる名を汚している。彼らは、すべての祭壇のそばで、質に取った衣服の上に横たわり、罰金で取り立てたぶどう酒を自分たちの神の宮で飲んでいる。」)土地投機が広がり、土地を譲ってはならない律法(レビ25章、民数記27・1〜11)が無視されていた。
[ix] 楽器や音楽やお酒さえ、それ自体が悪ではありませんし、楽しむことが罪、楽しまなければ罪を犯していない、なんてことではありません。ただ、宴会や享楽に浮かれ騒ぐことが、主のなさることに目を向けないことに繋がりやすいのですし、それが常態化していたのでしょう。8節からの流れを考えるなら、家に家を連ね、畑に畑を増すほどの有力者だからこそ、朝からどんちゃん騒ぎをし、パーティ三昧の生活をすることも出来た。そして、そんな暮らしなど手に届かない、巻き上げられた側の人々の、かつかつの生活も、主も見ないことに慣れきっていた。
[x] 13それゆえ、私の民は知識がないために捕らえ移される。その貴族たちは飢えた者となり、その民衆は渇きで干からびる。14それゆえ、よみは喉を広げ、果てしなく口を開ける。エルサレムの威光も、騒音も、どよめきも、そこでの歓声も、よみに落ち込む。15こうして人間はかがめられ、人は低くされる。高ぶる者の目も低くされる。