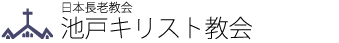2025/3/2 イザヤ書4章1~6節「麗しいものの創造」 招詞:マタイの福音書11章28〜30節
イザヤ書4章、たった6節。1~3章と比べると4分の1か5分の1です。イザヤ書全体でも最も短い章です。この4章が、2章からの言葉をガッチリと受け止める章なのでした。
2章の初めには、終わりの日に、主の家の山が山々の頂に立ち、すべての民族が、主なる神を礼拝し、そのさばきを求めて来る、すべての争いが終わり、剣が農具に打ち直される、という光景が描かれました。その後、現状の争い、高ぶり、暴力、虚飾の罪への断罪の言葉が続き、すべての悪が終わらされることが激しい表現で描かれてきました。その最後、4章1節の後に、2~6節が一転して、語られます。断罪や荒廃ではなく、麗しさ、栄光、誇り、輝きの言葉です。
2その日、主の若枝は麗しいものとなり、栄光となる。地の果実はイスラエルの逃れの者にとって、誇りとなり、輝きとなる。
こんな麗しい言葉が溢れます。「若枝」という言葉は、後に11章1節で神が遣わされる王を指しますが、ここでもその方を指す、とも読めますし、まだそこまで読み込めないと取る人もいます[i]。いずれにしても、若枝、枯れたように思えた木から芽を出す枝、倒された切り株の脇から生え出て来たヒコバエは、死からの再生、終わったように見えたものからの新たな始まりを思わせます。「地の果実」も、戦争で荒廃しきって食糧などなくなると思えたところに、食べる実がなって喜ばれる、ということです。そして「逃れの者にとって」とあるのもイザヤ書で繰り返される大事なテーマです。3節も、
3シオンに残された者、エルサレムに残った者は、聖なる者と呼ばれるようになる。みなエルサレムに生きる者として書き記されている。
これも、主なる神の裁きに遭わなかった者、とも読めますが、イザヤ書全体を見ていくと、裁きを受けて、他国に捕らえられていった者たちの中から、帰って来る者がいて、それが「逃れの者」です。「残された者」というのがイザヤ書の大切なメッセージの一つです[ii]。神は人間の罪の現実をきっちり裁く。でもその裁きは罰して滅ぼすためではなくて、その厳しい裁きを経て、人は聖なる者とされる。生きる者として書き記されるようになる――。裁きかいのちか、ではなく、裁きを通してのいのち、です。
このことは、次の4節でも明らかになります。
主が、さばきの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い落とし、エルサレムの血をその町の中から洗い流すとき、
3章16節で「シオンの娘たちは高ぶり」とありました。高級な飾りを追い求めて、貧者から奪い取るばかりで、顧みることのない、高慢な醜さが非難されました。それがこの
シオンの娘たちの汚れを洗い落とし、
でしょう。そして
エルサレムの血を…洗い流す
は、特に3章前半で非難された、指導者・為政者たちの
貧しい者たちからかすめ…砕き、貧しい者の顔を臼ですりつぶす…
とあった不正な支配への裁きでしょう[iii]。それらが残らず洗い落とされるのは、洗い流した後に、主が更に麗しいこと、栄光、誇り、輝きを与えてくださるからです。
4…洗い流すとき、5主は、シオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼には雲を、夜には煙と燃え立つ火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、6その仮庵は昼に暑さを避ける陰となり、嵐と雨から逃れる避け所、また隠れ家となる。
この昼には雲、夜には煙と火、といえば、かつてエジプトの奴隷生活から解放されたイスラエル人が荒野を四十年旅した間、昼には雲の柱、夜には火の柱があったことを思い出します[iv]。それは、第一には主ご自身がともにいる、という臨在であり、それゆえに、昼は日照りの暑さに屋根を指す雲となり、夜には暗闇を照らす燃える灯でした。あの雲と火の柱を彷彿とさせることを主は、汚れと血を洗い流した後に「創造する」と言われるのです。
この「創造する」という言葉は、聖書の冒頭、創世記1章1節の
はじめに神が天と地を創造された。
で出て来たあの言葉です。この言葉が聖書で使われるのは、いつも神が主語です。人間も物を作ったり創造的になることに喜びを覚えたりするものです。それは、私たちを創造した神が創造者なる神だからです。そして、創造者なる神と、その神に造られた人間のモノ作りには、決定的な違いもあります。ですから、この「創造」という言葉は神だけに使われます。そして、このイザヤ書4章5節で
昼には雲を、夜には煙と…火の輝きを創造される
という時にはその特別な「創造」[v]が使われているのです。因みに、イザヤ書にはこの創造という言葉は21回使われますが、ほとんどが40章以降に集中していて、1章から39章までの間に唯一登場するのが、今日の4章5節です。40章以降ではこの天地(全世界)を創造した神は、その力で世界を贖い(買い取って)癒し、回復させ、祝福してくださると繰り返します。人間の力や想像力が遥かに及ばない新しい創造をすることが描かれます。その後半の怒涛の展開を垣間見させるのが、ここで一度きり出て来る「創造」だと言えるでしょう。
それは高ぶって振る舞い、形式的な礼拝をしながら、人を卑しめていた人々を、その汚れから洗い清めて、聖なる者に造り変えてくださる創造です。
見てくれをよくすることばかりにかまけた結果、すべてを失って外見さえかさぶたや悪臭や焼き印で恥辱の底に突き落とされると言われた人々が、そこに住まい、栄光を与えられ、それを主が覆って守ってくださる、という全く新しい創造です[vi]。
貧しい者、掠め奪われて、生きながら殺されているような人々、守りや安心できる家のない人々も、暑さを避ける仮庵、嵐と雨から逃れる避け所、隠れ家が与えられるという創造です。
この世界で蔑まれた人から、その人々を蔑み踏みつけてきた報いを受けた人々まで、そしてその間にいるすべての人々を、主が汚れた虚栄からすっかり洗い清めてくださる時、主はそのボロボロな人々のために、人の予想が足元にも及ばない創造をなさる。その汚れた罪を容赦なく断罪した主は、その人々のために、惜しみなく麗しいものを備えてくださり、それがどんな暑い日差しや嵐や雨、他者の非難や悪魔の攻撃からも奪われないよう覆う。この神である主だけが、人を高ぶりから救い出し、命に生きる者としてくださるのです。[vii]
この主の深い憐みを味わうとき、主イエスの言葉が迫ってきます。今日の招詞、マタイ11章28~30節です。
すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。わたしは心が柔和でへりくださっているから、あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから学びなさい。そうすれば、たましいに安らぎを得ます。わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからです。
こうイエスは招きましたが、実際、罪人や娼婦、下層民や無学な弟子たちが集まった時、当時の宗教家や善人たちは嘲笑い、文句を言ったのです。そんな集まりこそ、イザヤが預言し、イエスが実現した創造でした。
イザヤ書の2章から4章が一纏まりです。2章の最初の歌で始まり、罪の批判とその厳しい結末を語りながら、結びの4章はこんな将来像を歌って締め括る。この先も、次の段落を結ぶ12章でも、その先の結びとなる35章でも「帰還の歌」を歌うことで繰り返されます[viii]。そしてイザヤ書全体が、40章以下、創造主なる神の力強い言葉で、希望を歌っていきます。それは、裁かれるべき罪を持つ者たちが、集められ、喜んで共に生きる姿です。善人や天使のような装いをした聖人の集まりではなく、そんな見せかけも高ぶりも冷たく醜い思いもすっかり洗い流された、装いのない素の私たちがここに集まっているのは、主の新しい創造の始まりなのです。
「創造主なる神」という告白は勿論、宇宙も地球も、偶然や自然に出来たのでなく、唯一の神が手塩にかけて創造した、という告白です。しかしそれにも勝って、イザヤ書が語るのは、その神が、今にもこれからにも、罪で壊れた世界をも贖って、新しいことを創造する、という告白です。創造主なる神を告白することは、この世界の破れや不信仰を批判して、断罪するのでなく、どの人も神の被造物であり、神はこの壊れた世界を癒し、壊れた人を癒すことが出来る。理解を超えたことを神はなさるし、イエスはそれを始めてくださった、という告白です。
「創造主なる神。世界が聖なる火を潜って、朽ちる全てが焼け落ち、流れ消えた後にも、雲や火の輝きが守り、暑さや嵐からも守られる仮庵がある、こんな将来があることを感謝します。今この時も、主ご自身に守られ導かれてある恵みに立ち戻ります。疲れた心が憩い、重荷を下ろします。そして、破れ傷ついたこの世界を、主の約束の中に包んで、深く癒してください」
[i] 「伝統的に、タルグムに始まり、主の枝はメシアを指すと解釈されてきた(他の箇所でも同様:エレミヤ 23:5、33:15、ゼカリヤ 3:8、6:12)。しかし、ほとんどすべての現代の注釈者は、この解釈に異議を唱えている(カルヴァンも同様)。彼らの主な証拠は、平行表現である地の果実には明らかにメシアとのつながりがないということである。一方、「果実」をより文字通りの意味でとるなら、「枝」は大きな困難なしにそれと平行することができる(NEB「主が育てた植物」を参照)。この見解では、主は、裁きの荒廃の後、比喩的または文字通りに、地の新たな実りを約束していることになる。
このような解釈は、確かに他の箇所のイザヤの記述や他の預言者の記述と一致しているが、モークラインが指摘するように、イザヤがなぜこの曖昧な言葉を、本来は非常に単純な記述であるはずの記述に使用したのかという疑問が残る。タルグムの証言も簡単には否定できない。明らかにゼカリヤやおそらくエレミヤの影響を受けていますが、それでも非常に初期の理解である。10
枝のメシア的解釈を受け入れる人々は、地の果実にメシア的つながりを持たせなければならないと感じてきました。デリッチ、そして最近ではヤングは、主の枝がキリストの神性を反映するのに対し、地の果実はキリストの人間性を反映するものにしようとしました。 11 しかし、バーンズが詳細に示したように、この立場は学者の創意工夫に頼りすぎています。枝がメシアであるなら、イスラエルの真の永続的な産物は神の賜物であり、イスラエル自身の豊穣と力の結果ではないということがポイントのようです。 12 神は、イスラエルが自らのために作り出した名誉 (tip’eret) (3:18) を取り去り、彼女に新たな名誉と高揚の源を与えます。イスラエル自身は新芽ではなく、神の恵みによって彼女から生まれたものです。神が彼女に栄光を与えるとき、彼女はその真の偉大さを知るでしょう。それは、彼女がその栄光を自ら生み出そうとしたときには得られなかった偉大さです。メシアは神の栄光の仲介者であるという考えは、新約聖書の中で目立つものです(ルカ 2:32; 9:26, 32; ヨハネ 1:14; 2:11; 11:4; 17:5, 22, 24; 1 コリント 2:8; 2 コリント 4:6; コロサイ 1:27; ヘブル 1:3)。」 Oswald、Google翻訳による。
[ii] 残りのもの פְּלֵיטָהぺレター 5回 4・2、10・20(その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れの者は、もう二度と自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に真実をもって頼る。)、15・9(ああ、ディモンの水は血で満ちる。わたしはさらに、ディモンにわざわいをもたらす。モアブの逃れた者、その土地に残った者に、一頭の獅子を。)、37・31~32(ユダの家の中の逃れの者、残された者は、舌に根を張り、上に実を結ぶ。32エルサレムから残りの者が、シオンの山から、逃れの者が出て来るからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。」) < פָּלִיטペリート 45・20、66・19
[iii] 「ここでの「主(アドナーイ)」の行為は直接的には、「男たち」(3:1-15)と「女たち」(3:16-4:1)に向けられたものである。敢えて言えば「シオンの娘たちの汚れ」とは女たちの高慢による堕落と恥(17、24節)、「エルサレムの血」とは「長老たちと指導者」による貧しい者たちへの過酷な抑圧(14-15節)を指していると言える。そして、それらはヤハウェによって「洗い」「清め」られるのである。」 大島、VTJ、81ページ
[iv] 昼は雲、夜は火 出エジプト13・21-22(主は、昼は、途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は、彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んで行くためであった。22昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。)。また、同19・18には「シナイ山は全山が煙っていた。主が火の中にあって、山の上に降りて来られたからである。煙は、かまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。」も参照。
[v] 創造される בָּרָאバーラ― 21回。39章までではここのみ。あとは、40章以下に二十回出て来ます。イザヤ書における「創造する」 בָּרָא バラーの用例
[vi] 「おおい」は詩篇19・5やヨエル2・16における「婚姻の部屋」であって、それが花婿と花嫁が愛と一致のうちにともに来たる際にプライバシーを守るようになる。「栄光」はメシヤとその花嫁としての民を愛のうちに結合させ、またシオンの聖とされた民を彼らをおおう神の臨在のしるしのもとで完全な愛のうちに結びつけるのである。 モティア、75ページ
[vii] 昔の幕屋の時代、主はその民とともにおられた(出エジプト29・43-46)。しかし、主の幕屋は彼らには閉ざされていた(出エジプト40・34-35)。もはやそうではない! 彼らをおおう神の栄光の雲、そして婚姻のおおいが「避ける陰……避け所と隠れ家」となる。ことばの重複は意図的なもので、「考えられ得るすべての守り」という思想を表している。同様に「暑さ」と「あらし」、「昼」と「夜」という対比は「すべての環境と脅かしにおいて」、また「どんなときも」ということを暗示している。 モティア、75ページ
[viii] イザヤ書35・10:主に贖われた者たちは帰って来る。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びを戴く。楽しみと喜びがついて来て、悲しみと嘆きは逃げ去る。
全く同じ言葉が、51・11にあります。