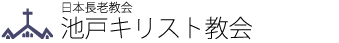2025/2/9 イザヤ書2章12~22節(12〜18節)「高ぶりは終わり」
イザヤ書が書かれた時代、紀元前8世紀後半は、神殿での礼拝は形式的に続けられていたものの、かえってそのことに慢心して、ユダヤの国は世俗化していた時代です。6~9節にその現状が訴えられています。呪いごとや、経済力、軍事力に頼み、自分たちの手になるものが偶像になって拝まれていました。そうした思い上がり、バブルは弾けると語ったのが、続く10~11節であり、その続きの今日の箇所です。12~16節は「すべての高ぶりの終わり」を歌います。この歌を挟んで、17節は11節とほぼ同じ言葉を繰り返します。
その日には、人間の高ぶりはかがめられ、人々の思い上がりは低くされ、主おひとりだけが高く上げられる。[i]
また19~21節も、10節で
岩の間に入り、土の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を、その威光の輝きを避けて。
とあったことを膨らませています。10節と19~21節、11節と17節、その真ん中に12~16節。こんなサンドイッチの作りからしても、12~16節の「すべての高ぶりの終わり」歌の大切さがわかりますし、この箇所全体のテーマが「高ぶりの終わり」です。
12まことに、万軍の主の日は、すべてのおごり高ぶる者、すべての誇る者の上にあり、これを低くする。
この「主の日」は歴史の終わり、というより、歴史の途中で主が歴史に介入する日でしょう。世の終わりを待つことなく、人間の高ぶりは折々に低くされるのです。銀や金で満ち、天井知らずの経済力――馬や戦車、どんな技術や優れた武器も、主の訪れには太刀打ちできません。
これを上書きするのが13~16節です。
高くそびえるレバノンのすべての杉の木
とは、イスラエル北方のレバノン山脈には、立派な最上質の杉材となるレバノン杉がありました[ii]。ヨルダン川東のバシャンには一級品の「樫の木」がありました[iii]。それらは人間が高く立派な建物を建てる材料となり、当然その建築には、多くの下層民の奴隷化、不法な重労働が伴ったでしょう。その汗と血の大建築の上で、富裕層が驕り高ぶっている、という姿が浮かびます。
続く14節の
高い山々と…そびえる峰々
も、山が神とされて拝まれたり、山に神殿を建てたり、宗教的な意味合いを持たされました。15節の
そそり立つやぐら…堅固な城壁
は人工の建造物で、これも大きく高く造ったからと誇るものでしょう。16節の
タルシシュのすべての船
は遥か西、スペインの街で、造船業で知られます[iv]。商品を山と積んで海を突き進む輝かしさは
すべての慕わしい船
とも呼ばれたのでしょう。11節の「思い上がり」[v]は「高く聳える」「高い」[vi]と通じています。杉も樫も、山々も城壁も大型商船も、どれもそれ自体が罪なのではありません。ただ、その高さ、大きさ、見栄えには、神を忘れた人間の高ぶりに通じるのです。日本語でも「高ぶり」は「高いふりをする、尊大な態度を取る」という意味と「気分・感情などが高まる、興奮状態になる」の二つの意味があります。確かに、高いものを身に着けて偉そうにすることは、感覚的にものぼせ上って陶酔的になるものでしょう。しかしそんなものは勘違いに過ぎません。だから、それらの上に、万軍の主の日が来るのです。
17その日には、人間の高ぶりはかがめられ、人々の思い上がりは低くされ、主おひとりだけが高く上げられる。18偽りの神々はことごとく消え失せる。
聳える木も山々も、人間の手による大都市、超大型建造物も、すべて神ではなかったと、消え失せる日が来るのです。神が消え失せる、という事自体、矛盾です。なんでもなかったという証拠です。そして、主なる神おひとりだけが高く上げられるのです。
19主が立ち上がり、地を脅かすとき、人々は主の恐るべき御顔を、その威光の輝きを避けて、岩の洞穴や土の中に入る。20その日、人は、自分が拝むために造った銀の偽りの神々と金の偽りの神々を、もぐらやこうもりに投げやる。
注意してください。ここにあるのは、主が立ち上がる時、人々が今まで拝んでいたものを何一つ残さず、岩や地面に隠れようとする様子です。神さえ現れなければ、城壁やタルシシュ船はそれ自体では立派なのに、圧倒的な神が現れたせいで人々が逃げる、という所謂いわゆる「世紀末」ではありません。主が現れる時、人間が造った偽りの神々、銀や金、財力や知力や権力を凝らして作ったどんなものも、神でも何でもないことに気づくのです。城壁や船、高速艇やシェルターを造っていても、主が立ち上がるのを見たら、人は目もくれず隠れる。まだ持っている神々やお守りがあっても、洞窟で出会った蝙蝠こうもりや土の中の土竜もぐらに投げ与える[vii]。本当に自分の作ったものなど、何の頼りにもならないと分かるのです[viii]。
「偽りの神々」は神でも何でもなかったと必ずバレます。でもこれが最後で、この人々は怯えて残念な終わりを迎えると予言したいのではありません。本当の将来は2章の最初、2~4節が歌った、大きな回復です。恵みによる祝福と喜びの始まりです。その祝福に与るためにこそ、高いものを作って拝み、様々な歪みを生み出す高ぶりは、すっかり投げ捨てる必要があります。
この20~21節はヨハネ黙示録6章で引用されます。
地の王たち、高官たち、千人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に身を隠した。[ix]
しかしそれに続く7章は神の前に無数の大群衆が、白い衣をまとい、礼拝している光景です。
彼らは大声で叫んだ。「救いは、御座に着いておられる私たちの神と、子羊にある。」
と叫ぶのです。子羊とは神の子イエスのことです。神は人々を圧倒する獅子や神々しい王の姿でなく、柔和で平和、そして自らを犠牲にした子羊の姿で現れ、崇められるのです。その黙示録7章にもイザヤ書の言葉が鏤ちりばめられ、人生の多くの艱難を経て、主がその民を守り、慰め、導いて来られたことが歌うのです[x]。その神を褒めたたえるために、その礼拝に先立って、あらゆる偽りの礼拝から、高ぶりが片付けられる必要があります。だから、こう結びます。
22人間に頼るな[xi]、鼻で息をする者に。そんな者に、何の値打ちがあるか。
人間に値打ちがない、ではありません。神に代わって頼りとする値打ちはないのです。「鼻で息をする」という言葉は、創世記2・7で
神である主は、その大地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。
を踏まえています[xii]。人間は、神によっていのちを与えられ、息をしている存在です。その造られた人間が、造り主なる神を拝まず、自分が造ったもので思い上がる――そんな勘違いが強く否定されるのです。
鼻で息をしてみてください。吸って、吐いて。この息を下さり、私を生かし、万物を創造し、支えて、治めるお方こそ、私たちが崇めるべき唯一のいと高き神です。神が人間の高ぶりを、虚しいふりだと気づかせ終わらせてくださるのも、神の恵み深い愛です。この息を下さった神が、決して私たちを「何の値打ち」もないとは考えていません[xiii]。生かされている存在に過ぎないという意味では、神を忘れるなら、何の値打ちもありません。しかし、その神に生かされている存在という意味では、限りない値打ちがあるのです。イザヤは主のこの言葉を語ります。
わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。(43・4)
この主が現れる時、私たちがこの主と出会う時が、高ぶりと偶像崇拝が終わる時です。見せかけや陶酔でなく、本当に高い方に出会うまでは、人間の高ぶりは砕かれることがありません[xiv]。また主は、偶像を壊したり人々を脅したりもせず、ただ立ち上がるだけです。主の本当の栄光を知る時、人々は神のように誇って来たすべてを捨て、偶像を投げ与えるのです[xv]。力の差が圧倒的、という比較の問題ではありません。私の息さえ、この神からの業です。そして、自分だけではありません。すべての人は、この神のいのちと尊い値を与えられている存在です。そこに人間が造った上下や卑賤などは偽りに過ぎません。
「ただひとり高くいます主よ。杉や樫の木も、山々や大宇宙も、すべての高きものはあなたの御手のわざ、永遠の栄光の貧しい影です。すべての高ぶりはあなたが現れるだけで、恥じ入ります。私たちのひと息ひと息が、あなたを証ししています。生かされている恵みを味わい、思い上がりを悔い改め、あらゆる偶像崇拝を慈しみ深く、最善の形で砕いてください。今日が、主の日でありますように。私たちの生涯の毎日を、主の日としてくださいますように。」
[i] 11節は「その日には、人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主おひとりだけが高く上げられる。」で、三か所ほどの違いがあります。
[ii] ソロモンは、レバノン杉の事を歌い(列王記第一4・33:彼は、レバノンにある杉の木から、石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣、鳥、這うもの、そして魚についても語った。)、エルサレム神殿と王宮をレバノン杉で造りました(同5・6:どうか、私のために、レバノンから杉を切り出すように命じてください。私の家来たちも、あなたの家来たちと一緒に働きます。私はあなたの家来たちに、あなたが言われるとおりの賃金を払います。ご存じのように、私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいませんから。」;5・14:ソロモンは、彼らを一か月交代で一万人ずつレバノンに送った。一か月はレバノンに、二か月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。;7・2:彼は「レバノンの森の宮殿」を建てた。その長さは百キュビト、幅は五十キュビト、高さは三十キュビトで、それは四列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の梁があった。)。また、列王記第二14・9(イスラエルの王ヨアシュは、ユダの王アマツヤに人を遣わして言った。「レバノンのあざみが、レバノンの杉に人を遣わして、『あなたの娘を私の息子の妻にくれないか』と言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのあざみを踏みにじった。」、19・23(おまえは使者たちを通して、主をそしって言った。「多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深くへ上って行った。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、その果ての高地、木の茂った園にまで入って行った。)、詩篇92・12(正しい者は なつめ椰子の木のように萌え出で レバノンの杉のように育ちます。)、104・16(主の木々は満ち足りています。 主が植えられたレバノンの杉の木も。)、雅歌3・9(ソロモン王は、レバノンの木で自分のために駕籠を作った。)なども参照。
[iii] エゼキエル書27・6(バシャンの樫の木でおまえの櫂を作り、キティムの島々の檜に象牙をはめ込んで、おまえの甲板を作った。)、ゼカリヤ書11・2(もみの木よ、泣き叫べ。杉の木は倒れ、見事な木々が荒らされたから。バシャンの樫の木よ、泣き叫べ。深い森が倒れたから。)
[iv] 大きなタルシシュ製の商船が高価な品々を運んでいた様子は、イザヤ書の23章で繰り返され、エゼキエル書27章にも描かれています。
[v] 思い上がりרוּםルーム(名詞):2・11、17、10・12(主はシオンの山、エルサレムで、ご自分のすべてのわざを成し遂げるとき、アッシリアの王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。)
[vi] 高くするרוּםルーム(動詞):25回 1・2、2・12~14(まことに、万軍の主の日は、すべてのおごり高ぶる者、すべての誇る者の上にあり、これを低くする。13またそれは、高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべての樫の木、14すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、)、6・1(ウジヤ王が死んだ年に、私は、高く上げられた御座に着いておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、)、10・15(斧は、それを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか。のこぎりは、それをひく人に向かっておごることができるだろうか。それは、むちが、それを振り上げる人を動かし、杖が、木ではない人間を持ち上げるようなものではないか。)、33(見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払われる。丈の高いものは切り倒され、そびえたものは低くなる。)、13・2、14・13、23・4、25・1、26・11、30・18、33・10(「今、わたしは立ち上がる。──主は言われる──今、わたしは自らを高く上げ、今、わたしは自らを高める。)、37・23(おまえはだれをそしり、だれをののしったのか。だれに向かって声をあげ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる者に対してだ。)、40・9(シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声をあげよ。声をあげよ。恐れるな。ユダの町々に言え。「見よ、あなたがたの神を。」)、49・11(わたしは、わたしの山々をすべて道とし、わたしの大路を高くする。)、22、52・13(見よ、わたしのしもべは栄える。彼は高められて上げられ、きわめて高くなる。)、57・14~15(主は言われる――盛り上げよ。土を盛り上げて、道を整えよ。わたしの民の道から、つまずきを取り除け。15 いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方が、こう仰せられる。「わたしは、高く聖なる所に住み、砕かれた人、へりくだった人とともに住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。)、58・1、62・10
[vii] 投げやる・投げ捨てるシャーラク:2・20(その日、人は、自分が拝むために造った銀の偽りの神々と金の偽りの神々を、もぐらや、こうもりに投げやる。)、14・19(しかしおまえは、忌み嫌われる枝のように、墓の外に投げ捨てられる。剣で刺し殺された者たちで、おまえはおおわれ、屍のように、墓穴に下る者たちに踏みつけられる。)、19・8(漁師たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者もみな嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。)、34:3 彼らの殺された者は投げ捨てられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。)、38・17(ああ、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。あなたは私のたましいを慕い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪を、あなたのうしろに投げやられました。)
[viii] これは、イザヤ書に展開していく描写。例として、30・22(あなたは、銀をかぶせた刻んだ像と、金をかぶせた鋳物の像を汚れたものと見なし、不浄の物としてそれをまき散らし、これに「出て行け」と言う。)、31・7(その日、イスラエルの子らは、それぞれ銀の偽りの神々や、金の偽りの神々を退ける。それらは、あなたがたが自分の手で自分のために造ったもので、そのことは罪過となっている。)、など。また、偶像の無力さ、矛盾については、42・17、44・9~20、45・16、46・6~7、などに展開していく。
[ix] ヨハネの黙示録6・12~17:また私は見た。子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。太陽は毛織りの粗布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。13そして天の星が地上に落ちた。それは、いちじくが大風に揺さぶられて、青い実を落とすようであった。14天は、巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島は、かつてあった場所から移された。15地の王たち、高官たち、千人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に身を隠した。16そして、山々や岩に向かって言った。「私たちの上に崩れ落ちて、御座に着いておられる方の御顔と、子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。17神と子羊の御怒りの、大いなる日が来たからだ。だれがそれに耐えられよう。」。参考、ホセア書10・8。
[x] ヨハネの黙示録7章には、欄外にあるように、イザヤ書からの引用がちりばめられています。イザヤ書11・12(主は国々のために旗を揚げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、ユダの追い散らされた者を地の四隅から集められる。)が、黙示録7・1(その後、私は四人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと押さえて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。)に;イザヤ書59・19(そうして、西の方では主の御名が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは、主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。)が、黙示録7・2(また私は、もう一人の御使いが、日の昇る方から、生ける神の印を持って上って来るのを見た。彼は、地にも海にも害を加えることを許された四人の御使いたちに、大声で叫んだ。)に;イザヤ書49・10(彼らは飢えず、渇かず、炎熱も太陽も彼らを打たない。彼らをあわれむ者が彼らを導き、湧き出る水のほとりに連れて行くからだ。)が、黙示録7・16(彼らは、もはや飢えることも渇くこともなく、太陽もどんな炎熱も、彼らを襲うことはない。)に;イザヤ書25・8(永久に死を呑み込まれる。神である主は、すべての顔から涙をぬぐい取り、全治の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる。主がそう語られたのだ。)が、黙示録7・17(御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、いのちの水の泉に導かれる。また、神は彼らの目から涙をことごとくぬぐい取ってくださる。)に。
[xi] 「頼るな」とは「頼る」+「するな」ではなく、一単語です。頼らない・やめるחָדַל ハーダル:1・16(洗え。身を清めよ。わたしの目の前から、あなたがたの悪い行いを取り除け。悪事を働くのをやめよ。)、24・8(陽気なタンバリンの音はやみ、はしゃぐ者たちの騒ぎも消え、陽気な竪琴の音もやむ。)
[xii] ネシャーマー נְשָׁמָה 4回:2・22(人間に頼るな。鼻で息をする者に。そんな者に、何の値打ちがあるか。)、30:33(すでにトフェトも整えられ、実に王のためにも備えられている。それは深く、広くなっていて、そこには火と多くの薪がある。主の息が硫黄の流れのように、それを燃やす。)、42:5(天を創造し、これを延べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。)、57:16(わたしは、永遠に争うことはなく、いつまでも怒ってはいない。わたしから出た霊が衰え果てるからだ。わたしが造ったいのちの息が。)
イザヤ書における「息」ルアハ רוּחַ ネシャーマー נְשָׁמָה
[xiii] この図は独り歩きして、世の終わりを暴力的なものとして描く宗教やSFになり、キリスト者もそんな影響を受けているかもしれません。確かにイザヤは、神が激しい形で、戦争や歴史の混乱さえ用いて、人間の幻想を終わらせることも告げています。しかし、それだけではなく、他にも様々な方法が出て来ます。子どもの誕生、困窮した者を慰めること、奇蹟や解放、病気と癒し、様々な方法を神は用いて、神は私たちの偶像崇拝を終わらせます。
[xiv] 「では、その人間の高慢(特に偶像化)はどうしたら砕かれるのか。それがここでの預言者の語りの強調点です。イザヤはこの箇所の中心で「万軍の主の日が臨む」(12節)と告げます。そして「高ぶる者と高慢な者すべてに己を高くする者すべてに。彼らは低くされる」と語ります。また「人間の高ぶる目は低くされ、人の高慢は卑しめられる。その日には、主のみが高くされる」(1節。1節もほぼ同様)と述べています。つまり、人間の高慢は結局、神が最も高い存在であることが決定的に示されることによってのみ砕かれるのです。それほど人間の高慢は人を支配するものです。」大島、56ページ
[xv] 「どうやってこのようなことが起こるのだろうか。実にそれは「主おひとりだけが高められ」(1節)、「主が立ち上がり」(22節)起こるのである。主は何もその御力を鑑がしくふるう必要はない。単にそのご臨在を現されるだけでいいのである。」、油井義明、65ページ