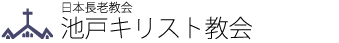2025/2/16 イザヤ書3章1~3節(1〜12節)「迷わす案内人」招詞:Ⅰコリント1・26~27
イザヤ書は、紀元前8世紀末の大きな変化の時代に、預言者イザヤを通して、頑ななユダの民に対して語られたことばです。民の中にあった問題の一つが、権力とか支配の問題であったことは、今日の箇所に明らかです。政治とか社会秩序が歪んでいました。といっても、政治や社会が歪んでいなかった時代なんてあるのでしょうか。現代の日本や世界も含めて。神である主がイザヤの時代に語られた言葉は、現代の私たちにも響いて来るみことばです。
1まことに、見よ、万軍の主、主はエルサレムとユダから、支えと頼みになるものを除かれる。
それは
すべての頼みのパン、すべての頼みの水
から始まって
2勇士と戦士、さばき人と預言者、占い師と長老、3五十人隊の長と身分の高い者、助言者と賢い細工人、巧みにまじないをかける者を。
と延々、色々な立場の有力者たちが挙げられるのです[i]。ただこのリストには、王と祭司は含まれません。本来、イスラエルの社会を維持する体制は、王と祭司と長老だったはずですが、王や祭司、本来の権威よりも、別の有力者、実力者たちのほうが幅を利かせている、というのも当時の混乱状況なのかもしれません。勿論、王や祭司だけに権力が集中するのもマズいわけで、そのためにももう一つの職務「預言者」が立てられたはずですが、その預言者も2節のリストに挙がっていて、その機能を果たしていなかったのです。そうしたすべての「支えと頼みになるもの」と思われてきた人々を、主は取り除くと言われます。
そのあり方の一つが4節以下の混乱状態、無政府状態です。
4「わたしは、若い者たちを彼らの君主とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。5民はそれぞれ仲間同士で虐げ合い、若い者は年寄りに向かって尊大にふるまう。身分の低い者は高い者に向かって。
ここにあるのは、リーダー不在の大混乱です。若い者、指導者を務めるには早すぎる人が長になり、仲間同士でも混乱して、年配者が足蹴にされている情況です。これは神がもたらした混乱であり、それと同時に、彼らが望んだまま、願った通りの成れの果て、でもありますね。
6節は「父の家」にいながら父親を後回しにして、兄弟にリーダーの責任を押し付けようという無責任ぶりでしょうか。
着る物を持っている
というだけで、乱れた有様を治めてくれ、というのは滅茶苦茶な理屈です。でもこれも現代にもありがちかもしれません。ファッションやルックスで政治家やスターが選ばれ、印象操作が第一となるとしたら、同じことでしょう…。かといって、続く7節の言葉も無責任です。傷の手当など出来ない、したくない、と重責は嫌がるのです。勿論、混乱に対処できもしないのに担ぎ出されてリーダーになるのも困りますが、指導者をただ押し付け合って、誰も責任を取りたがらない、というのも絶望的でしょう。
ローマ書1章には、神が、神に逆らう人間の
その心の欲望のままに汚れに引き渡されました。
とあり、「引き渡す」が三度繰り返されます。神は悪を選ぶ人を、罰するよりもその悪い思いに引き渡すことを裁きとします。イザヤ書にある主の裁きも、彼らが元から選んできた、気紛れ、尊大、虐げ合ってきた無責任の成れの果てでもあります。8節でもこう言われます。
8これは、エルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いが主に背き、主の栄光の現れに逆らったからである。[ii]
都や国が倒れたことと、民が言葉でも行いでも主に逆らい続けてきた背信、その両方が、この混乱状態の理由です。その背信の甚だしさは、9節で顔に出ていて、隠そうともせず、悪びれもしない、というほどの酷さです。
イザヤ書は決して、主なる神への礼拝儀式、宗教的義務が全く行われていなかったわけではありません。律義に朝晩の生贄や年間行事の祭儀は行われていたのです。けれども、それは形式だけになり、むしろそれが口実になって、実際の生き方では、人間的な力とか勝手気まま、争いごとが正当化されていました。主の言葉や、主の栄光の眼差しは省みられませんでした。ですから、ここ10節11節には、箴言のようなシンプルな倫理が彼らに突きつけられるのです。
10正しい人は幸いだ、と言え。その人たちは自分の行いの実を食べる。11悪しき者、悪人はわざわいだ。その手の報いは自分自身に降りかかる。
正しく生きるならその行いが結ぶ実を味わうことになります。悪しき生き方をすれば、そのお陰で人より早く、多く、得をしたように思えても、必ず悪そのものの報いが降りかかります。その典型的な事実が、イザヤが語っている社会の混乱という、結果であり、さばきです。
注意したいのは、ユダの社会にあったのは勇士と戦士、さばき人ら、権力者と言われるような立場の問題、権力の乱用です。そしてそれを裁いて、相応しい報いを与え、支えすべてを除かれるのは、主の権威です。神である主は、ただ人間の罪や背信に怒り、その全能の御手で力づくに罰する、裁く、というのではありません。主は、真実で、憐み深く、正しく、恵み豊かなお方です。その主の人格に基づくのが、主の権威です[iii]。だからこそ、主の権威は、人間の権力が正しく行われず、悪事に濫用されて、平然としている様子をそのままにはされず、相応しい形で終わらせるのです。人間の権力は、どんなものであっても主の権威の下にあります。そして本当の権威者、その恵みと真実ゆえに善を愛し、悪を憎まれる主は、人の権力乱用を裁いて破壊するだけでなく、その裁きを通して、新しい回復をもたらされます。ここで12節にはそれが仄めかされていないでしょうか。
12わが民は、幼子が虐げ、また女たちがこれを治める。わが民よ。あなたの案内人たちは迷わす者。あなたの歩む道をかき乱す。
幼子と女たちとは、社会で最も弱い者です。権力者にとっては、支配の関係が真っ逆さまに引っ繰り返る逆転です。ただ、子どもの中でも更に弱い孤児、女の中でも更に貧しい寡婦が虐げられていたことは1・17で告げられ、この後も繰り返される非難です。主は、権力者を引き降ろすだけでなく、虐げられていた者を引き上げてくださる。それは今の権力に胡坐をかいていたい人にとっては「虐げ」や屈辱でしょうが、主は人間の権力そのものを終わらせて、新しいことを始めようとしています。人間が立てた案内人たちが
「迷わす者、あなたの道をかき乱す」
としても、主はその人間の思惑が行き詰まり、彷徨さまよった先に、全く新しい道を備えておられる方です。迷わすままにして終わらせるのでなく、迷った者を捜すために来られる主です。その憐みと恵み、幼子や女性、権力などない者を愛して、生き生きと歩ませずにはいない主の真実こそ、真の権威です。それは、私たちの主、イエス・キリストが現された神の権威です。
イエスは「仕えられるためではなく、仕えるために」来られました[iv]。本当に権威あるお方イエスは世の権力者たちとは根本的に違いました。無責任に責任を押し付け合う人間とは違い、着る物や栄光や様々の持っている物すべてを脱ぎ捨て、私たちの主となる責任を引き受けてくれました。ご自分のいのちを捧げて、乱れ果てた有様をも新しい始まりへと変え、見える傷だけでなく見えない深い破れをも癒してくださいました。主は、世の権力者を批判するだけでなく、それ以上に私たちを癒し、力づけて、新しくしてくださる、本当に力のある方です。
今、自分の支えは、この神でしょうか。それとも大なり小なり、それ以外の何かでしょうか。それで争ったり、行き詰まったりして迷っている誰かが思い浮かぶでしょうか。それを「馬鹿な大失敗だ」とも言えるでしょう。しかしイザヤ書は叫びます。
人はみな草のよう、その栄えは野の花のようだ[v]。
拠り頼んでいた何かが枯れ萎しぼむ、とても厳しい迷い道にも、主がともにいて、他でもない主に支えられていたのだと気づかせ、権力に頼らない新しい生を始めさせてくださいます。教会はその告白を分かち合い、迷った人が行き着いて迎えられる場です。今日の招詞で告白した通り、私たちは
知者や有力者、高貴な者ではなく、愚かで弱く取るに足りない者、見下されている者が召された集まり
であると心から告白する集まりですから[vi]。
「すべての王や権力が冠を捧げてあなたを礼拝します。あなたこそ私たちと世のためご自身を捧げ、仕え、偽りや絶望から救い出し、喜びと愛を下さる方だからです。世の力がどんなに輝くとも、暗い闇を照らし、罪を赦して癒す、あなたの恵みには及びません。すべての支え、頼みはあなたのもの。正しく用いさせてください。それを失う時には新しいあなたの恵みを待ち望みつつ、主イエスご自身が私たちの支えであることを思い起こさせる日々としてください」
[i] 1節の「支えと頼みになるもの」は、「支え」(頼み)がמַשְׁעֵןマスエーン(ここの3回のみ)で、「頼みになるもの」がその派生語のマスエーナー(女性名詞)。男性名詞と女性名詞を並べて、<あらゆる頼みになるもの>を表していると言えよう。
気まぐれ者תַּעֲלוּלִיםターアールーム:ここと66・4「厳しく扱う」
[ii] 「主の栄光の」には欄外注があり「直訳:「目」」としています(つまり、「目の栄光の現れに逆らったからである。」)。聖書協会共同訳は8節を「エルサレムはつまずき、ユダは倒れてしまった。/彼らの舌と行いが主に敵対し/その栄光のまなざしに逆らったからである。」としています。
[iii] 「権力はリーダーの人格とは無関係だが、権威はリーダーの人格によって培われる。立場はリーダーに権力を与えるが、権威は与えてくれない。支配的なリーダーによる改革が行き詰まるのは、権力には限界があり、権力を行使しても人は変わらないからだ。…「偉くなりたい」との意味は権力と権限を獲得することではない。イエスはリーダーの影響力について言及されたのである。」 豊田信行「推薦のことば」、ジェームズ・ハンター『サーバントリーダーシップの原則』(嵯峨根克人訳、豊田信行監訳、地引網出版、2024年)
[iv] マタイの福音書20・25~28。
[v] イザヤ書40・6~8。
[vi] Ⅰコリント1・26~31:兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。27しかし神は、知恵ある者を恥じ入らせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じ入らせるために、この世の弱い者を選ばれました。28有るものを無いものとするために、この世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。29肉なる者がだれも神の御前で誇ることがないようにするためです。30しかし、あなたがたは神によってキリスト・イエスのうちにあります。キリストは、私たちにとって神からの知恵、すなわち、義と聖と贖いになられました。31「誇る者は主を誇れ」と書いてあるとおりになるためです。