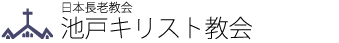2025/10/5 イザヤ書22章12~23節「どうせ明日は死ぬ、か?」
イザヤ書22章は「幻の谷についての宣告」と始まります。「幻の谷」とはどこの事だろうと思って読んでいくと「ユダ(7)」「ダビデの町(8)」「エルサレム(9)」とあって、この「幻の谷」とはどうやらエルサレムのことを指しているらしい、と分かるのです。
前回21章も「海の荒野」と謎めいた言い方でバビロンへの宣告が告げられました。同様にここでエルサレムが「幻の谷」と謎めいて呼ばれます。イザヤ書の13章から23章は諸外国への宣告が続いていますが、もう終盤のここ22章で、外国ではなくエルサレムへの言葉がある。それも、エルサレムは守られる、という保証の言葉ではなく、むしろ、俺たちは大丈夫と自惚れる慢心を責める言葉です。
1…これは、いったいどうしたことか。みな屋根に上ったりして。
町の人々が屋根に上っている。恐らく、攻めて来た敵が逃げて行った、町を囲んでいた危険が去ったのを、屋根に上って見ながら大喜びしているのでしょう。しかしその調子に乗った喜びは、神への感謝や礼拝、信仰には結びつかない浮かれ騒ぎに過ぎませんでした。真の神に心から立ち返れ、というイザヤの言葉は、エルサレムの人々には聞き流されていました。ですからエルサレムが一時的には窮地を脱しても、もっと強い敵が送られて、破壊される日は着実に近づいていたのです。その時にも彼らは、神である主に頼ることは後回し、先延ばしです。
8…その日、おまえは森の宮殿の武器に目を向けた。9おまえたちはダビデの町に破れが多いのを見て、下の池の水を集めた。10また、エルサレムの家々を数え、その家々を取り壊して城壁を補強し、11二重の城壁の間に貯水池を造って古い池の水を引いた。しかし、おまえたちはこれを造った方には目もくれず、遠い昔にこれを形造った方に目を留めなかった。
補強したり貯水池を造ったりして対策を講じたのが悪いのではありません。後にこの水道工事をリードするのは敬虔な王ヒゼキヤです[i]。しかしエルサレムの住民は、その水道工事をしながらも、そもそもエルサレムを造った方、水も大地も、世界をも造った方を見上げなかった。勿論、遠い昔に作っただけで今は疎遠な…という神では決してなく、今もイザヤを遣わし、本当に神に立ち返り、癒されるよう求めている神です。その神は、水や町や目の前にあるすべてのものを造った方でもあります。その神を蔑ろにして、自分たちがすべてだと思い上がる…。
こうした心が12節以下でも掘り下げられます。
その日、万軍の神、主は呼びかけられた。「泣いて悲しみ、頭を剃って粗布をまとえ。」13しかし、なんとおまえたちは浮かれ楽しみ、牛を殺し、羊を屠り、肉を食べ、ぶどう酒を飲んで言っている。「飲めよ。食べよ。どうせ明日は死ぬのだ」と。
町が助かったら有頂天に喜ぶ。一方で「どうせ明日は死ぬのだ」とも言う。本当に文字通りこのままを口にしたどうかではなくて、心の底に根深くある本心を言ってみれば「飲めよ、食べよ、どうせ明日は死ぬのだ」、俺の人生は俺のものだ、造り主が何と言おうと俺は俺で好きに生きて死ぬのだ、人生なんてそんなものだ…そういう本音です。
13章から23章で諸国への宣告が告げられます。神である主が、すべての民の主権者であり、歴史の審判者でもあることが語られます。でも、そうした言葉を聞きながらも、エルサレムの民は、禍を免れるかどうか、だけを考えるかと思えば、どうせ死ぬまでの命だ、と思って、神を忘れている――神を小さく考えている――そんな根深い傲慢さで、主のことばを聞き流しているだけ…。そういう「この咎」深い有罪ぶりがここ22章に取り上げられます。[ii]
その具体的な事例として、15節から「シェブナ」という人物が名指しされます。彼は宮廷を司る執事、いわば王に次ぐ地位、首相の座にありました。でありながらその立場を私物化し、高い所に墓を掘ったり、岩に自分の住まいを刻んだりしていました。その悪い影響は、宮廷や庶民にまで広く毒していたでしょう。17節の「ああ、勇者よ」とあるのは彼が勇者を自負していたことを皮肉ったものでしょう。18節に「あなたの誇る戦車」ともありますが、武器を自慢していたのでしょうか。武器や岩に立てた家、高い所に立てた墓を誇って、自分のために地位を濫用しているシェブナは、造り主を心に留めず、「飲めよ。食べよ。どうせ明日は死ぬのだから」と嘯うそぶく姿の最たる事例でした。万軍の神、主は彼に対して
19わたしがあなたをその立場から追放する。あなたは自分の地位から引き降ろされる。
と言われるのです。
このシェブナの代わりとなるのが、20節から描かれる「わたしのしもべ、ヒルキヤの子エルヤキム」という人です。エルヤキムはシェブナの執事の着物、長服・飾り帯を与えられ、権威を委ねられます。
22わたしはまた、彼の肩にダビデの家の鍵を置く。彼が開くと、閉じる者はなく、彼が閉じると、開く者はない。23わたしは彼を杭として、確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。
主はエルヤキムをシェブナ以上に信頼するかのようです。しかし、続きの24、25節が悩ましいのです。
24彼の上に、父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫も、すべての小さい器も、鉢からすべての壺に至るまで。25その日――万軍の主のことば――確かな場所に打ち込まれた杭は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。――主はそう語られた。』
エルヤキムは確かな場所に打ち込まれた、のではなかったのでしょうか。それでも、彼の所に、誰も彼もが見境なく集まって来てしまって、そうなれば、エルヤキムも失墜する、ということでしょうか。いずれはエルヤキムも死んだでしょうし、またエルサレムがバビロンに敗れて捕囚となる定めも、エルヤキムに頼ったからと言って避けられたわけではありませんから、そのことを指すのか…。[iii]
疑問も残るのですが、その疑問を解決するよりも大事な、この章の趣旨は明らかです。この22章から新約聖書が引用する箇所が二つあります。13節をⅠコリント15・32が引用します。死者の復活について論じる中で、
…もし死者がよみがえらないのなら、「食べたり飲んだりしようではないか。どうせ、明日は死ぬのだから」ということになります。
と言うのです。主イエスの復活は、私たちも死んで終わりではなく、復活し、神とともに永遠に生きることの保証です。それは「どうせ明日は死ぬのだ」といのちを弄もてあそぶ生き方を引っ繰り返します。いやそれだけなら、「永遠に生きられるだって? 明日で死ぬんじゃないなら儲けもんだ。もっと楽しんでやれ」と屋根に上がって浮かれかねないのも、ここに炙り出される姿勢ですし、私たちの中にもありかねない、永遠のいのちへの誤解でもあります。
もう一つ、ヨハネの黙示録3・7で、主イエスがご自分のことを
聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと、だれも閉じることがなく、彼が閉じると、だれも開くことがない。その方がこう言われる――。
と言います。今日のイザヤ書22・22、エルヤキムに言われた言葉を借用するのです。エルヤキムはやがて死にましたが、彼は主イエスの影・予表でした。そして、黙示録では困難極まる中で、小さくとも誠実に精一杯に歩んでいた教会への言葉として、この主イエスの自己紹介があるのです[iv]。主は私たちのために門を開いてくださる。しかし、開けっ放しではなく、閉じることもなさる。そこに「飲めよ、食べよ、どうせ明日は死ぬのだから」という思いはほんのひと握りさえ持って入ることは出来ません。自分のために目立つ墓・記念碑を立てるシェブナのような誇りも、門の手前で手放させてくださる。いや、頑なに、卑しく、造り主に向くことも出来ない私たちの心の扉こそ、主は開いてくださり、主を心の奥に迎えさせてくださいます[v]。イザヤの言葉は主イエスへと続いています。
明日は死ぬかもしれない、朝は来てまた夜も来る、大きな墓が羨ましいかもしれない…けれど、主イエスが私たちの主としておられ、今日という日を生かし、飲む物も食べる物も与え、私たちの労苦も喜びも戦いも、尊くかけがえのないものとしてくださっています。
「造り主、聖なる真実な主よ。祝福の言葉も厳しい御言葉も、自分に都合よく聞いてしまう、心鈍く頑なな私たちは、主の御心通り、恵みによって新しくされ、今日を永遠の如くに生きる者とされることを待ち望んでいます。御国に入ることにもまして、御国を私たちの心に、生活に、家庭に、この世界に迎え入れることを願います。今、パンを食べ杯を飲みます。主が捧げた、十字架と復活のいのちをもって、私たちを強め、慰め、手も心も開いて歩ませてください」
[i] Ⅱ列王記20・20:ヒゼキヤについてのその他の事柄、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を造り、都に水を引いたこと、それは『ユダの王の歴代誌』に確かに記されている。
[ii] 14節:万軍の主は私の耳に宣告された。「この咎は、おまえたちが死ぬまで決して赦されることはない。」万軍の神、主はそう言われた。
[iii] 更に、このシェブナとエルヤキムが、この先の36章3節以降で「宮廷長官エルヤキム、書記シェブナ」として出て来て、エルサレムを包囲するアッシリア軍との交渉にあたるのです。シェブナが宮廷長官でなく、書記となっているのは、この22章の成就なのか、しかし、22・17~19で言われていたのはもっと徹底的な罷免ではないか、あるいはシェブナは回心したので書記に降格するだけで留まったのか…諸説あります。
[iv] 「黙示録中、励ましと慰めとに満ちた箇所のうち、フィラデルフィアに宛てた手紙は、常にその第一番目に位している。キリスト教史の幾世代が、どれだけこの箇所から慰めと力とを得てきたかを語りうるものは、だれもいない。讃美が歌われ、祈りがささげられた古い聖堂の壁の上には幾百年もの驚くべき色がしみついているように、窮乏と抑圧に遭遇して、そこから見上げたこの静かな光彩のような数行の中には、キリスト教史の幾多の世代への回想がある。……フィラデルフィアに宛てた呼びかけには、牧会者としての優しさのおもかげがあるが、なお約束と恩恵の権威は弱められてはいない。」(Lilie, pp. 126-7)、小畑進『小畑進著作集 第1巻 ヨハネの黙示録講解Ⅰ』、290頁。
[v] 「彼は普通の戸のように一つの空間を互いに結びつけるのでなく、三つの空間をつなげる深い奥義をもったとの鍵の支配人としてその教会の前に現れたもう。それは、神から人の心へ、人の心から神へ、さらに一人の人の心から他の人の心へと通じる戸であり、私たちの上と、前と、中とにある戸、天と地ほどにへだたっている世界を互いにつなげる戸である。したがって主は言われる。私たちの前にある戸を人の心に向けて開き、私たちの上にある戸を父なる神に向けて開くのは、特別の奇跡であると。この奇跡を完成するには唯一の器しかない。この驚くべき、恐るべき器は、人や民族や諸力や魔力や、もちろんサタンの手中にあるのではなくて、イエスの手中のみにある」と。 (Hellmuth Frey)、小畑、上掲書、294頁。