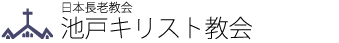2024/9/15 ヨハネの福音書19章16b〜22節「罪状書は「王」」
いよいよイエスが十字架につけられた、という今日の箇所です。18節にさらりと
「彼らはその場所でイエスを十字架につけた。」
とありますが、十字架という処刑の残酷さを思えば、あっさりと読み進めてはならない気もします。かといって、十字架の苦痛を強調しすぎて、イエスをそんな酷い目に合わせた、当時の為政者や群衆を非難すればいいのでしょうか。あるいは、彼らの罪に、私たち自身の罪や頑なさを重ねて、自分を責め、イエスへの申し訳なさを抱くべきなのでしょうか。このヨハネの福音書の書き方は、そういう人間の予想――イエスは誤解されて十字架に殺されたとか、苦しめられ犠牲にされた可哀想なイエス様――という見方が、予想もしないイエスを描いて来ました。それが、ここで頂点に達します。すなわち、
17イエスは自分で十字架を負って、「どくろの場所」と呼ばれるところに出て行かれた。
自ら十字架を負い、十字架につけられる場に向かったというのです。十字架を負い、とは、十字の形に組み合わされた木ではなく、横木だけを背負わされて刑場まで担がされたのです。そうして刑場まで進み、既に据えられていた縦棒に十字型に磔にされたのです。横木だけでも、鞭打たれた背中には耐え難いほど食い込んだでしょう。向かう場所は「どくろの場所」と呼ばれる、「ヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている」場でした。どうして「髑髏(頭蓋骨)の場所」なのでしょう。その場に骸骨が散らばっていたのだ、という説もありますが、汚れを忌み嫌うユダヤ人が骸骨を野晒しにしたとは思えません。「頭蓋骨に見える形の丘だったのだ」という説明もあります。聖歌399番「カルヴァリ山の十字架」がありますが[i]、「髑髏」をラテン語でcalvariaということから来ています。カルヴァリ山・丘というのはある時からの伝承に基づきますが、「丘」という記述は聖書には一言もなく、後から絵になるイメージとして広まったものでしょう[ii]。髑髏の形に見えた、という説明も根拠に乏しい。その由来は分かりません。由来はともかくとして「髑髏(されこうべ)」と呼ばれるいかにもおどろおどろしい場所で、十字架にかけられるべく、十字架を運ばされました。しかしここでイエスは、背負わされ、運ばされた、ではなく「自分で十字架を負って、「どくろの場所(ゴルゴタ)」に出て行った」と言うのです。それは、
10章18節だれも、わたしからいのちを取りません。わたしが自分からいのちを捨てるのです。わたしには、それを捨てる権威があり、再び得る権威があります。…15章13節人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません。
こうしたみ言葉の成就でした。イエスは誤解された被害者・悲壮感あふれる犠牲者ではなく、自ら進んで、私たちのためにいのちを捧げた主です。自分で十字架を負い、刑場に行きます。それは、髑髏の場、呪わしい名で呼ばれた場も、私たちの死や悲しみや絶望の場所にイエスが来ることで、その場を愛の場所、希望の地、始まりの場所に変わらせるため、でした。
ヨハネ以外の福音書、マタイ、マルコ、ルカは、イエスが十字架を運ぶ途中、偶々(たまたま)そこに居合わせたクレネ人シモンという人に、兵士たちが十字架を無理やり背負わせたと伝えます[iii]。兵士たちは、もうヘトヘトになったイエスにいつまでもダラダラと十字架を運ばせるより、通りがかりの人に十字架は運ばせて、さっさと十字架刑を始めたかったのでしょう。ヨハネはそのことを省いています[iv]。体力的には限界の状況でも、イエスはなお自分で十字架を負おうとしていた――決して逞しいとか馬鹿力があってとかでない、ゴルゴタまで行く力も残っていないと見える様な中で、イエスは自分で十字架を負い、運ぼうとしていたのです。[v]
このことに続けて、ヨハネはここに十字架の罪状書きのことを伝えます。
19ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには「ユダヤ人の王、ナザレ人イエス」と書かれていた。20イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを呼んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。21そこで、ユダヤ人の祭司長たちはピラトに、「ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてください」と言った。22ピラトは答えた。「私が書いたものは、書いたままにしておけ。」
イエスの十字架の罪状書きのことは四つの福音書が全て言及していますが、ヘブル語、ラテン語、ギリシア語、三つの言葉で書かれたことはヨハネだけの独自な記録です。最近、日本の各地でも、日本語と英語だけでなく、中国語と韓国語を併記した看板を見ます。イエスの罪状書きも、地元ユダヤのヘブル語と、ローマ公用のラテン語、そして広く共通語として使われていたギリシャ語で書かれました。通りがかる人々はこの三つの言葉のどれかは読める。図らずも、世界中から来る人々をざっくりとカバーできる仕方で、この十字架につけられた男は「ユダヤ人の王、ナザレ人イエス」という罪状書きが掲げられたわけです。それはユダヤ人だけの王ではなく、世界にとっての王である、というメッセージにもなりました。
これにはユダヤ人の祭司長たちが猛然と抗議します。イエスを亡き者に出来たと思ったら、思わぬピラトの抵抗に、彼らは大いに悔しがることになる。「ユダヤ人の王、ではなくユダヤ人の王と自称した、と書いてくれ」と要求しますが、ピラトはそれを拒むのです。
ピラトがここで「ユダヤ人の王、ナザレ人イエス」という文言を譲らなかったこと。それはピラトの個人的な恨み、細(ささ)やかな抵抗かもしれません。だとしても、それは確かにイエスを憎む人々にとって、十字架が自分たちの思い通りの勝利ではなく、手から滑り落ちて転がっていくような歯痒さだったでしょう。イエスの十字架が敵たちの勝利に見えて、実は彼らの敗北であった。イエスを十字架に葬れば万事解決、という思惑は大外れで、イエスは自ら十字架を負ってご自分を捧げる方だった。イエスはユダヤ人の王を自称した詐欺師ではなく、自らのいのちを与えて止まない、本当の王であった。そしてそれは、その罪状書きを書かせて撤回させなかったピラトの不思議な意固地さにも見て取れます。ピラトが最後までイエスを「ユダヤ人の王」と言い続けて、ユダヤ人たちはそれをどうすることも出来ない。そしてこの後ヨハネでは、祭司長たちが十字架のイエスを嘲ったり罵ったりすることは省略され、祭司長たち自身、舞台から退場します。もう姿を現しません。そして、イエスが十字架の最期の時まで、すべてを仕切っておられることが30節まで伝えられます。十字架はイエスが王であることの証しです。
ピラトは、少し前、自分には権威があると背伸びしていたのに、今はイエスに「王」という札をつけます。ピラトの拘りに「彼はイエスを信じてキリスト者となった」とまで言い切ることは控えます。ただここでピラトにもこんな態度を取らせたイエスが、私たちにも、十字架につけられたイエスを
「ユダヤ人の王」
私たちの、世界の主という告白を与えてくださった、と思わされるのです。
イエスが王として治めてくださっている中で、私たちがイエスを主、神として告白する信仰を持てるのです。それも、奇跡のようなこと、勝利や力に酔い痴れる出来事が起きたから信じる信仰ではなく、重荷を背負い、敵が勝利を祝い、髑髏の場所に立つような思いをする時にも、そこにおられ、治めておられるイエスを告白する――ただ口で告白するだけでなく、今まで自分の力、権威、考えを握りしめていた手を開いて、本当にイエスこそ私の王でいてくださる、と心から明け渡す。イエスこそ王です、と告白するのです。
勿論それは、一矢報いるためでも、単なる頑固さからでもなく、イエスが私たちのために十字架を負われたこと、それも仕方なく負われたから申し訳ないから、ではありません。
私たちを罪や偽りの神から解放して、喜びと信頼をもって生かすため、自ら喜んで十字架を負って、ゴルゴタに行かれた――そのイエスを知らされて湧き上がる、譲れない告白です。
それはイエスが下さる贈り物です。
「私たちの王、主イエスよ。あなたは御父の愛に押し出され十字架を背負われました。その死は、神の敗北ではなく、主の恵みの勝利であり、復活への入り口でした。この告白も、聖霊によってあなたが私たちのうちに芽生えさせてくださった恵みの賜物です。主を絶えず仰がせてください。主こそ王であり、私たちを治め、悪や敵をも奇しく支配なさいます。その信頼をもって歩ませてください。私たちをも担い続け、ゴルゴタを恵みに変える御業を現してください」
[i] さんびか (chobi.net)、参照。新聖歌105番「栄の冠を」にも「カルバリ」が歌詞に出て来ます。
[iii] マタイの福音書27章32節、マルコの福音書15章21節、ルカの福音書23章27節。
[iv] この後18節で「彼らはその場所でイエスを十字架につけた。また、イエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に、ほかの二人の者を一緒に十字架につけた。」とあるのも、ルカはその二人の強盗の一人が、イエスへの告白をして、パラダイスの約束をもらったと伝えますが、ヨハネもマタイやマルコもそれは伝えません。「こんな肝心なことを!」というのは私たちの考えで、それぞれに伝えたいことにフォーカスしています。
[v] そこには、イエスが、私たちのどんな罪や重荷をも背負ってくださること、私たち自身を最後まで決して諦めず、見捨てずに、自ら背負ってくださる愛が重なるのです。