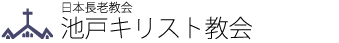2025/4/20 Ⅰコリント15章1〜11節②「最も大切なこと 復活の主が現れる」
キリストはよみがえった。神はイエスを死者の中からよみがえらせ、イエスは今も生きておられる。この告白こそ、教会の最も大切な告白です。主の弟子たちが最初に伝えたことが「神はイエスを死者の中からよみがえらせた」であったことは、使徒の働きの中で繰り返されています[i]。復活の朝の詳しい出来事は、四つの福音書が伝える通りですが、そのドラマに先立ってまず教会が宣べ伝えたのは、「キリストはよみがえった」という事実でした。それは紛れもない事実であって、弟子たちのでっち上げでも、妄想でもなく、本当によみがえって、多くの弟子たちが目撃証人として、証言出来た通りの事実だと教会は信じるのです。
教会は、と言いましたが、この手紙「コリント人への手紙第一」を受け取った、ギリシャのコリント(今のコリントス)の教会もキリストを信じる集まりだったはずです。ですから、キリストの復活を信じ、受け入れていたはずです。それを、この15章でパウロが再度取り上げています。その理由は、コリントの教会の中に、復活を信じない人が出て来たからでしょうか。ある意味ではそうでした。この後の12節にこうあります。
12ところで、キリストは死者の中からよみがえられたと宣べ伝えられているのに、どうして、あなたがたの中に、死者の復活はないと言う人たちがいるのですか。
キリストは死者の中から復活した、だけど、私たち人間が死んだら、それでおしまい、復活などない――こういう意見がコリント教会の中で口にされるようになり、放ってはおけない状態になったのです。そこで、パウロはここでイエスの復活を確認します。
13もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。
その後も続いて、私たちの宣教も信仰も空しいし、私たちは神について偽証したことになり、あなたがたは今もなお自分の罪の中にいるし、キリストにあって眠った者たちは、滅んでしまったことになる、と続けます。
19もし私たちが、この地上のいのちにおいてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れな者です。
ここまで言い切ります。私たちが死んで終わりなら、キリストの復活もなく、私たちの望みなど惨め極まりないものだ、と言い切る。しかし、20節から、その理屈を引っ繰り返します。
20しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。21死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。22アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。
キリストの復活は、眠った者の初穂――すべての人が死者の中から復活する希望の先駆け・始まりなのです。それはキリストと同じように三日目に復活するわけではありません。
23しかし、それぞれに順序があります。まず初穂であるキリスト、次にその来臨のときにキリストに属している人たちです。24それから終わりが来ます。…
とあるように、将来の終わり、完成の時です。それまでは復活はありません。死や死別の悲しみを免れることはなく、癒されてほしい、死んでも生き返ってほしいと嘆くばかりのこともあります。それでも、その死は「眠り」と言い換えて呼べます。いつか目が覚めて、もう一度、体をもって復活し、ともに逢う最後があるからです。魂の行く天国という死後ではなく、終わりの日の「からだのよみがえり」を告白するのが、使徒信条です。更に24節はこう続きます。
…そのとき、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。25すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。26最後の敵として滅ぼされるのは、死です。…
その終わりの時は、すべての力は滅んで、神が唯一の王として治める時の始まりです。すべての敵は滅ぼされ、最後の敵と言われる死も滅ぼされます。その最後の敵である死の敗北が、あの朝、イエスが死者の中からよみがえったことに先取りされたのです。
イースターに祝うのは、イエスが死者の中から復活したと、イエスだけを誉めそやし、英雄視し、その功績を称える――人間の偉人への表彰の延長でしかないようなお祝い以上の事――それは私たちも、この世界も、キリストの復活を初穂として必ず復活するという希望、最後には勝利が備えられている、という確信の前祝いです。聖書は最初に
はじめに神が天と地を創造された。
と書き出し[ii]、最後は
アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みが、すべての者とともにありますように。
と結びます。この世界は、神が創造された世界。今は神が見えず、悩みや労苦が多く、悪や人間の争いに翻弄され、どんな人も病んで死が避けられない空しい世界に見えるとしても、それでもこの世界は、神が創造された世界、元々「良い」世界であって、やがてすべての悪は滅ぼされて、死も滅ぼされて、死者はよみがえり、栄光の御国が始まる――その初穂が、イースター、キリストの復活なのです[iii]。
キリストが今から二千年程前、確かにエルサレムで十字架に死に、墓に葬られ、三日目に復活し、弟子たちに会った。このリアルな出来事が将来の復活、素晴らしい勝利の初穂だと信じる信仰は、決して来世に逃げ込んで、今の歩みを軽んじる態度にはなりません。この15章の結論は「ですから、私の愛する兄弟たち。堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。あなたがたは、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。」と結ばれます。今の労苦は無駄ではない、死は終わりではなく、復活を約束されたこの人生を、意味ある人生として働き、生き、死を迎えるのです。そして、そのように変わるのも主の恵みです。私たちの罪のため、死んで、復活された主がしてくださる恵みです。
15章最初でパウロはこう続けます。
8そして最後に、月足らずで生まれた者のような私にも現れてくださいました。9私は使徒の中では最も小さい者であり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しない者です。10ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私はほかのすべての使徒たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私とともにあった神の恵みなのですが。
かつてのパウロは、神の教会を迫害した、教会の敵でした。律法主義的な聖書理解で、キリストが呪わしい十字架にかかったなんてとんでもない、と教会を滅ぼそうとしたリーダーです。しかしそのパウロにキリストが現れてくださいました。恐れ敬うべきキリストが、私たちの罪のために呪わしい十字架にかかり死なれた、そしてよみがえった、それこそ聖書に書いてある通りのことだった、とパウロは知りました。いいえ、キリストがパウロに分からせてくださいました。主はパウロを罰するどころか、赦し、そしてかつての敵のパウロを、初代教会最大の宣教師としました。それが、私たちの罪のために死んだ主が、よみがえって、敵だったパウロをも赦し、人を殺す生き方から生かす働きへ、自分の枠に嵌はまらない人を排除する人物から今や遠いこのコリントの人々のために心砕いて手紙を書く仕え人へと、変えた恵みです。パウロだけでなく、主は私にも、皆さんにも現れて、今を新しく生きるよう恵みを日々下さるのです。
復活は決して勝利主義、ただの楽観主義ではありません。それは十字架を経ての復活でした。人間の罪の悲惨さ、絶望、闇の深さ、苦しみや醜さを味わい尽くした十字架こそが、復活に先だったのです[iv]。その十字架と、終わりの復活の間で、私たちの体は労苦を続けます。苦しみ、呻き、衰え、死を迎えます。その私たちと同じ体を、イエスは持ち、私たちの罪のために死に、よみがえらされた。だから私たちは、今のからだでの労苦が無駄ではないと知り、やがて死を迎える時にも、復活と、この世界全体が贖われて、新しくされる約束を仰げるのです。
「主よ、まことにあなたはよみがえられました。私たちの罪のため、死にて葬られ、三日目に復活されました。確かに墓は空に、弟子たちは新しくされ、世界は終わりの時代になりました。この朝、世界中の教会とともに使徒信条を告白し、復活の主を仰ぎます。今ここにも主が生きておられ、罪の赦しと新しいいのちを与えてくださいます。私たちを担い、支え、労苦を祝福してくださいます。どうぞ永遠の朝を迎えるに相応しく、恵みをもって私たちを導きください」
[i] 使徒の働き2・22~36、11~26、4・2、8~12、5・29~32、9・20、10・34~43、13・16~41、17・3、18、22~32、24・10~21、26・1~23。「(イエスは)よみがえられた」と訳される言葉は、文法的には「よみがえらされた」(受動態)です。
[ii] 創世記1・1。
[iii] 「キリストの死人の中からの復活は、滅びゆくべき世界の大変革、身体と大地の変容の始まりを予示している。古代教会が祝ったこのイースターの宇宙的な喜びは、東方教会の典礼を通して今日に至るまで伝えられている。神の国は「義の宿る新しい天と新しい地」(Ⅱペトロ三・一三、ヨハネ黙示録二二・一)として到来する宇宙の大変革の中心にはキリストがおられる。なぜなら「天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も、支配も権威も、万物は御子において造られた」(コロサイ一・一五、またⅠコリント八・六、ヘブライ一・二、ヨハネ一・三)からである。「天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられる」(エフェソ一・一〇)こと、そこに全歴史のクライマックスがある。」芳賀、『神学の小径Ⅴ』、キリスト新聞社、2024年、373ページ
[iv] 「神の国がこの方において始まったということを決定的に示す出来事が、十字架につけられた方の復活である。十字架の苦難と死は、人間の希望なき状況の極致を表している。この深い淵の底では人は絶望するほかなく、誰一人希望することはできない。しかし、この絶望的な状況に神ご自身が入り込み、これを克服し、死から命を造り出された。キリスト教的希望は楽観主義とは無縁である。十字架の中に現実の悲惨さを見据えている。しかもこの悲惨さを打ち破るものとして復活が起こったのである。「信仰とは実際、限界を踏み越え、超越し脱出することである。そうではあるが、おしかぶさってくる現実が、隠されたり跳び越えられたりはしない。死は現実的な死であり、腐敗は悪臭を放つ腐敗なのである。……信仰は、苦難・罪責・死の中に取り囲まれている人生の限界を、それらが現実に打ち破られた場所においてだけ踏み越えうる。苦難と死により神に捨てられたようになり、墓から甦えり給うたキリストへの聴従においてのみ、信仰は、もはや困窮がない彼方を望み、自由と歓喜を望み見ることができるのである。十字架につけられた者の復活において、すべての人間的望みがつきる限界が打ち破られたあの場所において、信仰は希望に向かって自らを広げることができるし、広げなければならない」(モルトマン「希望の神学」高尾利数訳、新教出版社、一九六八年、一〇頁)。/ 使徒パウロによれば、アブラハムは「死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神」を信じたからこそ、信仰の父となった。そしてこう述べる。「彼は希望するすべもなかったときに、なおも望みを抱いて、信じた」(ローマ四・一八)。原文を直訳すれば、アブラハムは「希望に逆らって、希望において信じた者(Who against hope believed in hope) [KJV])」である。キリスト教的希望は死人の中からの復活に根拠を持っている。だから私を克服する神こそ「希望の源」(ローマー五・一三)であり、復活のキリストが「栄光の希望」(コロサイ一・二七)となる。/ ユダヤ人の哲学者ヴァルター・ベンヤミンは言う。「ただ希望なき人々のためにのみ、希望はぼくらにあたえられているのだ」(『ベンヤミン著作集5」高木久雄編訳、晶文社、一九七二年、一二八頁)。難破船の壊れかけたマストの先端からでも、僕らは希望のメッセージを紡ぎ出さねばならない。そして私たちはさらにその先を語る。それが本当に可能となるのは、十字架につけられた方の復活を知っているキリスト教的〈信〉の担い手たちなのだと。」 芳賀力、371〜372ページ