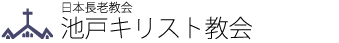2025/4/13 Iコリント15章1〜11節「最も大切なこと」棕櫚の主日礼拝説教
今週は、主イエス・キリストの受難と十字架の死を覚える「受難週」です。ちょうどこの時期の「過越の祭」に、イエスはエルサレムの都に来て、金曜日に十字架につけられました。その三日目の日曜日、主イエスは墓から復活しました。その復活のお祝いが復活祭イースター、教会の最大のお祭りです。キリスト教会の信仰の始まりは「キリストは復活した」「神は主イエスをよみがえらせ、主は今も生きておられる」という復活の告白です。
このコリント人への手紙第一は、新約聖書の七番目に置かれていますが、書かれた時代は、最初の四つの福音書やローマ人への手紙よりも早く、紀元54年頃とされます。そしてここに、
1兄弟たち。私があなたがたに宣べ伝えた福音を、改めて知らせます。あなたがたはその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。2私がどのようなことばで福音を伝えたか、あなたがたがしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなたがたが信じたことは無駄になってしまいます。
使徒パウロが伝えた「福音」の言葉が確認されます。それは3節で「最も大切なこと」と言い換えられます。これはパウロが勝手に考え出したものではなく「私も受けたことであって」、イエスの死と復活の後、キリスト教会が歩んできた中で伝えられ、信じられ、告白されて受け継ぎ続けた「最も大切なこと」です。最初の福音書が書かれるより先に、初代教会の中で定式化していた信仰のエッセンスです。それは
3…キリストは、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、4また、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおりに、三日目によみがえられたこと、5また、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
「よみがえられ、現れたこと」が「最も大切なこと」の中心です。しかしその前に主が死なれたからの復活です。死ななければ復活は出来ません。復活に先立ち、キリストは死にました。まず低く下り、卑しめられ、人間の最も深い闇にまで降りてくれました。それはちょうどジャンプするために、まず身を屈めるように――プールに落ちた宝物を拾うために、まずプールの底に潜るように――キリストは本当に死に、神はそのキリストをよみがえらせたのです[i]。
キリストとは「神が油注がれた方」という意味で、神から任職された預言者・祭司・王としてこの世界に派遣される、救い主、救世主、良い支配者と言い換えられるでしょう。イエスや新約聖書の書かれた時代には、他にも「救い主」を名乗る人物はいたのです。ローマ皇帝のアウグストゥスもそうですし、反乱を放棄させた革命家たちもいました。彼らも皆、死にました。けれどもそれは悲劇や不本意な死でした。願わくは、もっと生きて、自分たちの願う世界を手にしたかったのです。ただイエス・キリストだけが、不本意な死ではなく、最初から死ぬため、いのちを捧げるために生きた救い主でした。それは、私たち人間には非常識な救い主です。
このコリント人への手紙第一の15章は次の16章が最後になる前の長い一章です。しかし後一章で終わるというこの段階で初めて福音について語っているのではなく、一章の最初から福音について語っています。そこにはキリストの十字架が「愚か」で「つまずき」と言われます。
一18十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。…22ユダヤ人はしるしを要求し、ギリシア人は知恵を追求します。23しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、24ユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。
キリストが十字架に死んだこと、それは人間が神や宗教に期待する「しるし」とは真逆です。また人間の頭で考える知恵や哲学からすれば、愚の骨頂です。哲学の源流となるギリシア思想では、そもそも体や物質というものは汚れていて空しく、価値はないと考えられたのです。病気になったり、怪我で傷つき、老いていき、やがて死ななければならない肉体は、劣った、虚しいものだとしたのです。ですからキリストが死んだこと、つまり死すべき肉体をとって生き、本当に死んだことは、ギリシア人にとってはお笑い種で、愚かな言葉でした。その常識外れ極まりないことを、キリストはしてくださった――死ぬことも、肉体を取ることも厭わなかったキリストの福音を、教会は伝えて来たのです。そしてそれは「私たちの罪のため」でした。
「私たちの罪のため」とは私たちに罪があること、それも水に流せば済む程度の罪や、自分の力で償えるなどしない、キリストのいのちしか償えない途方もない罪があるということです。かといって、その私たちの罪のせいでキリストが死んだ、のでもありません[ii]。私たちの罪を解決するために死んで、確かに「葬られ」、
4…三日目によみがえられたこと…
これが教会が拠って立つ告白です。キリストの復活は、その前にキリストが私たちと同じ人となり、死んだからの復活です。肉体は肉体でも、不死身の体を持ったのではなく、私たちと同じ肉体――お腹が空き、眠くなり、傷つけられ、死に得る体で生きる人となり、そして死んだのです。
そして、これは「聖書に書いてあるとおり」のことです。このコリント人への手紙が書かれた時の聖書とは、まだ新約聖書は書かれ始めたばかりで、旧約聖書の事を指します。旧約に「メシアキリストが私たちの罪のために死ぬ」と明記していると言えば、交読したイザヤ書53章です。
イザヤ53・12彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのためにとりなしをする。
しかしコリント書でパウロが言いたいのは、そういう特定の箇所よりも、聖書全体が、キリストが私たちの罪のために死なれ、よみがえり、私たちに現れて、この福音に立つ救いを下さるということでしょう。そしてそれこそが「最も大切なこと」と言われるように、聖書の中心の福音です。そのことをハッキリと言い表したのが、イザヤ書53章であり、イザヤ書です[iii]。また、聖書においてずっと語られているのは、神は、ご自身が私たちの罪のために、自ら犠牲を厭わず、痛みを負うてくださることです。そして、それが紛れもない事実であることが、今から二千年程前、ユダヤのエルサレムで起きました。ローマのユダヤ総督ポンテオ・ピラトの元、ナザレのイエスが十字架で死んだのです。その年の過越の祭り、春分の次の満月に近い金曜日、午後3時ごろにイエスは死にました。この出来事は歴史に刻まれて、敵対者も否定しなかった事実です。それは「聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれた」死です。
「キリスト教の何を信じているの?」と聞かれたら、今日の箇所から答えればよいのです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死んで葬られ、三日目によみがえって、弟子たちや私に現れてくださった、そう信じているのです、と。「イエス・キリストを信じるだけで救われる」という答え方もあるでしょうが、他の宗教でも似た言い回しをします。しかし私が信じるやどうする以前に、キリストが本当にこの世界で、私たちの罪のために死なれた、という事実があり、紛れもなく葬られ、そして三日目に復活した、この福音に私たちは立ち、救われる[iv]。私はこう言い換えるようになって、福音理解が深く変わりました。自分の信仰が中心ではなく、キリストが中心に変わり、私と主との関係そのものが変わり、今も変えられ続けています。この「最も大切なこと」は最も不思議なこと、最も慰めと希望に満ちたことです。
この後、他の四つの福音書も書かれていき、主イエスの最後の一週間の教えや出来事が伝えられています。受難週はその出来事を一日一日味わう週でもあります。しかし抑々そもそもその大枠である「キリストが、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと」が驚きなのです。私たちの罪と死、人間としての痛み、悩み、悲しみをキリストはいのちをかけて味わってくださいました。その死から主が復活したことが、私たちの信仰の土台なのです。
「十字架の主よ。私たちのためこの世に来られ、苦難を味わい、十字架の死さえ引き受けたあなたを褒め称えます。私たちの悪や闇も、その根である、あなたを失った罪も、この体で生きるすべてのことを、あなたが味わったこと、今から二千年前のこの季節に、確かな事実としてあったことを、この受難週に覚えられる幸いを感謝します。死に、そしてよみがえられた主よ。どうぞあなたの命で私たちの罪を洗いきよめ、私たちの体も命を運ぶ土の器としてください」
[i] 「さて、この場合、欠けている章とは、つまり、キリスト教徒たちが申し述べている章とは、何でしょうか?受肉の話は下降と復活の話です。私がここで「復活」というのは、主の〈復活〉の最初の数時間、あるいは数週間のことだけではありません。私は、下へ下への下降すべてと、再上昇の大きな構図のことを言っているのです。われわれが通常〈復活〉と呼んでいるのは、いわば折り返し地点なのです。その下降の何たるかを考えてみてください。それは人性へだけでなく、人間の誕生に先行する九か月の間の、すべての人間が繰り返すという奇妙な、人間以前の、人間以下の生命までもの下降であり、さらに下って、死体の状態にまでなる下降なのです。その死体は、この上昇の動きが始まらなければ、まもなく全く有機物でさえなくなり、すべての死体同様、無機物に戻ってしまったでしょう。私がそのイメージとして思い浮べるのは、誰かが深く潜って海底をさらっている様子です。あるいは、強い男の人が、とても大きな複雑な荷物を持ち上げようとしている様子です。彼はひざまずいて荷物の真下に入るので、見えなくなります。しかし、次に彼は背中を伸ばし、荷物全体を肩の上で揺らしながら立ち去るのです。または、潜水夫が、一枚一枚衣服を脱いで、一瞬空中で光を受けて身を翻したと思うと、緑の、暖かい、日の光射す水を通り、暗黒の、冷たい、凍るような水の所までもぐり、さらに、ぬるぬるした泥の中へまでももぐり、そして再び上へ、緑の、暖かい、日の光射す水の所へと、肺をほとんど張り裂けそうにして戻ってきて、ついには太陽の光のもとへ、水から上がってくるのですが、その片手には、水を滴らせて、彼が取りにもぐったものを握っているのです。彼が持って上がってきたのは、人間性です。しかし、すべての自然と新しい宇宙がそれと結びついているのです。その点については――つまり、人間性と自然一般のこの結びつきについては実際、話そうと思えばひとつまるごとの説教になってしまいますので、今夜は深入りできません。期待に添えないかもしれませんが、充分お許しいただけると思います。さて、こう考えればすぐに、宇宙の深みの底の底までもぐり、また光のもとへと昇ってくるこの大きな潜水の様式が、どれほどまでに自然界の原理に模倣され、反響しているか、誰でも分かるでしょう。土の中への種の下降と、植物としての再上昇。また、われわれのあらゆる精神生活においても、あらゆる場合に、何かを強く素晴しい輝くようなものにするために、まずそれを殺し、壊さねばならないことがあります。その類似は明白です。その意味で、受肉の教義はぴったり当てはまります。実際余りに良く当てはまるので、即座に、「余りぴったりしすぎるのでは?」という疑惑が浮かんでくるほどです。つまり、キリスト教の話がこの、下降と再上昇の構図を取っているのは、それが世界中の自然宗教の一部だからではないでしょうか?」C・S・ルイス「偉大なる奇跡」『偉大なる奇跡』101〜103ページ
[ii] コリント書より前に書かれたガラテヤ人への手紙1・4ではこう言います。「キリストは、今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神のみこころにしたがったのです。」罪のためにキリストがご自分を与えたのは、私たちを救い出すのが目的だったのですから、キリストが私たちの罪のために死んだことは、必ず私たちを救い出してくださるのです。
[iii] 「人の子」が苦しみ、死ぬ、とは「水と油ほどに結びつきようのない両極端の思想である。天来の人の子が苦難の僕になる。この二つの思想の超絶技巧的な驚くべき結合を行ったのはいったい誰なのか。その答えは、イザヤ五三章の光のもとで生きていた唯一の方、そしてこの結合を身をもって実演したその方にほかならないということである。私たちはそのことに、もっと驚かなければならない。」芳賀力『神学の小径 Ⅳ』、168ページ。
[iv] この「救われる(ギソーゼステ)」は、文法的には不定過去(アオリスト)ではなく、現在形です。「救われ続ける」であって、「どこかの時点で天国に入る」というニュアンスとは違います。