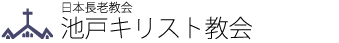2025/6/29 イザヤ書11章10〜16節「ねたみも敵も去る日」
イザヤ書は、紀元前8世紀、当時のイスラエル民族が北と南に分裂して、神の前に大きく道を踏み外していた時代にかかれました。ですから全体が民の罪、不正に対する非難と悔い改めの呼びかけで満ちています。しかし、今日の箇所はどうでしょうか。この11章の始まりから12章までは断固たる裁きという調子ではありません。11章から12章の二頁には、荒廃した森に若枝が生えるというイメージから始まって、全編が希望に溢れています。新しい始まり、全く新しい再出発が描かれていくのです。10節の「エッサイの根」とは1節に
エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。
と言われていた、ダビデ王の末裔としてやがてくる王のことです。その「エッサイの根」なる方がどんな方か、どんな世界を作るのか、9節までに不思議な光景で描かれていましたが、この10節からは別の絵を描かせるのです。
10その日になると、エッサイの根はもろもろの民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。
この王はイスラエル人だけでなく、諸国の民の旗として立つのです。イスラエル民族だけの希望や輝きに留まらず、国々がこの王を慕い求めるのです。そんな国際的な、民族や国家を超えた世界がここに語られます。それは具体的に、イスラエルの周辺、東西南北の国々の名前を挙げて、語られていきます。
11その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りの者を買い取られる。彼らは、アッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シンアル、ハマテ、海の島々に残っている者たちである。[i]
主は、天や神殿で待っていて、国々から集まってくる人々を受け入れる――ではありません。主ご自身が
御手を伸ばし…買い取られる
のです。
12主は国々のために旗を揚げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、ユダの追い散らされた者を地の四隅から集められる。
主ご自身が立ち上がってくださるのです。「地の四隅」という表現には、北の雪国、南の熱帯、東の陸の果て、西の海の果てまで、どこであろうと、そこから集める、という響きがあります。本当に主はそうしてくださる、と壮大な将来が語られているのです。
イザヤがこの言葉を語った当時は、こんなお気楽な将来像が語りやすかったわけではありません。その反対で、イスラエルの周辺の国々は同盟を組んだり戦争をしかけたり、ドロドロの国際情勢でした。同じ民族でさえ、北のイスラエルと南のユダに分断していたのです。12節に「イスラエル…ユダ」とありますが、こうして並べて書かれる事自体が、猛反発されかねない関係にあったのです。そして、その常識はずれな将来を、神はイザヤを通して告げているわけです。このことは次の13節でもわかります。
エフライムのねたみは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダをねたまず、ユダもエフライムを敵としない。
エフライムとは北イスラエルの中心部族で、北イスラエル王国の代名詞としても使われる呼び名です。そのエフライム(北イスラエル)とユダ(南ユダ王国)の、互いに対する妬みとか敵対関係がすっかり去るのです。逆に言えば、この時イザヤがこう語るのを聞く人々は、北と南に分かれて争い合い、不信も募っていたのです。長年の対立、不信、妬みや敵対。それも、赤の他人ではなくて、同じ部族、元は兄弟です。でも、家族や兄弟だからこそ、拗こじれた関係が難しいことを、聖書はたくさんの実例で刻んでいます。その修復の難しさを十分知った上で、その妬みは去り、敵対関係は変えられることを語る――その一つがここです。そしてそれは自分たちの内部だけでなく、周辺の国々にも及んでいく、新しい王の支配の始まりなのです。
14彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、ともに東の子らからかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アンモン人も彼らに従う。
これは前後関係、特に10節を念頭に読めば、彼らエフライムとユダがペリシテの肩――すなわち力、権力――も打ち負かす勢いで、エドムやモアブなど周辺から、神の民を集める描写でしょう[ii]。軍事力や人間的な力をも超えた神の力――心の妬みや敵意を終わらせる、主の力によって、周囲の国々も新しい王のもとに喜んで集められる。それが15、16節に続きます。
15主はエジプトの海の入江を干上がらせ、また、その焼けつく風の中で御手をその川に向かって振り動かし、それを打って七つの水無し川とし、履き物のままで歩けるようにする。
16残されている御民の残りの者のためにアッシリアから大路が備えられる。イスラエルがエジプトの地から上って来た日に、イスラエルのために備えられたように。
ここでは、聖書の二巻目、出エジプト記に出てくる光景が使われます。かつてエジプトにいたイスラエルの民が、四百年もの奴隷生活から解放されました。エジプトから出た民は、まもなく行手ゆくてを「葦の海」に阻まれましたが、主は強い風を吹かせて、海の中に道を開いて、エジプトからの脱出は果たされました。そのことと重ねて、ここでは将来のアッシリアからの解放が描かれます。この15節の「川」はアッシリアに流れる川、ユーフラテスです。滔々とうとうと流れる大河にも主は御手を伸べて、干上がらせ、七つの涸れ川にするので、主の民は難なく帰ってくるのです。アッシリア帝国のあらゆる束縛は無力になって、主はご自分の民を集めるのです。こうして主の民が大路を通って帰る光景に続いて、次回12章の喜びの歌が歌われます。
この11章12章は、今までのイザヤが語ってきたさばきや厳しい言葉とは打って変わった、喜びと希望の明るい将来像です。もちろん、こんな薔薇色の未来だとお気楽なことを言っているわけではなく、現在の罪、社会の不正や貧困、神を形ばかりに拝むだけの生活は非難されますし、その結果の荒廃が近いこともイザヤは語ってきました。その荒れ果てた末から、「エッサイの根」、若枝なる方が生え育ち、その方が支配する時に、今まで敵対してきた国々や身内のユダとエフライムも、ねたみや敵対は去って、世界の国々から主はご自分の民を集めてくださる――大路[iii]を備えて、帰らせてくださる、というのです。
余りにも明るすぎる希望、うますぎる話、と思うような言葉です。イザヤの時代の人々もそうだったでしょう。聞いている人々が信じたわけでも理解できたわけでもないでしょう。信じようと信じまいと、イザヤはここに条件も命令もつけずに、将来の事実として語っています。私たちが信じられない道を主は備えてくださる。そこにこそ聖書の希望があります。大路が備えられ、人間扱いされず奴隷やモノ扱いされ、すっかりそれに慣れきった人たちが帰ってくる。大路を歩くことを許されなかった人、日陰ばかりを歩く生き方が染み付いている人にも、主はその痛みや心のゆく手を阻む海の中に道を備えて、堂々と帰らせてくださる。私たちの心の妬みや、誰かとの間の敵対関係をも、主は終わらせてくださる。それは、考えれば考える程、信じがたいことですが、そう語られるのです。かつての出エジプトや聖書の出来事は、過去の栄光――昔の奇跡や懐かしい思い出ではなく、将来の解放、回復、祝福への確かな幻です[iv]。
そしてその確かな将来があるからこそ、それとは雲泥の差である現在の問題が嘆かれ、責められるのです。罪や暴力に慣れて「こんなもんだ」と諦めず、「いや、神の御心はこんなもんではないんだ。こんなに人が踏み躙られ、希望が失われているのはおかしいのだ」と言い続ける[v]。また、それでも耳を貸さずに頑ななまま歩み続け、遂には遠くの地に捕囚となった人々がその異国の地で、この言葉によって希望を持たせたのもこの言葉でしょう。「このどん底から、神は新しいことを始めると約束しておられたのだった」と思えたのです[vi]。
前回もお話ししたように、11章10節は新約聖書のローマ15・12で引用されます。イエスこそ「エッサイの根」であり、家族の確執や、民族の対立をも終わらせ、ともにおるようにしてくださる方。そして私たちの妬みや敵対を終わりにしてくださる方。この言葉を光に自分の心のうちを覗き込み、信じがたいこの約束を、今ここでも始めてくださるよう祈るのです[vii]。
「エッサイの根、私たちの希望、海に道を創造される主よ。私たちの願いよりも素晴らしく憐れみに満ちた将来をあなたは備えておられます。あなたこそが私たちの道、真理、いのちです。どうぞ導いてください。諦めや絶望や何物も、あなたの祝福を阻むことは出来ません。その約束に励まされて、今ここで、私たちの心を、問題を差し出しつつ、希望に生きさせてください」
[i] 「南とそのまた南には「上エジプト」(直訳「パテロス」〔新改訳〕)と「クシュ」、東には「エラム」と「バビロニア」〔新改訳「シヌアル」〕、北の果てには「ハマテ」、西へは辺ぴな「海の島々」(40・15〔新改訳「島々」〕を見よ)。全世界のいかなる遠方や辺ぴな所であっても、この壮大なる出エジプトを妨げることはできない。」、モティア、138ページ
[ii] パッと読むと、エフライムとユダが同盟を組んで軍事行動を起こし、東西の国々を征服していくように思えるでしょうが…。
[iii] 大路מְסִלָּהメスッラーは、イザヤ書に9回:イザヤ書7:3 そのとき、主はイザヤに言われた。「あなたと、あなたの子シェアル・ヤシュブは、上の池の水道の端、布さらしの野への大路に出向いて行ってアハズに会い、
11:16 残されている御民の残りの者のためにアッシリアから大路が備えられる。イスラエルがエジプトの地から上って来た日に、イスラエルのために備えられたように。
19:23 その日、エジプトからアッシリアへの大路ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人とともに主に仕える。
33:8 大路は荒れ果てて、道行く者は途絶え、契約は破られて、町々は捨てられ、人は顧みられることがない。
36:2 アッシリアの王は、ラブ・シャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところへ送った。ラブ・シャケは布さらしの野への大路にある、上の池の水道のそばに立った。
40:3 荒野で叫ぶ者の声がする。「主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために、大路をまっすぐにせよ。
49:11 わたしは、わたしの山々をすべて道とし、わたしの大路を高くする。
59:7 その足は悪に走り、咎なき者の血を流すのに速い。その思いは不義の思い。暴行と破滅が彼らの大路にある。
62:10 通れ、通れ、城門を。この民の道を整えよ。盛り上げ、土を盛り上げて、大路を造れ。石を除いて、もろもろの民の上に旗を揚げよ。
他に、35:8(そこに大路מַסְלוּלマスルール)があり、その道は「聖なる道」と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは、その道を行く者たちのもの。そこを愚か者がさまようことはない。)は、旧約聖書でここのみの言葉。
[iv] 出エジプト記11章で海の中に道が作られたのを、かつては「紅海」と訳していましたが、それは誤訳でもっと浅い「葦の海」と訳されるようになりました。それでも十分深い海ですから、奇跡は奇跡ですが、絵的には紅海じゃなくて残念、と私は最初思ったものです。でも、紅海を分ける姿には憧れても、自分の中の妬みや敵対が完全に去らされると信じることはもっと大切ではないでしょうか。
[v] 「すなわち、「現実」の厳しさから出発し、「過去」の原点に立ち帰り、そこから転じて「未来確信」を提示することによって、イザヤは「現実批判」をなしているのです。ですから、イザヤが指し示していることは、「むかしは良かった」と過去を夢見ることではなく、神によってもたらされる未来を前にして、その時代の人々が批判的責任を果たすように求めることであったと言えます。」 大島、『イザヤ書を読む』上、130ページ
[vi] 「このような聖句について、最後に一言述べなければなりません。ユダヤ民族の救済と復興を真に予言する預言がなかったならば、他の民族がそうしなかったのに、ユダヤ民族がどのようにしてそのアイデンティティと伝統を維持できたのか理解するのは難しいでしょう。もしこれらの「預言」がすべて事後に書かれたのであれば、それを受け入れる生き残った民族は存在しなかったでしょう。むしろ、故G・E・ライトの言葉を借りれば、「このような預言があったからこそ、ヘブライ人は民族の滅亡と兄弟たちの大半の絶滅を生き延び、主の民であり続けたのです」。つまり、預言的な約束によって生まれた確信があったからこそ、古代世界の終焉を告げたまさにその災難が、イスラエルの信仰に変革をもたらし、もはや国教ではなく真に普遍的な宗教へと変えたのです。」 オズワルト、11章16節の註解の結び、Google翻訳による。
[vii] ローマ人への手紙15・1〜13:私たち力のある者たちは、力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人ひとり、霊的な成長のため、益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、「あなたを嘲る者たちの嘲りが、わたしに降りかかった」と書いてあるとおりです。かつて書かれたものはすべて、私たちを教えるために書かれました。それは、聖書が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるためです。どうか、忍耐と励ましの神があなたがたに、キリスト・イエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうして、あなたがたが心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父である神をほめたたえますように。ですから、神の栄光のために、キリストがあなたがたを受け入れてくださったように、あなたがたも互いに受け入れ合いなさい。私は言います。キリストは、神の真理を現すために、割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人もあわれみのゆえに、神をあがめるようになるためです。「それゆえ、私は異邦人の間であなたをほめたたえます。あなたの御名をほめ歌います」と書いてあるとおりです。また、こう言われています。「異邦人よ、主の民とともに喜べ。」さらに、こうあります。「すべての異邦人よ、主をほめよ。すべての国民が、主をたたえるように。」さらにまたイザヤは、「エッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方が。異邦人はこの方に望みを置く」と言っています。どうか、希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であなたがたを満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。