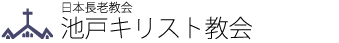2025/3/30 イザヤ書7章(1~9節)「『それゆえ』のインマヌエルの神」
1ウジヤの子ヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レツィンと、イスラエルの王レマルヤの子ペカが、戦いのためにエルサレムに上って来たが、これを攻めきれなかった時
当時、南のユダと北のイスラエルに分裂していたその北にアラムがあり、更にその北でアッシリア帝国が残忍な侵略で東西に勢力を増す、脅威が迫っていました。アラムとイスラエルとは「反アッシリア同盟」を結びましたが、ユダの王アハズが取ったのはアッシリアとの同盟を結ぶ「新アッシリア」政策を取った。そこでアラムとイスラエルの同盟国はユダに攻めて来た。この辺りのドラマは、Ⅱ列王記16章、Ⅱ歴代誌28章に詳しく書かれています[i]。最終的には「攻めきれなかった」とある通りで、イザヤ書を読む人々はその結末を知っていたでしょう。しかし、当時の人々はこの国難に必要以上に怯えてしまいます。
2ダビデの家に「アラムがエフライムと組んだ」という知らせがもたらされた。王の心も民の心も、林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。
この歴史的な出来事に揺れた、アハズ王への言葉が今日の7章です。
3そのとき、主はイザヤに言われた。「あなたと、あなたの子シュアル・ヤシュブは、上の池の水道の端、布さらしの野への大路に出向いて行ってアハズに会い、4彼に言え。『気を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない。…」
主はイザヤに子どもと一緒に王に遣わします[ii]。その名は「シュアル・ヤシュブ(残りの者が帰って来る)」という変わった名でした[iii]。直前の6・13にも「残る」とあるようにイザヤ書のキーワードです。イザヤはユダの民の罪を責めました。形ばかりの礼拝と、社会に蔓延る不正と搾取を神は裁きます。しかしその裁きは、容赦ないけれども絶滅ではなく残される者がいて、その者たちが帰って来ると約束が語られました。神への恐れと希望が込められたこのメッセージを、イザヤはわが子に名づけて、その子の存在そのものを証しとしたのです。今ここで、その子とイザヤは揺れ動く王の前に立ちます。アラムの王もイスラエルの王も「燃えさし」と呼び、その企みについては7節で「それは起こらない。それはあり得ない」と言わせます。実際アラムはこの3年後に、イスラエル王国も13年後にアッシリアに滅ぼされます[iv]。もう沈みかけていたこれらの国々は、恐れるには足らなかったのです。必要以上に恐れて、残酷なアッシリアとの同盟を選ぶ過ちを犯してはならない。それよりもまず、本当に恐れるべき方、主に耳を傾け、裁きと希望を語る主の声にこそ心を留めるべきです。神はイザヤとその子を遣わして、アハズに冷静な判断と、主に聴くことを迫りました[v]。しかしアハズはもうアッシリア王に縋ると決めていました。
10主はさらにアハズに告げられた。11「あなたの神、主に、しるしを求めよ。よみの深みにでも、天の高みにでも。」12アハズは言った。「私は求めません。主を試みません。」[vi]
こんな敬虔ぶった遠慮を口にしますが、実はもう主に頼らなくても生き延びられそうだから、今更煩わさないでくれ、主からの証拠など見たくもないのです[vii]。だからイザヤは怒ります。
13…「さあ、聞け、ダビデの家よ。あなたがたは人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。」
アハズの言葉の裏にある狡い態度を責めるのです。しかし、
14それゆえ、主は自ら、あなたがたに一つのしるしを与えられる。見よ。処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。15この子は、悪を退けて善を選ぶことを知るころまで、凝乳と蜂蜜を食べる。16それは、その子が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだ。
男の子が生まれて、インマヌエルと呼ばれる。欄外に「神はわれらとともにおられる、の意」とあります。その子が善悪の判断を身に着けるまでに、アハズが今恐れているアラムの王とイスラエルの王は廃れる。そのしるしが男の子であり、インマヌエル神は我らとともにおられるのしるしでもあります。
しかし、攻めて来る二人の王が恐れるに足らないだけではありません。17節では、ユダの王家、アハズの家にもアッシリアは脅威となると言われ、18節からは南のエジプトも、北のアッシリアも呼び集められて、19節で「彼らはみなやって来て」とあります。20節から最後25節には、主はアッシリアの王を使ってユダの王も民もすべて辱めること[viii]、雌の子牛と羊二匹からの沢山の乳から凝乳が造られて、みんなが凝乳と蜂蜜を食べる。それは、超良質な葡萄畑の地所も茨とおどろアザミ[ix]に覆われ、全地が荒れ果てて、牛と羊が放牧されるだけになる、という将来が語られます。大変な荒廃のようでもあり、牛と羊が歩いている様子は何とも平和な光景でもあります。22節に「すべての者が凝乳と蜂蜜を食べる」とあるのも鍵でしょう。王や貴族は贅沢に暮らしていて、貧しい者は食べる物にも事欠く、というのが当時の社会でもあり、現代でもある貧富です。そうした格差や贅沢が終わって、すべての者が簡素で十分な栄養で暮らすようになる。そのことも、14、15節で言われた、生まれる男の子が「悪を退けて善を選ぶことを知るころまで凝乳と蜂蜜を食べる」が予告するのです。そして、そのような人間の思惑や期待や貧富の身分がひっくり返された先に、シュアル・ヤシュブ残された者が帰って来るという言葉が成就して、そのことを通してインマヌエル神が我らとともにおられるという事がハッキリと示されるのです。
このインマヌエル預言は、直接にはここでイザヤがアハズ王に告げた言葉ですが[x]、クリスマスに必ず読まれる言葉でもあります。新約聖書で一番初めに引用される預言です。マタイ一章でマリアの胎に主イエスが聖霊によって宿った時、夫のヨセフに御使いが現れて言います。
…このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。「見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。[xi]
あの預言の元が今日のイザヤ書7章です。「インマヌエル神が我らとともにおられる」と語られたのは、平和な時代に、信仰篤い人々に対してではありませんでした。大国の脅威や国々の同盟と、どっちに就くのだと迫られる情勢――まさに今の世界も同じく、私たちの心も揺れている、その中での言葉です。
気を確かに持ち、落ち着いていなさい」「信じなければ堅く立つことは出来ない
との言葉は何も政治判断をするな、という極論ではなく、最善の、しかし難しい政治的な決断を、ともにいる主への信頼と祈りをもってしていく、ということでしょう。でもそれをも「主を試みません」などとしおらしそうに逃げるアハズに、主が与えられたのが「インマヌエル」預言です。しかも14節の冒頭は
それゆえ、主自ら、あなたがたに一つのしるしを与えられる
です。「それゆえ」です。主を煩わせ、信頼しない人に対しての「それゆえ」なら罰や断絶を与えても良かったでしょう? 人間の理屈ならそうです。主なる神の理屈は違う。「信じなければ堅く立つことは出来ない」と言われても信じないで倒れるしかない人間だからこそ、主は自らしるしを与えて、ご自身を信頼させてくださる。それが神の「それゆえ」です。なぜなら神は私たちとともにおられる神だからです。だから神の「それゆえ」があります。そしてここで、主自ら一つのしるしを与える、と言われた主は、やがて主自ら一つのしるしとなって、マリアの胎に宿り、丸裸の赤ん坊となって、生まれてくださいました。その貧しい誕生も、罪人の友となった生涯も、最後の死も、復活も、神が私たちとともにいます「しるし」です。
今も戦争が続くように、今日の箇所は歴史の動きの複雑さや儚さを見せつけます。でもその世界の中に、神はご自身がいることを、自ら胎に宿り、赤ん坊として生まれ、生きて、しるしとしました。イエスの生涯と教え、十字架の死と復活は、この歴史の中に与えられた、誰も否定することの出来ないしるしです。これ以上のしるしはありません。それさえ信じられない人かもしれませんが、だからこそ「それゆえ」と自らを差し出してやまないのが、我らとともにいます神、私たちの内にも宿ってくださる神です[xii]。この方にあって今を生きていけるのです。
「主よ、あなたはインマヌエル神が我らとともにおられると呼ばれる神。あなたこそ私たちの神、世界の王、歴史の支配者です。あなたの「それゆえ」が、私たちの考えとは全く異なる恵みであることを感謝します。どうぞその恵みに信頼しつつ、今を生きるための知恵と勇気を与えてください。気を確かに持ち、落ち着いて、恐れず、心を弱らせるな、との御声を私たちのうちに宿らせてください。敬虔そうで閉ざした心から救い出してください。いいえ、その私たちのうちに、宿ってください」
[i] これを「アラム・エフライム戦争」とも言います。列王記と歴代誌の二つの記事は、同じ事件に関して異なる解釈をしていて、興味深いです。
[ii] 前回6章から16年経っていますから、この子がいつ生まれ、何歳頃かは不明です。
[iii] 欄外参照。
[iv] 8節の「エフライムは六十五年のうちに、打ちのめされて、一つの民ではなくなる」は、具体的に何を指しているのかは諸説ありますが、紀元前671年の、エサルハドンが北イスラエルに他国民を移住させた時のこと(Ⅱ列王17・24)という説が有力かもしれません。
[v] 9節の「あなたがたが信じタアミーヌゥなければ堅く立つテェアーメーヌーことはできない」は、タアミーヌゥ(アーマン、支える、の使役能動態未完了形)とテェアーメーヌー(アーマンの受動態未完了形)の語呂合わせです。11節の「しるしを求めよシェアラ。よみシェオルの深みにでも、」も欄外にあるとおり掛詞です。
[vi] 主を試みた罪の事実は、出エジプト17・2に始まり、民数記14・22、申命記6・16、詩篇78・18、41、95・8で想起される。禁令の形では申命記8・3にも明言され、イエスはそれを引用してサタンの誘惑を退ける(マタイ4・7)。パウロも、Ⅰコリント10・9で「キリストを試みることのないようにしましょう」と警告する。
[vii] しかし、アハズは「主を試みません」と殊勝な態度を取りながら、「しるしを求めよ」とまで言われる主の申し出を払いのけることで、主を煩わせ、主を操作しようとしています。それは、いわば、主の上を行こうとすることであり、もっと悪辣な意味で「主を試して」いるに他なりません。
[viii] 20節の「頭と足の毛を剃り、ひげまでも剃り落とす。」とは、全身の毛を剃ることを嫌ったユダの民にとっては、屈辱的な体験を表します。文字通り、アッシリアの王が彼らの全身剃毛をするというよりも、屈辱的な扱いをすることの表現でしょう。
[ix] 聖書協会共同訳では「あざみ」と訳しています。
[x] 「それでも、このメッセージはアハズと彼の時代の民にとって、7世紀以上後に実現する出来事についてであるというよりは、何か重要であったに違いない。もしこの出来事が700年以上先のことを指しているにすぎないのなら、アハズとその時代の人々にとっていかなる重要性を持つことができただろうか。ここには遠くの成就と同時に近くの成就があり、その預言は近い将来と遠い将来の両方を指していた。神はダビデを通してメシアを送ることを約束なさったが、そのダビデの王位をタベアルの子が奪うのではなく、アハズに息子が生まれた。ヒゼキヤである。たぶん預言者は、すぐ近くに立っていた「若い女性」、その時は結婚しておらず処女だった人(この2つは同時であるのが当然と考えられていた)を指し示したのだろう。その女性との間に生まれるのがアハズの息子ヒゼキヤということになる。/だが、この解釈は少なくとも2つの大きな問題を提示する。(1)ヒゼキヤの誕生は奇跡的受胎の結果ではない。(2)ほとんどの年代記によると、ヒゼキヤは当時10歳くらいであった。第1の異議に対しては、これは預言における近い成就と遠い成就のつながりを誤解している、と答える。「今の」もしくは近い成就は、究極的な出来事によって完了することの詳細と期待の大部分をかなえることはほぼないし、ましてやすべてをかなえることはない。例えば、バプテスマのヨハネはエリヤの「霊と力」をもってやって来たのであり(ルカ1:17)、この点では来るべきエリヤであった。けれどもエリヤはなお、主の大いなる輝かしい日が来る前に再び来ることになっている(マラキ4:5)。同様に、反キリストはすでに多数現れているが、最終的な反キリストの性格や力と比べれば大した問題ではない(1ヨハネ2:18)。さらに、4世紀の間に5人の預言者が「主の日」に経験する5つの異なる危機を宣言したが、それでも主の最後の日がどのようなものであるかはまったく経験しなかった。同じように、「私たちは今すでに神の子どもです。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません」(Iヨハネ3:2、傍点は筆者)。ここでは同じ緊張関係が「今」と「まだ・・・・・・ない」の間にある。だからヒゼキヤは、預言者が考慮していたことをすべて成就したわけではない。とりわけ、預言者はダビデの家の複数性を表すものとして「あなたがた」と語ったのだから。/年代記の問題はどうなのか。イスラエルの王とユダの王の間の同期性には解決していない問題が1つ残っている。ヒゼキヤの治世における10年問題である。筆者は、シリア・エフライム戦争の年代を再吟味することで、この預言がダビデの王座に次に着く者の誕生を告知するために適切に配置されていることがわかると考える。それによって、最も偉大な子孫に至るまで、途切れることなく王家の系図が続いていることがわかるのである。/したがって、「almâh」という語が故意に使われているのは、この語がいつも処女である若い女性を指していたからである。神は、誕生に関して何か奇跡的なことがあること、もしその約束が近い成就の中で果たされないなら、最終的成就の時に果たされることを約束したのである。その人物がインマヌエル、「神が私たちとともにおられる」である。」「7:14処女が身ごもるとはどういうことか」(抜粋)『聖書難問注解旧約編』(いのちのことば社、2024年)445〜446ページ
[xi] マタイの福音書1・22~23。イザヤ書のヘブル語原文と違い、ギリシャ語訳になって、母がインマヌエルと呼ぶ、という部分が変わっています。イザヤ書の言葉には、処女なる母の、主体性が、驚きをこめて言及されていたことも、見落とされがちな視点です。
[xii] 「おとめ」なのか、については、オズワルドの解説が最も説得力を感じます。オズワルドの注解は次の通り(Google 翻訳による):「処女は身ごもる。イザヤがここで曖昧な almâ を明確な betûla 19 の代わりに使用した理由について断定することは不可能であり、alma にどのような意味を割り当てるべきかも明らかではありません。通常、与えられた意味は「結婚適齢期の若い女性」20 であり、妊娠が自然なものであることが明確に示唆されています。しかし、保守的な学者は、この言葉が旧約聖書で既婚女性を指すために使用されたことは一度もないと頻繁に指摘しています。21 そのため、彼らは、この言葉は性的に成熟しているが未婚の若い女性を示すと主張しました。そのような女性が処女であることは、ヘブライ社会では自明です。betûlâ の場合のように処女であることが主な焦点ではないとしても、それでも従います。英語の「maiden」は、同じ表示と意味合いに非常に近いです。このような理解には、七十人訳聖書の「処女」を意味する「パルテノス」の起源を説明するという重要な利点がある。これは、「結婚適齢期の若い女性」を選んだ注釈者たちが言及していないことだ。アルマが処女を暗示するものでなければ、七十人訳聖書の翻訳は説明がつかない。
しかし、イザヤがここで母親の処女性を強調したかったのなら、なぜ betûla を使わなかったのだろうか。ヤングは、betûlâ が「彼女は男を知らなかった」といった発言を伴うことが多いことに注目し、この語は曖昧な語であると主張する。しかし、これは明らかにそうではない。betûlâ には処女性以外の意味合いはないが、almâ にはあるからである。22 そこから導かれる結論は、預言者は処女性を強調したくなかったが、それを無視することも望まなかった(’išŝa または「女性」を表す他の語を使用することでそうすることもできたのだが)ということである。実際、彼はこの語の豊かさと多様性ゆえに、まさにこの語を使ったのかもしれない。ウガリット語の同根語(glmt)は、永遠の処女であると理解されていた女神について言及する際に使用されている。 23 イザヤが単に神話を翻案しただけだと認めるつもりはないが、24 彼がよく知られた言語形式を翻案したと考える人もいるかもしれない。その言語形式は、途中で何が起ころうとも、この預言の最終的な成就は普通の出来事ではないことを明らかにしている。
おそらく、ここで ‘almâ が使われているのは、この預言の二重の焦点によるものでしょう。短期的には、処女懐胎は主要な重要性を持っていなかったようです。むしろ、その瞬間に妊娠した子供は、脅威となる二つの国が滅ぼされたときには未熟であったということが重要なのです(16、22 節)。25 イザヤがここで betûlâ を使用していたら、アハズはおそらくその考えにとらわれすぎて、自分の時代との具体的なつながりを見逃していたでしょう。」