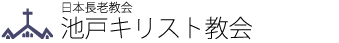2025/3/23 イザヤ書6章1~13節(1〜7)「御使いが飛んで来て」
「1ウジヤ王が死んだ年に…」
と語り出します[i]。ウジヤ王が死んだのは紀元前740年頃。それまで52年の長期間、国政を司った王です[ii]。神の目にかなう政治をして、国土も拡大したのですが、そのことに思い上がってしまい、晩節を汚してしまった王です。その王が死んで、国内の不正や諸問題は再燃しそうですし、周辺諸国では北方のアッシリア帝国が攻めて来ている。そういう不安要素だらけの
ウジヤ王が死んだ年に、私は、高く上げられた御座に着いておられる主を見た。
というのです。「御座」には欄外注があり「あるいは「王座」」とあります。地上の王が入れ替わっても、いと高き所の王座には主なる神が座しておられる[iii]。その栄光に、圧倒されます。
その裾は神殿に満ち、2セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ六つの翼があり、二つで顔をおおい、二つで両足をおおい、二つで飛んでいて、3互いにこう呼び交わしていた。
「聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。その栄光は全地に満ちる。」
4その叫ぶ者の声のために敷居の基は揺らぎ、宮は煙で満たされた。
精一杯想像してみてください。高い御座につき、かつ、その裾は地の神殿に満ちている神。そして、「セラフィム」とはここにしか出て来ない、何か燃えるような存在ですが、そのセラフィムたちが
聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。その栄光は全地に満ちる。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主…
と呼び交わし続けている[iv]。その神の輝きを目の当たりにして、イザヤは、
5私は言った。「ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れた者で、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから。」
聖ではない自分、汚れた自分を強烈に自覚せずにおれない。聖であるとは神の力や偉大さ、神々しさだけでなく、レビ記17章やローマ12章にあるように、倫理的に全きことです。利己心も悪も微塵もない、その聖なる輝きに照らされて、イザヤは自分の汚れ、とりわけ「唇の汚れた者」と言うように、嘘、妬み、暴言など、唇の汚れを自覚したのでしょう。これまでもイザヤは忠実な預言者として、清く生きようとしてきたはずです。しかし今、聖なる主を見て、イザヤは自分自身の汚れを絶望するのです。そして、聖なる神の前で、自分の汚れは大目に見てもらえるものではなくて、滅ぶしかない――汚れた自分が神を目で見るなら死ぬしかない。永遠の神を見ることは、生きている人間には到底耐え難い、圧倒的なことなのです。しかし、
6すると、私のもとにセラフィムのひとりが飛んで来た。その手には、祭壇の上から火ばさみで取った、燃えさかる炭があった。7彼は、私の口にそれを触れさせて言った。「見よ。これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も赦された。」
幻の中の神殿にあった祭壇から持ってきた燃え盛る炭をもって、イザヤの口・唇に触れて、罪の赦しが宣言されるのです。イザヤは滅びるしかないと思ったのに滅びません。どころか、
8私は主が言われる声を聞いた。だれを、わたしは遣わそう。だれが、われわれのために行くだろうか。」私は言った。「ここに私がおります。私を遣わしてください。」
と主の派遣の呼びかけに応えて立候補して、立ち上がる者になるのです。
イザヤの元に運ばれた炭は、祭壇の上から持って来た炭でした。生贄を焼くための木の炭か、焼かれた牛や羊の燃え滓の炭でしょう[v]。それは罪のための生贄かもしれませんが、数として圧倒的に多いのは「全焼のささげ物」です。祭壇には毎朝毎晩、折あるごとに絶えず全焼のささげ物が捧げられます[vi]。それは民の献身を表しました。動物に託して自分を主に捧げる――「私たちはあなたのものです。今日もしている仕事や日常生活、雑事や人生もひっくるめて、私たちは主のものです」という献身の告白でした。罪を犯した時は罪のための生贄が捧げられます。でも、その罪の生贄を捧げる祭壇は、全焼のささげ物を焼き続けている火の上、献身あっての罪の赦しです[vii]。全焼のささげ物が現す献身こそ、聖なる神に相応しい礼拝です。
このイザヤ書6章が型になって、私たちの礼拝、多くのプロテスタント教会の礼拝の構成が出来ています。賛美があり、その聖なる神の前に罪を自覚して告白をし、赦しの福音の言葉を聞き、その聖なる神に出会った者として、派遣されるという構成です。礼拝の終わりはお勤めの終わりではなく、派遣なのです。もし罰ばちが当たらないよう捧げもので勘弁してもらえばいいという宗教だとしたら、それこそ神を聖としない罪、滅ぼされるべき汚れたあり方です。
献身。今回、教会名簿と葬儀に関する希望を集めました。葬儀に関して献体を選んでいる方が何人かいます。自分の亡骸を使ってください、という選択です。勿論、自分の体が人目に晒されることに抵抗があって、と献体しないのも選択です。しかし、主に出会うとは、この方の前に自分が丸裸で、心の奥も過去もすべてが知られて、唇の汚れも何もかも、私以上にご存じであると知る出会いでもあります。そしてその聖なる神が近づいて、私に触れてくださることで、私たちは赦された者として新しくされ、派遣されていくのです。死んでからの献体より、生きている今の献身、このからだを献げ、私を通して御心がなりますように、との献身です。イザヤが「私を遣わしてください。」と言ったのも神の聖が下さった応答です[viii]。聖なる神は、ご自分の民に出会って、恐れと絶望しかない私たちに、滅びではなく赦しを与え、そしてその出会いに与った者として、私たちを派遣されるお方です。それが主イエスの生涯であり、十字架の死と復活です。それは、人間の罪の罰を取り除くだけでなく、再び神のものとして生きること――神への生きた聖なる供え物として自分のからだを捧げる歩みを与えるためでした[ix]。
9…「行って、この民に告げよ。『聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな』と。10この民の心を肥え鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。
不思議な言葉、厳しく不可解な言葉です。しかし、この言葉通り、この先もイザヤの言葉を聞いても頑なな応答をする人がこの後も続きます。それほど、人々の心は聖なる神が見えず、頑固で、汚れに平然としていました。どうしようもない…。だから、その先も徹底しています。
11私が「主よ、いつまでですか」と言うと、主は言われた。「町々が荒れ果てて住む者がなく、家々にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。12主が人を遠くに移し、この地に見捨てられた場所が増えるまで。13そこには、なお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。
飾りもガードも、頼みの綱や支えや、神に降参せずにやっていけると頑張っていたすべてが失われて、しかし、最後の最後に、こういわれる。
…それらの間に切り株が残る。この切り株こそ、聖なる裔。
それが何かはハッキリしませんが、滅びに見えてなおその先に「聖なる」何かが始まるという希望が語られます。この聖なる神と出会う6章なのです。
この9~10節は、実は新約聖書の四つの福音書と使徒の働きそれぞれで、計5回引用される言葉です[x]。主イエスと弟子たちもパウロも、伝道しながらこの頑なさの壁に直面したのです。しかしそれは他人事ではありません。イザヤも私たちも、主が出会ってくださることがなければ、自分の汚れに気づけないのです。聖なる主を知るなら、絶望的な罪の深さに気づきますが、そのイザヤに御使いが飛んで来て、罪の赦しと、派遣を下さいました。私たちに、主イエスが近づいてくださり、十字架に釘打たれた御手、今も生きている御手で触れて、罪の赦しを下さり、今日もまた、ここから派遣してくださいます。それで立派な成果や、大きな働きは期待しなくていい。主がその人に出会ってくださる時に、分かることだからです。私たちは、自分が毎週、毎日、聖なる主を仰いで、あるがままを主に捧げながら、遣わされた場所で歩むことです。私たちの日々と、唇の言葉と、存在そのものを、主のものとして生きるのです。
「聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。イザヤの幻のように、今この会堂にあなたを見るならば…、私たちの家が神殿ならば…、王や指導者が失せた思いをする時、なお王座におられるあなたを見る目を持つことが出来れば、と畏怖の念を頂きます。今日この礼拝で、あなたが私たちに出会ってくださいます。罪と赦しを頂きます。そしてここから派遣される全地にあなたの栄光は満ちています。どうぞ日々私たち自身をあなたに捧げさせ、あなたのものとしてください」
[i]これはイザヤがエルサレムの神殿にいた時のことかもしれませんし、違うところで見た幻かもしれません。
[ii] Ⅱ列王15・1~7、Ⅱ歴代26・3~15、参照。
[iii] 前回5章で暗澹たる様子が描かれましたが、その流れをハッとさせる、王なる主の幻なのです。
[iv] 永遠に歌い続けても飽きはしない。いや、その一回毎に、ますます賛美の念を深めずにおれない、そういう礼拝の様子を見ます。
[v] Oswalt.
[vi] 幕屋、後には神殿となった礼拝の場には、生贄を焼く「祭壇」(出エジプト記27・1~8)だけでなく、「香の祭壇」(30・1~11)もありました。このイザヤ書6章の「祭壇」が、どちらの祭壇かは意見が分かれますが、「香の祭壇」も「最も聖なるもの」に関わります(出30・11)。そもそも、この二つの祭壇を分けてここで想定する事自体、意味があるのか、とも言えます。
[vii] また罪の生贄を捧げる際には、全焼のささげ物が伴うのです:レビ記8・14~21、9・3~22、12・6~8、14・12~31、15・15、29~30、16・3以下、など。
[viii] 罪赦された感謝とか、イザヤの勇気や純粋さ、というよりも、これも恵みです。
[ix] ローマ12・1:ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です。
[x] マタイ13・14~15(こうしてイザヤの告げた預言が、彼らにおいて実現したのです。『あなたがたは聞くには聞くが、決して悟ることはない。見るには見るが、決して知ることはない。15この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように。そして、わたしが癒すこともないように。』)、マルコ4・12(それはこうあるからです。『彼らは、見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って赦されることのないように。』」)、ルカ8・10(イエスは言われた。「あなたがたには神の国の奥義を知ることが許されていますが、ほかの人たちには、たとえで話します。『彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないように』するためです。」、ヨハネ12・39~40(イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。40「主は彼らの目を見えないようにされた。また、彼らの心を頑なにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして、わたしが彼らを癒すこともないように。」41イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。)、使徒の働き28・25~27(互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言、次のように言った。「まさしく聖霊が、預言者イザヤを通して、あなたがたの先祖に語られたとおりです。26『この民のところに行って告げよ。あなたがたは聞くには聞くが、決して悟ることはない。見るには見るが、決して知ることはない。27この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように。そして、わたしが癒すこともないように。』)。また、ローマ11・8(「神は今日に至るまで、彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられた」と書いてあるとおりです。)も。